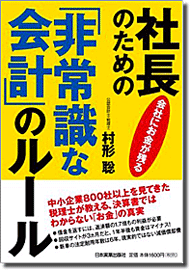損益計算書は何のために作るのか?:社長のための「非常識な会計」のルール(1/3 ページ)
連載「社長のための“非常識な会計”のルール」について
本連載は、村形聡著『会社にお金が残る 社長のための「非常識な会計」のルール』(日本実業出版社)から一部抜粋、編集しています。
「決算書」の数字を鵜呑みにしてはいけない! 決算書の数字だけを見て「ウチの会社は儲かっている」「節税しよう」などと勘違いしてはいけません。決算書の数字は経営の実態を映していないのです。そもそも決算書とは、税務の申告や投資家への報告のために作られるもの。投資家などいない中小企業にとっては、あまり意味がありません。実際、儲かっているはずなのに「お金がない」と感じている社長は多いのではないでしょうか?
本書では、実際の決算書の数字を使いながら、会社の実態が見える新しい会計、会社にお金を残す会計のルールを提案! 例えば「新車の法廷耐用年数は6年。減価償却費も6年で計算するが、実際は3年で買い替えるなら、3年間で車1台分を貯める必要がある」「借金は、税引後の利益からしか返済できない。つまり、利子や借り入れた金額だけでなく、儲けにかかる法人税も計算に入れておく必要がある」など、これまで見逃してきた指摘が盛りだくさん。本書のルールにのっとって収支計画を立てれば、必ず会社にお金が残り、儲かる会社に変われます。
損益計算書の常識をおさらい
最初に、決算書に関する常識についてお話ししましょう。
決算書の中心的な存在は、なんと言っても損益計算書(P/L)です。損益計算書とは、その名のとおり、その企業の「利益」を計算しています。
一般的に「利益」とは「儲け」のことですから、企業が黒字なのか赤字なのか? 儲かっているのか儲かっていないのか? という話の際には、ほとんどの場合この損益計算書で計算された「利益」のことを指しています。
しかしながら「損益計算書」の「利益」というのは、いくつかの会計ルールに従って計算されたものですから、その計算の前提となるルールを知っておかなければなりません。
期間損益計算
まず重要な点は、損益計算書の利益計算は「期間損益計算」という計算方法がルールとして定められていることです。
すべての会社は、少なくとも1年に1回は利益を計算しなければならないことが法律で定められていますので、会社はその法律に従って利益を計算するための計算期間を自分で決めておかなければなりません。
しばしば「決算日」という言葉を耳にすると思いますが、この「決算日」というのが、期間利益を計算する計算期間の締め日を表しています。決算日が3月31日であれば、損益計算書の利益計算は、4月1日から3月31日までの1年間を対象とし、その1年間の利益を計算することになります。
平たく言えば、損益計算書は、毎年毎年の利益だけを計算するということです。
発生主義会計
次に重要なルールは、利益を計算する場合に、現金や預金といったお金の増減ではなくて、経済的な価値の増減に基づかなければならないというルールです。
ちょっとややこしい言い方になりましたが、例えば、代金後払いの約束で商品を売った場合、まだ販売代金を受け取っていないとしても、「儲かった」と考えなければいけないということです。
このようにお金の収支を離れて、利益を計算する方法のことを「発生主義」と呼びます。
費用収益対応の原則
損益計算書の利益計算には、もう1つ面倒なルールがあります。それが「費用収益対応の原則」です。
例えば、商品を100個仕入れてその代金を支払ったとしましょう。商品100個分のお金は、すでに使ってしまっています。そしてその商品のうち30個が、どうにもこうにも売れ残ってしまったとしましょう。この場合の利益計算は、売れた分の70個の仕入代金のみが費用となります。売れ残った30個分は費用になりません。
この「費用収益対応の原則」を簡単に言うと、費用は売上に対応するものだけに限定するというルールです。だから、売れ残った商品は売上にかかわっていないものとして、費用にすることができないのです。
関連記事
 日本で起業するのはなぜ難しいのか――アメリカのほうが優れている点
日本で起業するのはなぜ難しいのか――アメリカのほうが優れている点
「会社を立ち上げる際、日本よりも米国のほうがやりやすい」――。こういった声をよく聞くが、なぜ米国のほうが起業しやすいのか。研究者という安定を捨て、米国で製薬ベンチャーを立ち上げた窪田良さんに、話を聞いた。 弥生が起業家の悩みをまとめたリポートを公開――継続企業を作る法則とは?
弥生が起業家の悩みをまとめたリポートを公開――継続企業を作る法則とは?
弥生は創業経営者1501人へのアンケートをまとめた「開業リポート2013年改訂版」を発表した。回答者の55.8%は「起業1年目の売上が計画の半分以下」として、計画と現実の違いが明らかとなった。 決算書は読めなくても大丈夫
決算書は読めなくても大丈夫
ヘッジファンドや物言う株主、さらには“ハゲタカ”とも渡り合わなければいけない、現代の日本企業。金融市場の中で企業が生き抜くために必須の知識、それが「ファイナンス(財務)」です。今日からスタートするのは、会計が苦手だったという元証券マン・保田隆明氏が、“とにかく分かりやすく”ファイナンスについて説明する新連載。所要時間は毎回約10分です! 会計、レシート入力がスマホで手軽に――弥生がベンチャー企業と提携
会計、レシート入力がスマホで手軽に――弥生がベンチャー企業と提携
弥生はスマートフォンアプリを開発するクラウドキャストとの資本/業務提携を発表した。小規模企業向けに提供する会計やレシート入力アプリの開発、マーケティング、販売で協業を進めていく。 確定申告の準備をスマホで――撮って記録する会計サービス「Taxbird」
確定申告の準備をスマホで――撮って記録する会計サービス「Taxbird」
Taxbirdは、レシートをスマートフォンで撮るだけで確定申告の準備ができる会計サービス「Taxbird」を開始した。利用料は月額1980円。 個人事業主が語る、独立する人が知っておくべき会計経理
個人事業主が語る、独立する人が知っておくべき会計経理
独立、開業をする人は何かしらの専門知識を持っている場合が多い。一方で「経理や税金は全然分からない」という人も多いはずだ。本記事を読めばそうとは言えなくなるはずだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング