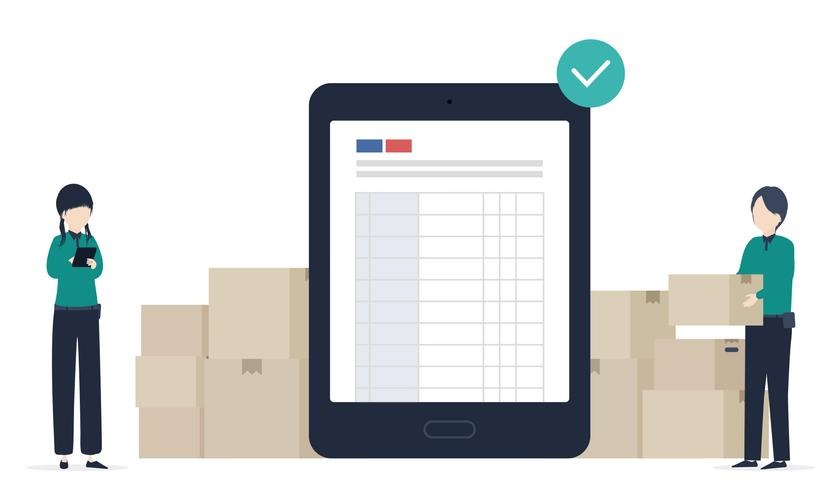定額減税の給与明細への明記義務化、経理現場で不満爆発 作業約50時間増える試算も
6月から始まる定額減税を巡り、政府が給与明細に所得税の減税額の明記を義務付けたことで、企業の経理現場などでは不満が爆発している。国民に早く減税を実感して欲しいという政府の思惑が見え隠れするが、事務負担が増える現場にとっては「ありがた迷惑」だ。減税条件も複雑で、企業によっては一連の対応で約50時間の事務負担が増えるとの試算もある。政府の補助金終了で電気料金が6月使用分から引き上げられることもあり、減税の恩恵よりもさまざまな負担感が顕在化しそうだ。
明細義務化で増える事務負担
定額減税は、1人当たり所得税3万円と住民税1万円を本来の税額から差し引く形で行う。サラリーマンの場合、勤務先から受け取る給与や賞与から源泉徴収される所得税を6月分から順次差し引く。対象は年収2000万円以下の納税者で、納税者と配偶者、子ども1人の世帯なら計12万円の減税となる。
ただ、企業は減税分を差し引いて給与を支給すればいいというわけではない。今回の減税対象は、所得税法上で控除扶養親族として定めている16歳以上の扶養親族だけでなく、16歳未満も含まれる。そのため、企業は新たに従業員の扶養人数などの情報を集め直さなくてはならない。その上で、減税金額を算出し、給与に反映させていくなどの作業工数が増える。
さらに、今回、毎月の給与明細に所得税減税額の記載が義務付けられたことで、年末調整の給与支払明細書にまとめて減税額分を記載しようとしていた企業にとっては、新たな仕組みを整えなければならなくなる。
クラウド会計ソフトなどを手掛けるfreeeの試算によると、減税対象者の詳細抽出や減税額算出、計算、明細書類の出力など一連の定額減税に関わる作業が追加された場合、企業の経理担当者の事務負担が計約40〜52時間増えると試算する。
罰則なく義務化が形骸化も
負担が増えるのは企業だけではない。所得が少なく減税額が本来の税額を上回る場合は現金が給付されることとなり、その作業は市区町村が担う。一部では、給与取得者の大半で給付が発生する見込みの自治体もあるという。都内企業の経理担当者からは「最初からすべて現金給付で対応してもらった方が、企業と自治体の双方の作業が楽になる」と不満の声が漏れる。
大手税理士法人「辻・本郷税理士法人」の菊池典明税理士は、「今回の定額減税制度を理解するには数十ページに及ぶ手引書を読み込まねばならず、従業員などからの質問対応、システム反映状況など目に見えない負担も生じる」と指摘。「freeeの試算(約40〜52時間の事務負担の増加)以上の負担がかかるのではないか」とみる。
また、菊池氏は減税額の給与明細への明記義務化についても、「通知が直前すぎる」と苦言を呈す。給与明細に減税額明記をしなかった場合も罰則は科されないといい、「義務化は形骸化している」と強調する。(西村利也)
関連リンク
copyright (c) Sankei Digital All rights reserved.
Special
PR