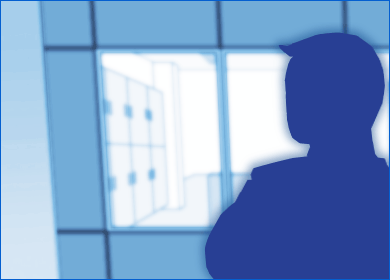いったい、いつの間に:大口兄弟の伝説(1/2 ページ)
営業コンテストも大詰め。吉田和人率いるC市営業所も最後の頑張りを見せていたが、和人本人やスタッフも疲労がたまり、本来の力が発揮できないでいた。そんな時、大口兄弟が県内でも有数の大企業、竹田食品のアポイントを取ってきたのである。
あらすじ
ビジネス小説「奇跡の無名人たち」第1部の続編「大口兄弟の伝説」――。営業所の存続をかけた営業コンテストを前にして、順調に契約数を増やしていたC市営業所。問題は、大企業しか攻める気のない「大口兄弟」のタカシとショージ。2人はそれぞれ過去の失敗を「リベンジしたい」と胸に秘めていたが、なかなか契約が取れないでいた。そんな折り、営業所のオタクが過労で倒れ、本部の査察で資料作りを担当するチェッカーが精神的に追い込まれ、息子のケガでマザーが会社を休んだ。そんな時、大口兄弟が県内でも有数の大企業、竹田食品のアポイントを取ってきたのである。
さすがに疲れがたまっていた。和人は、その日は昼まで寝ることにした。午後から出社し、19時からのプレゼンに備えて、クライアントである竹田食品の会社情報をチェックした。
創業寛永2年。1749年だ。元々は味噌を作っている会社だった。第二次世界大戦後、冷凍食品が大当たりした。C市営業所の管轄内だが、営業所からは北に30キロぐらいの距離にある。社員数は5000人。県内でも有数の大企業であり、東京、大阪にも支社がある。本社内には工場と物流センターがあり、1500本の電話回線がある。ここと契約できれば、まず間違いなく全国でトップだろう。
しかし、老舗中の老舗である。決裁が降りるまでに何人の部課長と役員の判子がいるのだろうか。和人には想像できなかった。
大口兄弟は、別の客先から車で直行するとのことだったので、和人は電車とタクシーで行くことにした。駅から拾ったタクシーは当然のように社名だけで和人を目的地まで連れて行った。
7月である。夜の7時でも薄明るい。郊外のせいだろう。まだ暮れきっていないのに、金星がやたらと大きく見えた。雲ひとつない群青色の空である。和人はしばし現実を忘れて見入ってしまった。以前クオーターと一緒に聞いた、モーツアルトの交響曲第41番の最終楽章のメロディーが心の中で鳴り響いた。
和人の心に勇気がわいてきた。きっと取れる。
大きな味噌樽のオブジェが置いてある正面玄関は、すでに閉まっていた。裏口で守衛に来意を告げると、内線電話で総務部につないでくれた。
数分後、谷と名乗る総務課長が降りてきた。大口兄弟はすでに来ていて、プレゼンの準備中だという。
「夜分にすみません」。和人が申し訳なさそうにいう。
「いえいえ。こちらこそ、こんな時間にお呼び立てしてしまって。なにぶん部長も忙しいもので」
「無理を言ってくださったんでしょう?」
谷はそれには答えず、話題を変えた。
「最初は、どこのチンピラかと思いましたよ」。苦笑しながら、谷は言った。
「はあ、申し訳ありません」
「いえいえ。まあ、アポはあったんだけど、まさか御社のような有名な電話会社の社員には見えませんでした。適当に話だけ聞いて、帰ってもらおうと思いました」
和人はただ恐縮している。谷の話は続いた。
「いったいどんなことを話すのかちょっと興味もあったんです。そしたら、いきなり1円切手の絵を見せて、前島密(ひそか)がどうこうって言い出すじゃありませんか。何かと思えば日本の電話の歴史の話。私はこう見えても歴史小説を読むのが趣味で、ついつい話に引き込まれちゃったんです」
あいつら、ちゃんとオレの営業トークを学んでたんだ。和人はちょっとだけ目頭が熱くなった。しかし、何が幸いするか分からない。本当はいきなりする話ではないんだけどな。
「なんか20分ぐらい歴史の話をしていたなあ。どうも勉強は苦手らしくて、ちゃんと覚えていなくて。こっちもフォローしましたよ。で、終わってから、それで何の話をしに来たんだと聞く羽目に」。谷は思い出し笑いをした。
「そしたら、マイラインの契約替えをして欲しいってことで、じゃあうちのメリットを説明してみろって言ったら、ちゃんと説明するんです。こっちは正直バカにしていたから、びっくりしちゃって」
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- NTTデータ、仮想化基盤「Prossione Virtualization 2.0」発表 日立との協業の狙いは
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路
- Apple、「macOS」や「iOS」に影響するゼロデイ脆弱性を修正 悪用確認済み
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説
- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散