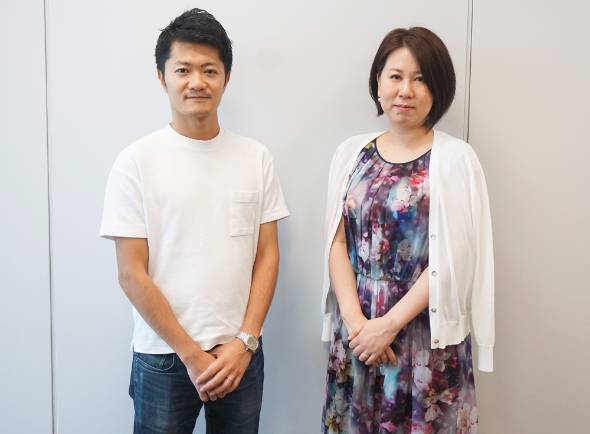ソフトバンクが新卒の「ES選考」をAIに任せた理由:HR Tech最前線(2/2 ページ)
評価基準のばらつきを統一させる
――もともと人事部は、どのようにしてESの合否を決めていたのですか?
中村: 具体的なことはお話できませんが、弊社にはいくつかの「求める人物の条件」があります。「あなたが過去に努力してきた体験を教えてください」などといった設問への回答文章の中から、その条件とどのくらい一致しているのかを採点します。
しかしその判断基準については、結局は読んだスタッフ本人の感じ方次第という部分があり、アナログでした。すると、どうしても採用経験が浅い若手とベテランの間で評価基準にばらつきが出てきてしまいます。
――そこで、属人的な評価基準をワトソンで統一しようと。
中村: はい。「こういう人を合格にしてください」とそれぞれのスタッフに評価基準を叩き込むのではなく、正解の情報(過去のデータ)をワトソンに学習させる方が、公平な選考ができるわけです。
評価基準が統一されるので、受験者は誰にどう評価されるのかという「運」に左右されることなく受験することができます。ワトソンの判断だけで不合格になることはありませんし、選考結果を今までよりも早くお伝えすることが可能になりますので、受験者にも大きなメリットがあると考えています。
スタッフは自社のアピールに注力
――ES処理を自動化したことで、採用スタッフの仕事はどう変わっていきますか?
中村: 選考のプロセスを効率化することで、より対面でのコミュニケーションに注力できるようになります。
「見極める・選ぶ」といった仕事はどんどんAIに置き換わっていくでしょう。一方、人間は「対話」を通じて自社を好きになってもらう活動が仕事の中心に変わっていくと考えています。
例えば、技術的には「Pepper」に会社の説明を任せることが可能です。しかし、学生は単に事業内容をインプットしたいだけではなく「どんな人が、どんな風に説明しているのか」を見ているわけです。
「この人たちと一緒に働いてみたい」と相手の心を動かして優秀な人材を集めるためには、やはり人によるコミュニケーションが欠かせません。人事担当者が学校に直接出向いて自社について説明するなど、学生と直接関わる機会を積極的に増やしていきたいですね。
ESを処理するという機械的な作業を自動化することで、より重要なコミュニケーションの部分に力を入れることができるようになるわけです。内定者のフォローにもより時間を使えるようになるので、内定者が入社前に辞退してしまうリスクの軽減にもつながっていくでしょう。
――今後は、面接の自動化も考えているのでしょうか。
中村: それは難しいですね。面接はESと違い、単なる選考ではなく、志望度を高めてもらうための要素も含まれています。
実際、担当した面接官の印象によって志望度が変わる学生も多いのです。近年、AIに面接を任せるサービスが出てきていますが、当社としては慎重に検討していきたいですね。
――なるほど。本日はありがとうございました。
関連記事
 活躍できる職場をAIがレコメンド 人事業務の最適化で「輝ける人を増やす」
活躍できる職場をAIがレコメンド 人事業務の最適化で「輝ける人を増やす」
採用活動、人事配置などの人事業務は属人的な判断に頼る部分が多く、まだまだ合理化されていない領域の1つだ。そのような中、人事業務にテクノロジーを掛け合わせた「HRテック」(Human Resource Technology)と呼ばれる取り組みが本格化しつつある。 AIは優秀な人材を採用できるのか
AIは優秀な人材を採用できるのか
企業の採用業務にAIを活用する動きが進んでいる。AIが採用後の結果まで自己学習するようになれば、今後は「採用の基準」もAIが作るようになるかもしれない。 いま“逆求人型”の就活が必要とされるワケ
いま“逆求人型”の就活が必要とされるワケ
いま“逆求人型”の就活が盛り上がりを見せている――。就活定番のイベントといえば合同企業説明会、いわゆるゴウセツ。しかしいま、こうした従来の就活スタイルを変える新しい風も吹き始めているという……。 AIが働かないと私たちは貧しくなる
AIが働かないと私たちは貧しくなる
人口減少による著しい人手不足が今後も加速していく可能性が高い日本。このままでは、あらゆる業界で過労問題が発生するだろう。「AIが仕事を奪う」という心配をしている場合ではない。AIに働いてもらわなければ経済(社会)が回らなくなるという事態になりかねないのだ。 上司との良質な対話がストレスをなくす? ヤフーが本気で取り組む1on1プロジェクトとは
上司との良質な対話がストレスをなくす? ヤフーが本気で取り組む1on1プロジェクトとは
企業にとって重要な課題である離職率の抑制、メンタルヘルス対策、そして従業員の生産性の問題。これらの問題を解決するヒントがどうやらヤフーの人事施策にありそうだ。一体どんな人事施策なのか……。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング