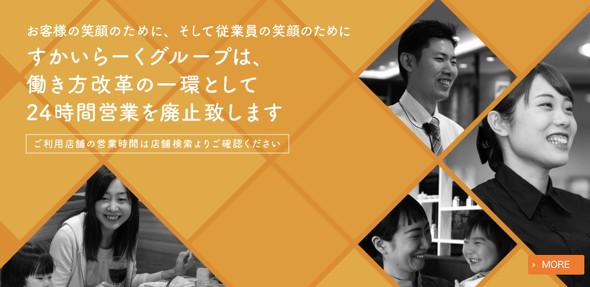すかいらーくの「24時間営業撤廃」を手放しに喜べないワケ:古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」(1/3 ページ)
1月20日、著名ファミレスの「ガスト」や「ジョナサン」を手がけるファミリーレストラン最大手の「すかいらーくホールディングス」は、2020年4月までに24時間営業を全廃すると発表した。1972年から50年近く続いた深夜営業は、人手不足や夜間の客足減を背景として廃止される形となった。
本件はなぜか「働き方改革」という文脈で片付けられやすい。しかし、問題はそれほど単純ではない。時短営業のきっかけが違法残業や過酷な労働によるものであれば話は別だが、今回は人件費の高騰や、夜間の客足減速によるものだからだ。
そもそも夜間に営業しないという方針は、深夜に働きたいという労働者の労働機会が確保されないため、多様な働き方を容認する「働き方改革」の趣旨からしてもズレた見方であるといえるだろう。このことは、トヨタが夜間のみ働くことのできる期間従業員制度を先月導入したことからもいえることだ。
筆者がすかいらーくの24時間営業撤廃を手放しで喜べない理由を端的にいえば、内部で増加するコストを、すかいらーく自身で吸収していることによる経済的なリスクにある。
営業時間の短縮は新たな”実質値上げ”?
24時間営業の撤廃、つまり営業時間の削減は、近年スーパーなどでも目立ち始めた、新たな”実質値上げ”の類型だ。
実質値上げといえば、主にコンビニチェーンや、製菓メーカーの弁当や菓子が槍玉に挙げられやすい。例え価格は据え置きでも、量が減ったり、低グレードの原料になったりという変化が生じれば、消費者の得られる効用は目減りする。これが典型的な「実質」値上げだ。
一方で、近年増加しているのがサービス面での実質値上げだ。通常、外食や小売等の販売価格には、原価に加えて、サービスにかかる費用も加味されている。例えば、百貨店や家電量販店であれば、商品を展示したり、従業員が丁寧に顧客対応を行ったりするというサービスが行われるため、そのようなサービスがないネットショップに比べて価格が高くなる傾向がある。
営業時間の短縮は、同じ価格で「いつでも開いている利便性」というサービスが低下していることになる。したがって、営業時間の短縮はサービス面での実質値上げとして整理される。では、なぜサービス面での実質値上げが問題になるのか。まずは外食業界の構造的問題から考えていこう。
関連記事
 増加する「黒字リストラ」 垣間見える企業の苦しい“ホンネ”
増加する「黒字リストラ」 垣間見える企業の苦しい“ホンネ”
2019年にリストラを実施した企業は27社に増加、人数も6年ぶりに1万人を超えた。注目すべきは、「黒字リストラ」事例の増加だ。業績が好調にも関わらず、企業が早期・希望退職を募った上場企業は、リストラ実施企業のうち、実に34.4%。これは40年前のGE的経営が日本にも広がっているのだろうか。 ゴンチャ新社長の原田氏がタピオカブーム“最後の希望”の理由
ゴンチャ新社長の原田氏がタピオカブーム“最後の希望”の理由
SNSで大きな話題を呼んだのが、国内大手タピオカ飲料店の「ゴンチャジャパン」社長人事だ。同社は12月1日付で原田泳幸氏を新たな社長に任命した。冷たい飲み物というイメージが強いタピオカの「冬越え」問題や、大手カフェチェーンなどのタピオカ参入という競争激化も業界全体の課題になりつつある。 freee“10倍値上げ”問題から考えるサブスクエコノミーの落とし穴
freee“10倍値上げ”問題から考えるサブスクエコノミーの落とし穴
今週上場したfreeeの波紋が後を引いている。freeeが提供する法人向け会計サービス内容の改定が今月上旬に発表され、これが実質“10倍値上げ“になるとSNS利用者の間で解釈されたためだ。 ガストやジョナサンの24時間営業廃止へ すかいらーくHDが人手不足受け決断
ガストやジョナサンの24時間営業廃止へ すかいらーくHDが人手不足受け決断
 「ロイホ24時間営業廃止」の正しい読み方
「ロイホ24時間営業廃止」の正しい読み方
ファミレスの「ロイヤルホスト」が2017年1月までに24時間営業を廃止するという。大手マスコミは「外食産業の営業時間短縮は最新トレンド」といった感じで報じているが、ロイホの場合はちょっと違う。というのも……。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング