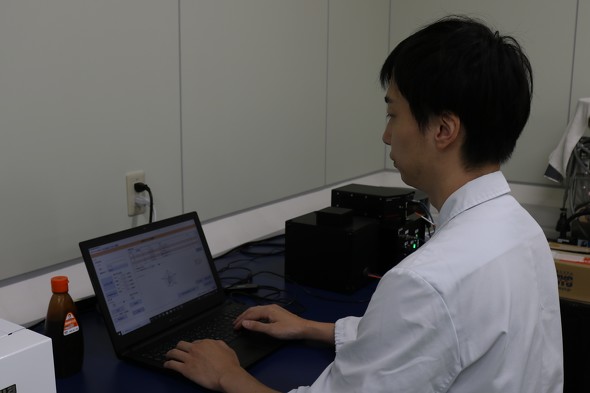オタフクが作った「“この味”に近いソース」を探すAI レシピ開発の属人化を解消
【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!
生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」
【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)
【視聴】無料
【視聴方法】こちらより事前登録
【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。
生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。
多くの読者になじみ深いだろう「お好みソース」を始め、液体調味料を開発・製造しているオタフクソース。実は、新たに開発する商品のうち9割が特注品だ。スーパーに並ぶ商品のような「オタフクマーク」はつけないもので、惣菜用のとんかつソースや飲食店のお好み焼きソースとして使われる。
こうした特注品の試作は、社員の経験やスキルによって所要時間が大きく変化する分野だ。属人化の課題を解決しようと、産業システム事業などを手掛けるIHIと同社が共同で、AIを用いた新たなシステムを開発した。一体どのようなシステムなのか。また、業務プロセスにAIを導入するに当たり、障壁になったこととは? 研究室長の吉田充史氏に話を聞いた。
「あの商品に近い味」を探すAI 経験・スキルによる差の解消目指す
オタフクソースが開発する特注品のうち3〜4割程度が、「他社のあの商品の味に近づけてほしい」と注文される「ベンチマーク品」だ。ベンチマーク品の開発はかなり時間のかかる作業だと、吉田氏は話す。
目指したい味のサンプルがある場合、まずは分析装置で成分を測定する「理化学分析」や、人が味見をして評価をつける「官能評価」を行う。そうして得た分析データや「甘い」「しょっぱい」といった言語データを、同社が保有している1万5000以上もの製品や試作品のデータと照合して、近いものを探す。言語検索は、完全一致でなければヒットせず、知識や経験が必要だ。
検索にヒットしたデータは、一つ一つページを開いて中身をチェックし、記載されている原材料から味をイメージする。過去に近い味を作った経験があれば、原材料の配分比を見てイメージできるが、経験年数が浅い社員にとっては大きな手間だ。作業の所要時間は人によって異なるが、30分〜2時間程度かかるという。
呼び出したレシピをベースに、付加価値のある原材料を加えたり、「この地域で今好まれている味」など同社の分析を基にした改良を加えたりしながら、試作と提案を繰り返し、特注品を作り上げていく。これが従来の流れだった。
一連の作業の中でも、社員の経験によって所要時間の差が大きい「レシピ検索」をAI活用で短縮化したのが、今回の新システムの要点だ。
蓄積してきたデータの中から、AIがベンチマーク品に近い味を見つけ出し、類似順に並べて表示する。言語データの検索は完全一致している必要はなく、特徴を言語化している文章でも検索可能になった。
また、新たに分光スペクトルで取得したデータも使用することにした。光を波長として表し、成分ごとの強さを見やすく配列するものだ。分析の精度が向上したほか、社員の主観や既存のカテゴリに縛られず、製品の特徴を把握できるようになった。
従来の方法で仮に1件1時間かかっていたとすると、新システムの活用で5分に短縮できれば、ベンチマーク品の試作開発効率は7%向上し、年間442時間、309万円の削減につながる──というのが、当初描いた青写真だ。稼働から約1年。7%の目標には到達していないものの、効率化にはつながっているという。
「属人化」と「有効活用できいないデータ」 2つの課題を解決
味を数値化し、AI活用するというアイデアが生まれたのは、全社で取り組んだDX勉強会の場だった。研究室として何ができるかを考えたとき、業務課題を解決する案として挙げられたのだ。このアイデアの実現に向けて、同社の工場でIHIのコンプレッサーを使用していた経緯などから、IHIと共に取り組むことになった。
もともと研究室では、試作開発におけるスキルの属人化が問題視されていた。勉強会やベテランが若手に実施する教育の取り組みなどはこれまでも実施してきたが、細かな味の出し方の理解にはどうしても時間がかかる。
また、保管している膨大なレシピを有効活用できていないことも、もう1つの課題だった。年間数千件ものレシピが追加されていくが、その検索にも困難が伴うため、せっかくのデータを活用できていなかった。
属人化の解消と、データの有効活用。この2つを同時に解決に導く手段が、AI活用だったのだ。
データの不揃いが壁に
当初は甘み、旨み、酸味、塩味、苦味の「五味」を表示できれば理想だと考えていたというが、適した分析器がないため断念。塩分やpH、粘度といった、取得可能な値を使用した。
並行して、味覚センサーのテストも実施。こちらは官能評価とも一致し、精度としては比較的問題ないが、1日に10サンプルしか分析できない。膨大なサンプルを1日10件ずつ処理していくことは、費用対効果の観点から断念した。
匂いのセンサーもテストを実施したが、現時点では適したものを見つけられなかったという。今後は性能の向上を待って、匂いのデータも取り込む意向だ。
「特徴的なお好みソースを20品ほど用意し、その原料と、『五味』に関する官能評価を学ばせれば、ゴールを設定できるのではないか」当初はそう考えていたというが、サンプル数が足りず実現はしなかった。これまで五味の全てに関する記述をしてきておらず、データの不揃いも壁になった。また、味に関する記述と容器や包装に関する記述が混在していた。現在はデータを入力する際、味に関する情報とそれ以外を分けている。
理想は「AIアラート」 さらなる活用に意欲
今後、さらなるAI活用の予定はあるのか。「構想段階に過ぎない」としつつ、開発マニュアルを読み込ませて「こういうレシピを作ったら危ない」というパターンを学習させ、アラートを作りたいという。例えば、レシピにおける醤油の配合割合が高いと、低い温度で沸騰してしまい、調理の際に問題となりやすい。こうした失敗に陥りやすいポイントをAIで検知し制御するイメージだ。
「議論を重ねて、今回のシステムの概要を作り上げはじめたのが4年前。AI活用ありきで始まった取り組みではなかったため、(IHIと)お互いのニーズやできることを理解するのに時間がかかってしまったが、この4年間でAIはより進歩している。もっとできることはあるはず」(吉田氏)
この記事を読んだ方へ 生成AI×ビジネスを見据える
元・東京大学松尾研究室のAI研究者、今井翔太氏が「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」に登壇。
生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。
- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」
- 2024年7月9日(火)〜7月28日(日)
- 無料でご視聴いただけます
- こちらから無料登録してご視聴ください
関連記事
 「ギャルのお悩み相談」も パーソルが社内GPTの“プロンプト掲示板”を作ったら、何が起きたのか
「ギャルのお悩み相談」も パーソルが社内GPTの“プロンプト掲示板”を作ったら、何が起きたのか
言葉が思い出せないときには「あれ、あれ、あれだよあの単語」。誰かに悩みを聞いてほしいときには、ギャルが明るく解決してくれる「悩みへの認知行動療法的アドバイスbyギャル」。パーソルグループの社内GPTでシェアされている、生成AIへの指示文(プロンプト)だ。プロンプトをシェアし合うことで起きた「思わぬ効果」とは? 「AI菓子職人」を全国に派遣 神戸の100年企業が起こした「お菓子作り」のDX
「AI菓子職人」を全国に派遣 神戸の100年企業が起こした「お菓子作り」のDX
神戸市の老舗菓子企業「ユーハイム」は業界でもあまり例がない、菓子の生産にAIを導入している。河本英雄社長に背景を語ってもらった。 AIドラレコで「リスク運転」が86%減った運送会社も どんな仕組み?
AIドラレコで「リスク運転」が86%減った運送会社も どんな仕組み?
タクシーやトラック、営業車など車を運転する仕事で注目されているのが、AI搭載のドライブレコーダーだ。運転レポートの作成機能などもあり、事故の予防が期待されている。「リスク運転」を減らす取り組みを紹介する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング