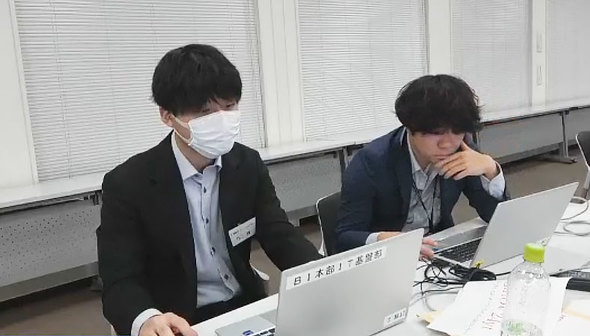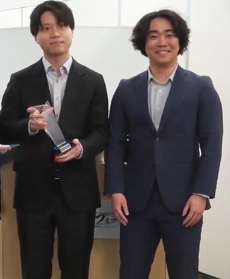「正直甘く見ていた」 NTT東日本の27歳エース社員、数十億規模のプロジェクトでの学びと成長:教えて!あの企業の20代エース社員
連載:教えて!あの企業の20代エース社員
あの企業の20代エース社員にも「新卒1年目」の頃があった。挑戦、挫折、努力、苦悩――さまざまな経験を乗り越えて、今の姿がある。企業に新たな風を吹き込み、ビジネスの未来を切り開く20代エース社員の「仕事」に迫る。
人々の生活を「通信×IT」の力で支える東日本電信電話(以下、NTT東日本)。高速通信インフラの提供にとどまらず、企業のDX支援や自治体向けのITソリューションにも注力し、社会のデジタル変革を推進している。
竹口嶺さん(IT基盤ソリューション部 第一基盤SEグループ 第二担当)は、同社のITが業界や分野を横断し、新たな価値を生み出す可能性に引かれ、2021年に新卒入社した。文系出身で、就職活動中は営業職を志望していた彼が、配属を希望したのはSE職。「技術を扱う企業だからこそ、職種に関係なく技術を理解する必要がある」と考えたからだ。
未経験からの挑戦だったが、現場での学びを重ね、2年目には数十億規模のプロジェクトにアサインされたり、4年目には社内技術コンペで優勝したりと頭角を現す。文系出身ながら技術の実力を証明し、周囲にも影響を与える存在になった。
なぜ、ここまで挑戦を続けられたのか。竹口さんの成長の原動力を探っていこう。
営業志望からSEへ 自ら選択したキャリアだが、精神的な負担も
竹口さんは学部時代に経済学を専攻し、就職活動の初期は金融業界を志望していた。しかし、ある金融系企業のインターンでフィンテックに触れたことで、ITが業界や分野を横断し、新たな価値を生み出す可能性に魅力を感じるように。それをきかっけに、後半はITのアセットや技術を強みに持つ企業へと志望をシフトした。
「サポーターとして人々を支えられる仕事」と「汎用性の高いスキルを身に付けられる環境」を軸に企業を検討する中、広大な営業ネットワークと多様なアセットを持つ点で魅力を感じたのがNTT東日本だった。
就活時代は営業職を志望していた竹口さんだったが、配属先はSE部門。この配属は、入社直前の配属面談で竹口さんが「SEをやりたい」と人事担当者に伝えたことがきっかけだった。
当時のNTT東日本では、事務系と技術系で採用が分かれており、文系出身者は基本的に事務系採用、そのうち大半が営業職配属だった。竹口さん自身も就職活動の段階では営業職を志望し、NTT東日本のセールス向けインターンにも参加していた。
「営業職で働くとしても、技術を身に付けなければ、お客さまとの対話が難しいのではないかと考えるようになりました。どうせゼロから技術を学ぶなら、新卒のうちに直に触れられる環境へ飛び込んだ方がいいなと思ったんです」と当時を振り返る。
これまでも同社では文系出身者がSEに配属されるケースはあったが、今回のように本人の強い希望で配属されることは珍しく、配属面談を担当した人事も驚いていたという。
とはいえ、竹口さんの要望は意外にもすんなりと受け入れられた。その背景には、営業職をはじめとする事務系業務でも技術スキルの重要性が高まり、その流れが年々加速していたことが関係する。特に竹口さんが入社するころは、ちょうどその変化が本格化し始めた時期だった。
配属先ではSIer部隊に所属し、プロジェクトマネジメントを中心に、小規模な顧客向けの受託事業を担当。チームは12〜15人体制で、6人の同期が配属されていた。メンバーは案件ごとにアサインされ、プロジェクトの期間は2、3カ月から半年と、案件によって異なる。
竹口さんの初年度の担当案件は年間で約10件。業務用ルーターの更改などネットワーク案件を中心に取り組み、1年間かけて少しずつ経験を積み重ねていった。しかし、当初は「ベンダーに業務を丸投げするのが精いっぱいでした」と竹口さんは振り返る。
「案件を収めることが主な役割となり、『プロジェクトを管理しているだけになっていないか?』という不安を感じていました。ベンダーに丸投げした案件の進捗に気を配ることしかできず、精神的な負担も大きかったです」
最初はできることが限られていたものの、業務をこなすうちに意思決定の機会が増え、少しずつ仕事への自信がついてきた。
トラブル案件を乗り越え、成長の本質に気付いた2年目
2年目に入り、竹口さんは数十億円規模の自治体向けプロジェクトにアサインされた。このプロジェクトはもともと他チームで進められていたが、メンバーの欠員や計画の遅れにより、部署全体での補強が急務となっていたのだ。チームは異なるが、若手育成の機会に活用しようという部署の方針で、竹口さんも参加することに。
「今思えば、プロジェクトに参加できたのはラッキーだったと思います。でも、当時は『ひどい目にあったな』と思いました」と、苦笑しながら振り返る。
同プロジェクトでは、サーバークラウド構築チームのサブリーダーを担当。チームは約40人で構成され、その約8割がベンダーやコンサルからの派遣社員だった。
運用保守のサブリーダーは理系院卒の同期が務めており、業務情報を共有する際にはOSに関する専門的な話が出ることも多かった。しかし、知識が追い付かず、知ったかぶりをしてしまった自身に、プレーヤーとしての未熟さを痛感したという。
「同期は業務上必要な情報を共有してくれているだけなのに、何も知らない自分に劣等感を覚えました」
また、ベンダーやコンサルからのメンバーの方が経験は豊富だったものの、意思決定はNTT東日本の社員の仕事だった。本来であれば主体的に課題へ対応すべきだったが、当時の竹口さんはリーダーに伝え、それを協力会社や派遣社員に共有するので精一杯だったという。
「1年目で少しずつ自信を持ち始めていましたが、この環境に入ってみると想像していたものとは全く違いました。正直、甘く見ていたと痛感しました」
休日には案件について勉強しながら知識を深めようとしたものの、新しい情報が次々と入るため、最初の1〜2カ月はキャッチアップに苦戦。しかし、あるトラブル対応をきっかけに、エンジニアも技術の全てを理解しているわけではないことに気付き、そこから何を自分で理解し、何をメーカーなどの協力会社に聞くべきかを切り分ける重要性を学んだ。
技術の体系的な理解が深まるにつれ、「この部分はメーカーさんに聞くべきだ」と判断できるようになったという。すると、大枠を押さえていればエンジニアとも円滑に会話できることが分かり、考え方も変わり出した。
それまでは「全てを勉強し、理解しないといけない」という漠然とした不安があったが、どこまでを自分で理解し、どこから先をメーカーに委ねるべきかの線引きができるようになった。この営みこそが「実務で技術を学ぶ」ことであり、その繰り返しは達成感と成長に直結する。そう気付いてからは、プロジェクトに楽しさを見いだせるようになったという。
こうした学びもあり、プロジェクトの終盤には主体的な行動が取れるようになる。要件定義の再設定を担当した際には、メーカーや関係者を適切に巻き込みながら、本業務と並行して約1カ月かけて1人で設計書に落とし込むことに成功。また、年度末対応時には、運用保守チームへの問い合わせ対応に加え、チーム全体の意思決定もできるようになっていた。
「メーカーさんと最大限に連携できれば、案件の進め方や考え方次第で大きな効果を生み出せると実感しました。1年目はベンダーに丸投げしていましたが、マネジメントを経験する中で、プロパーとしての意思決定の重要性をあらためて認識しました。自分がプロジェクトを担うとしたら、どう進めるべきかを考える2年目でした」
技術コンペ優勝の4年目、次なる挑戦へ
自治体のプロジェクトも一段落し、元のチームに戻った3年目。年間30件以上の案件をこなす中で、複数の案件を効率的に回すことを意識し始めた。この頃から後輩とチームを組む機会も増え、自分が得意な業務を後輩に引き継ぎ、自身は新たな挑戦をすることで、プレイングマネジャーの役割も担う。
4年目には、部署の推薦を受け、社内技術コンペに参加することに。この大会は毎年、各事業部から選ばれたメンバーが120分の制限時間内でネットワーク・サーバー・クラウドの3領域におけるトラブルシューティングの実務スキルを競い合う。社内でも注目度が高く、全社に向けて中継される大会だ。
例年、ベテランと若手が混ざって参加する形式だったが、2024年度からは5年目までの社員を対象とした若手部門が新設され、別大会として開催されることになった。今年度の若手部門には、竹口さんらが所属する本社からは3チーム、神奈川や千葉の6事業部からそれぞれ1チームずつ出場し、合計9チームが競い合った。
2人1組で参加するこの大会で、今回パートナーとなったのは、ネットワークとインフラ設計が得意な後輩。彼も文系出身で、技術を学びたいという思いからSEの道を選んだ。せっかく挑戦するなら目標を持ち、前向きに取り組みたい。その思いで、上位入賞を目指して努力を重ねた。
約2カ月の準備期間中は、過去問の共有や検証環境の提供といった部署からのサポートを受けつつ、自身も業務効率化を進めることで、勉強時間を捻出。しかし、業務と並行しての勉強は相当な負担があったという。周囲からは案件を減らすことも打診されたが、「その分の業務負担が後輩にかかっては意味がない。仕事と両立してこそ価値がある」と断っていた。
技術コンペ当日、竹口さんのチームは全5問のうち4問を正解し、優勝。どの問題も高いプレーヤースキルが求められ、チームによっては1問しか解けないこともあったという。なぜ、ここまでコンペに力を入れていたのか。竹口さんは、「技術の楽しさを伝えるには、自分の姿勢を見せるしかない。その1つの材料としてコンペは活用できると思った」と語る。
「文系出身でも優勝できるんだ、かっこいいなと思ってもらえれば、その影響が周囲にも広がるはずです。4年目になり、同期が退職を選ぶのを見て、このままでは組織が続かないと感じました。組織力の根幹は、やはり技術力。その技術は自分で学ぶしかない。しかし当然、皆がモチベーションが高いわけではないです。誰だって仕事が終われば休みたいし、休日は遊びたい。それでも頑張ってみようかなという自主性を持てるように、自分の活躍が少しでも皆の刺激になればと思ったんです」
コンペでの優勝は部署内にとどまらず、他部署や営業にも影響を与えた。初対面の他部署の後輩や営業から声をかけられる機会が増え、「自分も勉強しようと思った」と言われることもあったという。竹口さんは「誰かの良い刺激になれたのなら嬉しいですね」と笑顔を見せた。
現在は、社内のダブルワーク制度を利用し、採用にも関わっている。さまざまな学生と出会う中で、NTT東日本の可能性や未来に期待して入社を決めた彼らの思いに応えたいという気持ちが強くなったという。
「NTT東日本を選ぶ学生は、総じて社会課題解決への強い情熱を持っています。そしてこの会社ならそれが果たせると信じて入社する。その期待を裏切らない働きをすることが、自分自身のさらなる成長につながると感じています。そう考えるようになってから、仕事がより楽しくなりました」と竹口さんは語る。
将来的には、後輩をサポートする姿を会社に認められ、新卒採用や育成支援の場でも声をかけてもらえるようになれたらと考えているという。
「4年目で同期や先輩が皆異動し、1人残った同期も新たな目標のために昨年転職しました。今は19人の後輩がいるチームで、実務における最年長として奮闘しています。ただ、無理に『後輩指導』という型にはまるのではなく、あくまで実案件を通して成長を促せる存在にこだわっています。プレーヤーとしても、プロジェクトマネジャーとしても稼働しつつ、自然と周囲から相談や依頼が来るくらいがちょうどいいと思っています」
一方、会社に対しては「Sler市場における当社の価値やそのマーケティングといった、もう一段上の視座が弱いのではないか」と指摘する。着実に現場での経験を重ねてきたからこそ、会社に対する危機感や課題が見えている竹口さん。今後もプレーヤーとして実績を重ねつつ、「会社をより良くするためには?」という視点から、行動を積み重ねていく。
関連記事
 LINEヤフー動画事業の27歳エース社員 「アプリDL数」前年同期比3倍を実現、その手腕は?
LINEヤフー動画事業の27歳エース社員 「アプリDL数」前年同期比3倍を実現、その手腕は?
新卒から5年間、LINEヤフーの動画事業で奔走してきた27歳エース社員がいる。現在はLINE VOOMに携わっているが、新卒配属されたGYAO!では、新規アプリDL数を前年同期比で3倍にした。エース社員の手腕を取材した。 新卒2年目でMVP 楽天エース社員の「売上、営業とのコネも少なかった」中での奮闘記
新卒2年目でMVP 楽天エース社員の「売上、営業とのコネも少なかった」中での奮闘記
楽天グループが提供するポイ活サービス「スーパーポイントスクリーン」の部署に初めて兼村さんが新卒としてが配属された。売り上げも営業とのコネクションも少ない中で、新しい広告ソリューションを考案し、新卒2年目でMVPを獲得する。楽天エース社員の奮闘記。 日立の29歳エース社員が考える「製造業の未来」 タイ赴任で見えた、自身の役割とは
日立の29歳エース社員が考える「製造業の未来」 タイ赴任で見えた、自身の役割とは
日立製作所のエース社員が、アジア各国の製造拠点が集まるタイに赴任。そこで感じた日本の製造業の未来とは──。 富士通の27歳エース社員、1年目で花形部署に異例のヘッドハント 信条は「3カ月で成果出す」
富士通の27歳エース社員、1年目で花形部署に異例のヘッドハント 信条は「3カ月で成果出す」
新卒1年目で富士通のグループ会社に入社した寺島さん。まさかの1カ月で異動希望を提出し、現在は本社の花形部署で働く。新卒4年目の現在までにどのような経験を積んできたのか、取材した。 「裸の王様だった」 サイバーエージェント新卒社長は挫折から何を学んだのか
「裸の王様だった」 サイバーエージェント新卒社長は挫折から何を学んだのか
新卒1年目に「社長」の役割を任せる企業がある。サイバーエージェントだ。新卒で子会社の社長となった若手は、当時を「裸の王様だった」と振り返ったが、何を学んだのか。同社の「任せる文化」に迫る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング