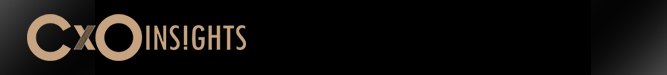「雪塩さんど」大ヒットの舞台裏 調味料から菓子事業にかじを切った、その理由とは?:地域経済の底力(2/5 ページ)
海外からの観光客には通用しなかった……
実は、雪塩さんどが誕生した背景にあったのは、こうした既存ビジネスの行き詰まり感だった。西里社長は、「時代の変化とともに、自宅で料理する人が減りました。また、塩の専門店というのは、塩の魅力を言語化してお客さまに伝え、興味を持ってもらうというプロセスが必要なため、日本人による、日本人のための、日本のサービスだったのです」と、当時の状況を振り返る。
日本における塩のマーケット縮小に加えて、海外からの観光客の増加が新たな課題として浮かび上がってきた。
「せっかく塩の楽しさ、おもしろさを言語化して体系化していったのに、言葉が通じない、食文化が違う、そもそも興味を持ってないというお客さんが増えていきました」
試行錯誤の末、西里社長が行き着いた答えが、「言葉がいらない商品・サービス」開発の必要性だった。
「お菓子なら万国共通で、おいしければ売れる。キャッチーなパッケージで販売し、味が本当に納得いくものだったらいけるはず」
こうして同社は、菓子メーカーとしての新たな一面を強化する方向へとかじを切ったのである。
もともと菓子も製造・販売していたものの、主力はあくまでも調味料としての雪塩だった。その中で、菓子事業をブラッシュアップし、その目玉として開発したのが、雪塩さんどだった。
“理想の味”に向かって組み立てる
では、雪塩サンドはどのような着想から生まれたのだろうか。
サンドというアイデア自体は、以前から菓子事業で協業していた寿製菓(鳥取県米子市)からの提案だった。しかし、味に関しては、西里社長のこだわりが強く反映された。
「私たちが作る菓子には“理想の味”があります。ボリュームがあり、濃厚かつリッチな味わいを持たせつつも、後味はすっきりと切れのいい感じに。一般的にリッチな味というのはすごく余韻が残るのですが、それを塩で切るイメージです」
そうした理想型があり、そこから逆算して味を組み立てていったという。
「『売れるためには、こういう味でなければならない』というイメージが、私たちにはある。その味に近くなると、売れるんです」と力を込める。
雪塩さんどの開発には半年以上の歳月をかけ、毎週のように試食。具材を入れてみたり、食感を変えてみたり、味を変えてみたりと、工夫を重ねた。
最終的なジャッジをするのは、西里社長自身だった。
「ゴーサインを出すには、当然食べないとダメ。セブン−イレブンの鈴木(敏文元会長兼CEO)さんの話ではないですが、やはり食べなければ分からない。最終判断は、他人に任せてはいけないと思っています」
この哲学と徹底が、雪塩さんどをはじめとする同社のヒット商品を支えている。
関連記事
 雪塩さんどは「一本足打法」で終わらない――ヒットを生み出し続ける秘密とは?
雪塩さんどは「一本足打法」で終わらない――ヒットを生み出し続ける秘密とは?
大ヒットとなった「雪塩さんど」。ただ、宮古島の雪塩社が危険視するのは「一本足打法」になることだ。ヒットを生み出し続けるためには、どのような考え方が必要なのか。インタビュー後編。 書類でよく見る「シヤチハタ不可」、シヤチハタ社長に「実際どう思ってますか?」と聞いたら意外すぎる答えが返ってきた
書類でよく見る「シヤチハタ不可」、シヤチハタ社長に「実際どう思ってますか?」と聞いたら意外すぎる答えが返ってきた
ハンコで国内トップメーカーのシヤチハタが、2025年に創業100周年を迎える。気になっていた質問をぶつけてみた。インタビュー後編。 部下に「仕事は終わってないですが定時なので帰ります」と言われたら、どう答える?
部下に「仕事は終わってないですが定時なので帰ります」と言われたら、どう答える?
企業にとって残業しない・させない文化の定着は不可欠だ。しかし――。 ナイキ「オワコン化」の足音 株価急落、新興シューズメーカーが影
ナイキ「オワコン化」の足音 株価急落、新興シューズメーカーが影
ナイキの不調には複数の要因が絡んでいるようだ。 部下が相談する気をなくす、上司の無神経な「たった一言」
部下が相談する気をなくす、上司の無神経な「たった一言」
部下が報連相しようとしたときの上司の何気ない「ある一言」が、部下の心を萎縮させているのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング