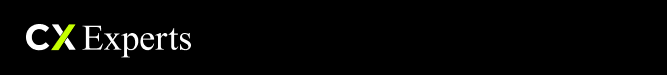『ゴジラ-1.0』山崎貴監督に聞く、「前作超えヒット」を生み出す秘訣 日本映画界の課題(1/2 ページ)
世界で150億円以上の興行収入となった2023年の映画『ゴジラ-1.0』。米国の第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞し、世界からも高い評価を受けた。2025年3月には、デジタルメディア協会が主催する第30回AMDアワードで「大賞/総務大臣賞」を受賞した。
『ゴジラ-1.0』は「ゴジラ」シリーズ前作の庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』(2016年)に続いて、日本映画でフルCGのゴジラを描いた点が特徴だ。『シン・ゴジラ』が国内82.5億円のヒットとなり、後継作を制作するにあたり、『ゴジラ-1.0』の山崎貴監督は、『シン・ゴジラ』との徹底的な差別化を図ったという。
いったいどのような戦略で作品を作り込み、『ゴジラ-1.0』を世界的な成功に導いたのか。山崎監督に聞いた。
 山崎貴(やまざき・たかし)昭和39年、長野県松本市生まれ。松本県ケ丘(あがたがおか)高校を卒業後、阿佐ヶ谷美術専門学校で学ぶ。平成12年映画『ジュブナイル』で監督デビュー。CGなどを駆使した映像表現・VFXの第一人者。平成17年『ALWAYS三丁目の夕日』で第29回日本アカデミー賞最優秀作品賞・監督賞など12部門を受賞。他作品に『永遠の0』『STAND BY MEドラえもん』など
山崎貴(やまざき・たかし)昭和39年、長野県松本市生まれ。松本県ケ丘(あがたがおか)高校を卒業後、阿佐ヶ谷美術専門学校で学ぶ。平成12年映画『ジュブナイル』で監督デビュー。CGなどを駆使した映像表現・VFXの第一人者。平成17年『ALWAYS三丁目の夕日』で第29回日本アカデミー賞最優秀作品賞・監督賞など12部門を受賞。他作品に『永遠の0』『STAND BY MEドラえもん』など前作・庵野秀明『シン・ゴジラ』へのプレッシャー 「ペンペン草も生えない」
――山崎監督はCGテクノロジーと映画の歴史を築いてきました。『ゴジラ-1.0』は第96回アカデミー賞で視覚効果賞にも輝きました。本作は自身のキャリアの中でどのような位置づけになるのでしょうか。
「ゴジラ」シリーズ前作、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』(2016年)に対抗しなければならない意識がものすごく強くありました。それはもう、恐怖に近い感覚でした。『シン・ゴジラ』は自分自身も心から認めている作品ですし、世間的にも非常に高い評価を受けています。
もし自分が好きじゃない作品だったら「世の中はゴジラが好きなんだな」と割り切れるのですが、自分も大好きな作品だったので、その後に何かを作るとなると、まるでペンペン草も生えないような状況なんです。あれだけ良いものができてしまうと、誰も次をやりたがらないんじゃないかとすら思いました。
実際、私はずっとゴジラをやりたいと思ってきましたが、技術的な面、例えばマシンのスピードなどの問題で、自分がやりたいゴジラを実現するのは難しいと感じていた時期もありました。そんな中で『シン・ゴジラ』が出てきてしまったので、正直なところ「大変迷惑だな」と思ったこともありました。
――『シン・ゴジラ』による“焼け野原”の中で、山崎監督が手を挙げた形となりました。
今回のゴジラの話をいただいた時に、「このままいくとゴジラの火が消えてしまうんじゃないか」という危機感がありました。実際、7年間も新作が作られていなかったのです。それはやはり、みんな『シン・ゴジラ』の後に作るのが怖かったからだと思います。
あまりにも出来が良すぎたけれど、誰かが挑戦しないといけない。そんな気持ちも少しありました。自分が貧乏くじを引きに行くような感覚もありましたが、それでも「やれることは全部やろう」と決意して臨みました。
『シン・ゴジラ』への恐怖心が、逆に今回の作品にとっては大きなプラスになったと思います。今までも一生懸命やってきましたが、今回は本当に相当な覚悟と努力で臨みましたし、その結果がこうして評価されたことは本当にうれしいです。
『シン・ゴジラ』との徹底的な差別化戦略
――山崎監督は2021年に西武園のアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド」も手掛けました。その経験は本作にどう生きましたか。
ゴジラのコンテンツを作ってみて、あらためて感じたのは、「ゴジラとの距離の近さ」に対する恐怖です。緻密に作られた怪獣というのは、どれだけ寄ってもディテールがしっかりしているので、本物に見えてしまうんです。視聴者の中の潜在意識が「これだけ細かいディテールがあるなら本物なんじゃないか」と錯覚するわけですね。
その点、デジタル技術のメリットは、細かい部分のディテールまで徹底的に追求できる点が大きいです。着ぐるみでは成し得なかった、ゴジラにかなり接近した絵を撮っても成立する点は、まさにデジタルならではの強みだと感じています。
西武園の「ゴジラ・ザ・ライド」を作った時も、「こういうアプローチならいけるかもしれない」と手応えを感じました。『シン・ゴジラ』を超えることは難しいかもしれませんが、少なくとも並ぶものが作れるんじゃないかという感触がありました。今回の『ゴジラ-1.0』も、その経験や自信が大きく生きていると思います。
――『シン・ゴジラ』と、どこを差別化したのでしょうか。
私は『シン・ゴジラ』のとにかく裏を狙うことを意識しました。『シン・ゴジラ』は、キャラクターたちの人間ドラマをあえてカットすることで、クールでドライな雰囲気が非常に高く評価された作品です。だからこそ、私は逆に、人間ドラマたっぷりの超エモーショナルな作品に仕上げようと決めました。
また、『シン・ゴジラ』は主に陸での騒動を描いていたので、私は海を舞台にしようと考えました。さらに、『シン・ゴジラ』が現代の物語であるのに対し、私は第二次大戦直後という特殊な時代設定にすることで、徹底的に差別化を図りました。
とにかく『シン・ゴジラ』の裏を突き詰めていくことで、なんとか違いを出そうとしたんです。自分がこれまでの作品で得意としてきたジャンルや土俵。例えば『ALWAYS 三丁目の夕日』で描いた昭和の時代や、『永遠の0』『アルキメデスの大戦』などで扱った戦争の時代。そういった自分が勝負できる材料のある世界観に、ゴジラを引っ張り込むという作戦をとりました。そうすれば、それなりに戦えるのではないかと考えたんです。
――非常に緻密な狙いがありますね。
そうなんです。『ゴジラ-1.0』はある意味、戦略商品なんですよね。『シン・ゴジラ』と戦うための。
若手とベテランの融合が生み出した『ゴジラ-1.0』
――マーケティングの観点から見ても、とても興味深いお話です。制作の裏に、若手クリエイターの活躍もあったようですが、具体的にどういった点が印象的でしたか。
デジタルネイティブの若いスタッフたちは、僕らの世代が想像もできないような大量の情報を平然と扱えるんです。私たちはどうしても、マシンパワーが遅かった時代の癖が抜けていません。例えば水のワンシーンだけで1テラバイトを超えるデータ量になると「もう1テラいっちゃったよ」と驚いてしまう。でも、若い子たちにとっては「テラ」なんて当たり前で、そこからがスタートなんです。何日間もかけてレンダリングすることにも全く動じないし、「いいものを作るにはそのくらいかかるでしょう」という感覚でやってくれるのが本当にありがたかったですね。
ただ、そういう若手だけで作ると、今度は映画が完成しなくなってしまう。そこで昔からやっているベテランスタッフには各シーン数百ギガくらいのデータでしっかり作ってもらい、ここぞという場面では、ちょっと頭のおかしいくらい突き抜けた若手にスーパーショットを作ってもらう。そうやってバランスを取りながら制作を進めました。絶対にスーパーショットは必要ですし、でも映画として完成させることも大事。そのバランスの中で、なんとか作品を作り上げました。
関連記事
 Netflixが世界で進める“独自作品”戦略 プロデューサーに聞く日本の実写ドラマ制作力とは
Netflixが世界で進める“独自作品”戦略 プロデューサーに聞く日本の実写ドラマ制作力とは
前編に引き続き、Netflixで『地面師たち』を担当した髙橋信一プロデューサーに、日本の実写ドラマ制作の実力を聞いた。 Netflix『地面師たち』プロデューサーに聞く 「次が気になって仕方ない」の作り方
Netflix『地面師たち』プロデューサーに聞く 「次が気になって仕方ない」の作り方
Netflixで『地面師たち』を担当した髙橋信一プロデューサーに、社会現象の舞台裏を聞いた。 AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
米国のテック系人気ユーチューバーの何人かが、こぞって「AI開発競争はGoogleが勝利した」という見出しの動画をアップしている。これでGoogleの勝利が決定したのかどうか分からないが、少なくともOpenAIの首位独走の時代は終わったのかもしれない。 『スマブラ』『カービィ』生みの親に聞く ヒット作を生み出し続けるマネジメント
『スマブラ』『カービィ』生みの親に聞く ヒット作を生み出し続けるマネジメント
『星のカービィ』『大乱闘スマッシュブラザーズ(スマブラ)』の「生みの親」、ゲームクリエイターの桜井政博さんに、ゲーム作りにおけるノウハウや、ヒット作を生み出し続けるマネジメントについて聞いた。 ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意
ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意
ソニーグループを再生させた平井一夫元社長兼CEOが自ら実践し、体験を通じて会得したビジネスリーダーに必要な要件とは? 「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
NECが、オープンイノベーションに本腰を入れている。NEC Open Innovation Nightには富士通の社員も登壇。同社の取り組みの真意に迫る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング