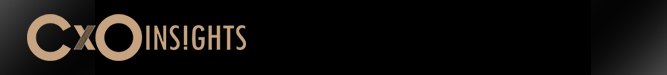日本発のブランドを“世界に売る”AIベンチャー 社長に聞く「海外展開の秘訣」
米スタンフォード大学が、寿司(すし)を媒介にしたハッカソン(アプリ開発コンテスト)を2024年から主催している。名前はそのまま「Sushi Hackathon」で、2回目となる2025年は、約600チームが応募し14チームが最終審査でプレゼンした。
最終審査に残った参加者全員に日本の本格寿司を提供し、食文化理解を深める狙いがある。2回目は東京・銀座の「鮨あらい」の板前が訪米し、寿司を会場現地で振る舞った。
Sushi Hackathonを共催し、書類審査や審査委員長を務めたのが東京・渋谷に本社を置くGDXだ。同社は生成AIによるDX支援の他、主にECサイトの海外展開における支援業務も手掛けており、日本発のさまざまなブランドを海外展開させた実績を持つ。
寿司を通じたハッカソンを共催した狙いは何か。日本企業が海外展開する上で何が重要なのか。GDXの洞田(ほらた)潤社長に聞いた。
 洞田潤(ほらた・じゅん)GDX代表取締役CEO。1981年生まれ。早稲田大学卒業後、三井住友銀行で法人営業など幅広い業務に従事。2013年にGDX(旧・五反田電子商事)に参画し、翌年より代表取締役CEOとして経営全般を統括。Eコマース事業の拡大と海外展開を推進し、現在はグローバル市場で次世代コマースの価値創出に取り組んでいる
洞田潤(ほらた・じゅん)GDX代表取締役CEO。1981年生まれ。早稲田大学卒業後、三井住友銀行で法人営業など幅広い業務に従事。2013年にGDX(旧・五反田電子商事)に参画し、翌年より代表取締役CEOとして経営全般を統括。Eコマース事業の拡大と海外展開を推進し、現在はグローバル市場で次世代コマースの価値創出に取り組んでいる「寿司」でつながる人材ネットワーク ハッカソンが生む出会いの場
――Sushi Hackathonでは学生なども多く参加しています。人材獲得といった実務的な面での狙いはあるのですか。
Sushi Hackathonの狙いのまず一つは、優秀な人材との出会いです。それに加えて、米国には副業文化があります。そこに大きな可能性があります。例えば、来年から私たちは「寿司トラック」を走らせる計画があります。各大学を回って、コンピューターサイエンス専攻の学生たちに、おいしい寿司を無料で提供するものです。
最終的には、私たちのラボの中に寿司カウンターを併設し、エンジニアがいつでも食べに来られるようにしたいと考えています。そしてそこには学生だけでなく、Googleなどビッグテックのエンジニアも夜に来て、寿司を食べながら交流できるようにするんです。そこから、副業として日本企業のAIプロジェクトに関わってもらう。そんな仕組みを作りたいと思っています。つまり、世界の最前線の研究者やエンジニアたちと日本企業が自然につながる環境を「寿司」を媒介に作るんです。
――発想がシンプルでありながら、とても本質的ですね。
そうなんですよ。実はGoogleのカフェでも寿司を提供しているんですが、あれがそこまでおいしくないんですよ(笑)。あるとき、Googleの関係者と一緒に食べていて「これ、もう少しおいしかったらもっと人が集まるよね」という話になって。それなら、うちでやろうじゃないかというノリから始まったアイデアなんです。
――日本では、エンジニアの副業は利益相反の観点から、同業他社では高い制約がある場合が多いです。米国での副業人材は、こうした制約は日本に比べると緩いのでしょうか。
そこは正直言って未知数ですね。ただ、実際にスタンフォードの学生がインターンとして入って、手を動かしながらアイデアや情報を提供してくれるような、緩やかな関係性から深めていける可能性はあると思っています。ビッグテックの中でも本当にAIど真ん中の企業はさすがに厳しいですが、それ以外の部署や分野の人なら、アイデアベースの協力は十分できるのではないかと考えています。
例えばGoogle内でも、AI部門では制約があっても、VR部門の人と話して、魚の締め方をバーチャルグラス上で再現できないかといった議論はできたりするんです。そういう柔軟な関係性から始めれば、協業の余地は十分あると思っています。
日本発ブランドをAIで世界へ 次の挑戦は米国市場
――中学や高校時代はどんな活動をしていましたか。ITとの出会いについても教えてください。
ずっと柔道をしていましたが、家庭は全員アーティストでした。母が書道家、父と兄は彫刻家で、家中に裸婦像の石彫が置いてあるような環境でした。中学2年生くらいの頃にMacintoshを買ってもらい、PCをいじりながら柔道漬けの日々を送っていました。ITとフィジカル、その両方にエネルギーを注いでいましたね。
――大学時代の生活はどんな様子だったのですか。
早稲田大学には(東京)東伏見の柔道部寮があったのですが、そこに入ると柔道漬けの日々になるのは分かっていたので、あえて入りませんでした。高田馬場で下宿して自分なりの学生生活を送りました。それでも重量級でインカレに出場するなど柔道でも活動しつつ、夜は夜で東京の学生生活を満喫していました。何事も全力で楽しみたいタイプなんです。
――上場も目前とのことですが、今後の課題や展望について教えてください。
これからのグローバル展開には優秀な人材が不可欠です。特に米国で本格的にビジネスを拡大していくためには、現地で人材の確保と経営基盤の強化を進めていかなければなりません。そのためにも、いずれは米国市場での上場を目指しています。
現在は日本で上場審査中でして、おそらく来年には上場できる見込みですが、その先にあるのはナスダック上場です。日本発の技術やブランドを基盤にしながら、AIを活用してグローバルビジネスを推進していく。それが今の大きな目標です。
――具体的にどのようにグローバルビジネスを展開していきたいですか。
具体的には、ファッションブランドやコスメ、さらには魚の締め方や流通といった日本特有の技術や職人文化を、世界に発信していくようなビジネスを構想しています。日本企業が持つ高品質なプロダクトを、AIとデジタルによって新しい形で世界へ届けたいと考えています。
食育すればAIが育つ 感性がテクノロジーを進化させる
――Sushi Hackathonに代表されるように、洞田社長の食へのこだわりの原点とは何なのでしょうか。
これはもうシンプルに、両親の影響ですね。両親ともに芸術家で、幼い頃から年に4回ほど海外旅行に連れて行ってもらい、美術館を巡りながら必ずその土地のおいしいものを食べていました。例えば「今度はギリシャで遺跡を見よう、ついでに屋台も味わおう」といった具合に、旅と食がセットになっていたんです。
パリでルーブル美術館を見たら、そのあと街角でフレンチを楽しむ。そんな経験の繰り返しでした。これが私の「食育」でしたね。芸術と食を同じ文脈で学ぶような家庭でした。
――それが今、AIやビジネスに還元しているわけですね。
まさにそうです。私は「食育すればAIが育つ」と思っています。本当に、感性を育む教育が後々テクノロジーや創造性に生きてくる。親の投資がいま、大きなリターンになって返ってきていると感じます。
――美術にも関心が強かったそうですが、そちらの道には進まなかったのですか。
書道では全国大会に出場したこともありますが、最終的には新卒で三井住友銀行に入行し、ビジネスの世界を選びました。とはいえ、アート的な思考はずっと自分の中にあります。やはり右脳的な感性と左脳的な論理の両立が、良いソリューションを生み出すためには欠かせません。例えば日立製作所が買収した米GlobalLogicのように、エンジニアにビジネスモデルの理解を促す会社も増えています。私もそのバランスが非常に大切だと感じています。
銀行で得た人脈が20年後の事業協力に直結
――生まれ育ったアート的な素養が、経営や発想の核になっているわけですね。
そうですね。銀行時代に培ったロジカルな思考と、子どもの頃から身につけたアート的感性、その両方がある。どちらが欠けても今の自分は作れなかったと思います。システムを作るにも、AIを設計するにも、最後は「美意識」なんです。
――芸術一家から銀行に進むのは面白いですね。やはり将来の起業や財務の理解を見据えての選択だったのでしょうか。
そうですね。銀行時代に築いた人脈は、今でも大きな財産になっています。当時の取引先だった顧客が、今でも応援してくれているんです。数字や経営の仕組みを理解する上で、PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)を実際の企業活動と照らし合わせて体感できたのは大きかったです。それに加えて、銀行の仕事を通じて人脈を広げられたのも非常に大きかったですね。
今回のSushi Hackathonも、スポンサーに三井住友銀行が入っています。現地で米国展開を担当している方も、実は私を銀行時代に採用した方で、もう20年以上の縁が続いているんです。ニューヨークで偶然再会して、「面白そうだから協力しよう」と言っていただけたのも、その長い関係があったからこそだと思います。
「売る力」で日本を変える Sushi Hackathonに込めた挑戦
――Sushi Hackathonの狙いの一つとして、やはり「日本を世界へ」という思いがあるのでしょうか。
本当にそう思っています。日本には素晴らしいプロダクトやブランドがたくさんあります。でも、「売るのが上手でない」んです。ほとんどの企業はいい商品や技術を持っていながらも海外で広がらない。例えば当社が支援しているしまむらさんも、あれだけ品質も価格競争力もあるのに、海外ではまだ大きな展開ができていないのが現状です。台湾には20年以上前に出店しましたが、中国で一度失敗してから止まってしまいました。
そういう事例を見ていて思うのは、日本企業がもっと世界で評価されるべきだということです。いいものを持っていても、それを伝える力が弱い。だからこそ、われわれがAIやハッカソンのようなプラットフォームを通じて世界に出していくことに意味があると思っています。
――日本にはアニメや漫画など、世界に誇れるコンテンツが多くあります。こうした中で、なぜ「寿司」というコンテンツを選んだのでしょうか。
それは「寿司のある場所は親日的」という法則があるんです。面白いことに、寿司店がある地域には日本企業が成功している傾向があります。逆に、寿司文化が根付いていない地域では日本ブランドが苦戦するケースが多い。これは単なる偶然ではなく、ひとつの相関があるのではないかと考えています。
実際、その話を以前メンタリストのDaiGoさんともしていたんですが、「寿司がおいしい街には、良い日本企業が多い」というのはかなりの確率で当てはまるんです。だから寿司を象徴として、日本ブランドが展開しやすい拠点を世界中に広げるというのは理にかなっていると考えています。しかも、寿司は世界で最も求められている日本文化の一つです。個人的にも寿司が大好きで、もし寿司で世界をつなげられたら、それほど面白いことはありません。
関連記事
 銀座の寿司をシリコンバレーへ ECサイト支援企業がスタンフォード大とハッカソンを共催したワケ
銀座の寿司をシリコンバレーへ ECサイト支援企業がスタンフォード大とハッカソンを共催したワケ
スタンフォード大学が、日本のECサイト支援企業GDXと「Sushi Hackathon」を共催した。優勝賞金は3万米ドル、最終審査進出者には東京・銀座の「鮨 あらい」の寿司を会場で振る舞った。狙いを共催企業GDXの洞田(ほらた)潤社長に聞いた。 富士通がNVIDIAと提携 時田社長、フアンCEOが語った理由は?
富士通がNVIDIAと提携 時田社長、フアンCEOが語った理由は?
富士通は、米半導体大手の米NVIDIAと協業し、企業の主体性を保ちながらAI活用による競争力強化を支える産業向けフルスタックAIインフラの構築を進める。 NVIDIAフアンCEO大いに語る CESで明らかにしたこととは?
NVIDIAフアンCEO大いに語る CESで明らかにしたこととは?
米ラスベガスで開催中のCES 2025で1月7日(日本時間)、米半導体大手NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが基調講演をした。世界第2位の企業として事業拡大の可能性を強調した。 「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?
「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは都内で主催した自社イベントで「日本はこれまでテクノロジーの分野で遅れていたが、AIを活用すればリセットできる」と話した。「日本なくしてNVIDIAはなかった」と語る真意は? NVIDIAフアンCEOが「1on1」をしない理由 “階層なき”組織運営は機能する?
NVIDIAフアンCEOが「1on1」をしない理由 “階層なき”組織運営は機能する?
半導体大手の米NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、上司と部下が1対1でミーティングをする「1on1」をしないことで知られている。世界で3万人超の従業員を率いているにもかかわらず、直属の部下であるリーダーシップ・チーム(日本で言う経営会議)は60人。その他には階層がないという。特異な組織運営をする狙いを、フアン氏が語った。 NVIDIAフアンCEOに聞く孫正義氏の「先を見通す力」 ASI実現への見解は?
NVIDIAフアンCEOに聞く孫正義氏の「先を見通す力」 ASI実現への見解は?
米NVIDIA創業者でCEOのジェンスン・フアン氏は、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏と対談した。ITmedia ビジネスオンラインはフアン氏に、孫氏が掲げてきた人類の1万倍の知能を持つ「ASI」実現のビジョンについて見解を聞いた。 孫正義氏とNVIDIAフアンCEOが語り合った「AIの未来」 高性能AIスパコン構築へ
孫正義氏とNVIDIAフアンCEOが語り合った「AIの未来」 高性能AIスパコン構築へ
NVIDIA創業者でCEOのジェンスン・フアン(Jensen Huang)氏が、東京都内で開催した自社イベントで、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏と対談。フアン氏は孫氏と「ここから共に価値を作っていきましょう」と話した。 孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?
孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?
ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は、個人専用のAIが予定の管理や買い物などを代行する「パーソナルエージェント(PA)時代」が数年以内に到来するとの見方を明らかにした。 “孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」
“孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」
「部下と議論するより面白い」と株主総会で会場を沸かせた孫正義氏のChatGPTの使い方とは。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング