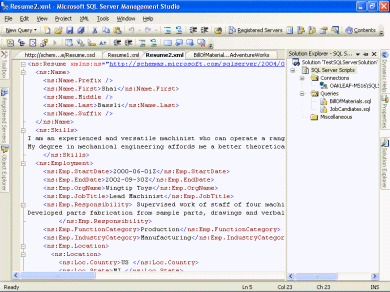特集:準備が整ったSQL Server 2005:Visual Studio Magazine(4/5 ページ)
SQL Server 2005は、「localhost」ではなく、「サーバ名\インスタンス名」という名前付きインスタンスとしてインストールすることもできるため、もしそうした環境ならば、プロジェクトのプロパティのダイアログボックスのサーバ名や、データソースの設定ファイルとなるadventure_works.dsファイルの接続文字列(Connection String)の設定を環境に合うように変更してほしい。
なお変更する場合には、adventure_works.dsをダブルクリックするか、右クリックし、[Open to display the Data Source Designer dialog]を選択すればよい。ベータ2では、[プロパティ]を選択することはできない。
グラフィカルなDTSデザイナーでは、フラットなファイルのインポート機能が強化された「DTSインポート/エクスポート・ウィザード」を使うことで、作成されたパッケージをあとから拡張できる。
列の長さやデータ型をカスタマイズするときには、事前にプレビューすることで、データが切り詰められてしまわないかを確認できる。
ウィザードではさらに、新しいデータベースや新しいテーブルを加えたり、既存のテーブル内に新しい列を定義したりすることもできる。
SQLネイティブクライアントを使う
SQLのネイティブクライアントドライバ(SQLNCL1.dll)は、SQL ServerのOLE DBプロバイダおよびODBCプロバイダを単一のDLLとしてまとめたものだ。
このDLLは、Windows 2000 SP3にインストールされている「MDAC(Microsoft Data Access Component) 2.5 SP3」以降の環境で動作する。
SQLネイティブクライアントを使うことで、ADOからアクセスするときに、ユーザー定義タイプ(UDT:User Defined Type)やXML機能、varchar(max)、nvarchar(max)、varbinary(max)のような、SQL Server 2005の新機能を使えるようになる。
SQLネイティブクライアントでは、スナップショット分離レベル(snapshot transaction isolation)や複数のアクティブな結果セット(MARS:Multiple Active Result Sets)、非同期コマンド、そして、有効期限が切れたパスワードの変更といった機能も利用可能だ。
SQLネイティブクライアントドライバは、Windows Installer形式の「SQLNCL1.msi」を使うことで、再配布できる。SQLネイティブクライアントドライバは、ネットライブラリにおいて非同期コマンドをサポートする(SQL Server 2000では非同期コマンドサポートしていない)。
スナップショット分離レベル、MARS、そして非同期コマンドについては後述する。
SQL Server 2005では、管理方法やレプリケーションの方法も変更された。
SQL Server 2005では、従来の管理オブジェクトであった「SQL Distributed Management Objects(SQL-DMO)」が「SQL Management Objects(SMO)」と「Replication Management Objects(RMO)」の2つの管理オブジェクトに分離された。
SMOとRMOは、それぞれ「Microsoft.SqlServer.Management」と「Microsoft.SqlServer.Replication」の名前空間に存在する.NET 2.0のアセンブリだ。これらは、SQL Server 7.0と2000もサポートするが、SQL Server 2005の場合に最も高いパフォーマンスを発揮する。
SMOは従来SQL-DMOを使って管理していたアンマネージのコードをマネージドコードに置き換えるものだ。従来のSQL-DMOを使って作っていたものと同様なプログラムは、.NETコンポーネントの参照で、Visual Studio 2005による作成が可能だ。COMラッパーを使えば、アンマネージドコードであるVB、C++、VBScriptからも、SMOを使ってプログラミングすることが可能だ。
XMLを使っているユーザーは、XMLデータ型とXQueryの機能を評価することだろう。
SQL Server 2005では、XMLデータをBLOB型のデータとみなし、ドキュメントの構造、要素の順序、そして再帰的な構造が丸ごと保存される。そのため、XMLスキーマを定義して型定義したXML列として扱うか、それとも、型定義せずに扱うのかを選択できる。
SQL Server 2005には、ひとつのトップレベルの要素を含んだウォルフォームドXMLドキュメントだけでなく、トップレベルの要素が欠けた要素の集合となるXMLドキュメントでも格納できる。SQL Server 2005では、エンコード方式として、一般的なUTF-8ではなくUTF-16を採用している。
型定義したXML列では、スキーマを定義したXML名前空間を指定する。そうすることで、データエンジンは、挿入されたXMLデータや編集されたXMLデータの検証が可能となる(画面5)。
型定義したXML列では、さらに、クエリのために最適化されたり、性能を向上するためにインデックス付けされたりする。XMLクエリのプランは、実行プランダイアグラムにも現れる。
XMLデータ型の列は、クエリエディタのグリッドにおいて、データへのリンクとして示される。リンクをダブルクリックすると、書式化されたXMLコンテンツがXMLエディタページに現れる。xmlns:nsアトリビュートの値は、schemas.microsoft.comで定義されたスキーマ情報だ。Ctrlキーを押しながらクリックすれば、そのスキーマ情報を参照できる。インテリセンス機能も有効で、要素の始まりである「<」を入力すると、その位置に入力可能な要素一覧が表示される。XMLエディタ上で保存すれば、データベースのデータが更新される(訳注:ベータ2では、まだインテリセンス機能が提供されていない)。
© Copyright 2001-2005 Fawcette Technical Publications
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題
- 新たな基準になる? NSA、ゼロトラスト実装指針「ZIGs」のフェーズ1・2を公開
- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに
- 長期記憶で能力を進化 Googleらが脆弱性解析を自動実行するLLMを提案
- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音
- Gartner、2026年のセキュリティトレンドを発表 6つの変化にどう対応する?
- 作業効率爆上がりでも不幸になる? 開発者を襲う「AIのパラドックス」とは
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- Active Directoryの心臓部を狙うNTDS.dit窃取攻撃の全貌とは?
- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍