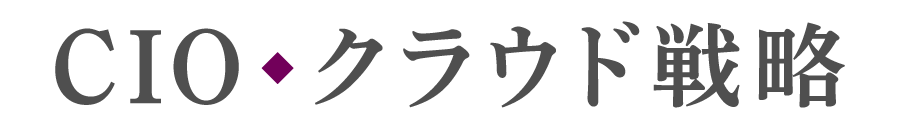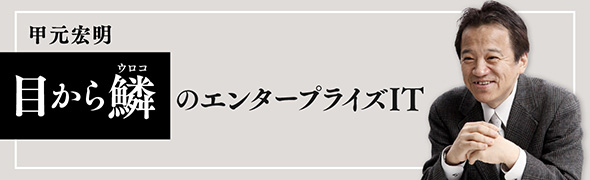なぜIT部門は市民開発を嫌うのか? 「“野良化”回避」より重視すべきこと:甲元宏明の「目から鱗のエンタープライズIT」
かつて一般従業員による開発がノーコード/ローコードツールを駆使するものに限定されていた時代は終わり、AIを駆使すれば誰でもアプリケーションを開発できる環境が整いつつあります。こうした変化の中で、IT部門の役割はどう変わるのでしょうか。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
この連載について
IT業界で働くうちに、いつの間にか「常識」にとらわれるようになっていませんか?
もちろん常識は重要です。日々仕事をする中で吸収した常識は、ビジネスだけでなく日常生活を送る上でも大きな助けになるものです。
ただし、常識にとらわれて新しく登場したテクノロジーやサービスの実際の価値を見誤り、的外れなアプローチをしているとしたら、それはむしろあなたの足を引っ張っているといえるかもしれません。
この連載では、アイ・ティ・アールの甲元宏明氏(プリンシパル・アナリスト)がエンタープライズITにまつわる常識をゼロベースで見直し、ビジネスで成果を出すための秘訣(ひけつ)をお伝えします。
「甲元宏明の『目から鱗のエンタープライズIT』」のバックナンバーはこちら
近年、「市民開発を進めたいが、シャドーIT(野良化)になると困る」という相談が国内企業のIT部門から寄せられています。企業としてデジタル化を推進する上で、ユーザ部門(事業部門)や現場レベルで主体的にアプリケーションを開発・運用し、業務効率化やビジネス拡大に貢献できるのは大きなメリットです。
一方でそれを「勝手に開発されるとITガバナンス上の問題になる」と恐れる向きもあります。筆者は、あらゆる開発をIT部門が細かく管理しようとすることで失われるものは大きいと考えています。また、今後IT部門に求められる役割は「管理」や「審査」ではないとも思っています。
「野良化」回避施策で失われるもの
まず、「野良化」回避施策で失われるものについて考えてみましょう。筆者は、野良化を回避するための施策を実施することにより、せっかくのスピード感が削がれたり、創造的なアイデアが失われてしまい、市民開発の長所を生かしきれない状況が生まれがちだとみています。
ここで重要なのは、市民開発とは決してローコード/ノーコードによる開発だけを指すものではないという点です。
確かにローコード/ノーコードのプラットフォームは、プログラミング知識の浅い人でも比較的簡単に業務アプリケーションを作れるため、多くの企業で採用が進んでいます。しかし最近では、「Pythonを使ってAIアプリケーションを作りたい」と考える新入社員や、海外発のアプリケーションや先進的なプログラミング言語を使ってデジタルサービスを試作するデジタルネイティブ世代が台頭してきました。
こうした若手やデジタルテクノロジーに明るい人材が自主的に実装し、試行錯誤しながら組織に新たな価値をもたらすことは、企業全体のイノベーションを進展させる大きな可能性を秘めています。
にもかかわらず、中堅以上のIT部門担当者の中には、最新テクノロジーの内容や価値を十分に理解できていない人もいます。「AIなんて本当にウチの業務に役立つのか」「海外製アプリを使われるとセキュリティが心配だ」などといった未知のものへの警戒心から制限をかけようとしてしまうのです。
確かにセキュリティやコンプライアンスの確保は重要です。ただし、「市民開発」の本質を考えると、ある程度の自由度がなければユーザ部門が自主的に動き出すことは難しく、シャドーIT化するのはむしろ必然といえます。
「民主化」という言葉は政治や地方自治の文脈でよく使われますが、本来は「誰もが同じように意思決定や実行に関わることができる」という価値観を意味しています。市民開発も同様に、テクノロジーやアプリケーション開発を特定の専門家が独占するのではなく、必要性を感じた当事者が自ら動いて変革を起こせる状態こそが望ましい姿です。
IT部門からすれば「野良化」や「シャドーIT」というネガティブな印象があるかもしれません。しかし、業務やビジネスに実際に貢献し、当事者が責任を持って運用しているのなら、それはもう立派な「正規アプリケーション」といえるはずです。「野良化」「シャドーIT」という言葉自体がIT部門の一方的な視点から生まれたものであることを忘れてはなりません。
管理部門からデジタルテクノロジ活用推進部門への転換が必要なIT部門
歴史を振り返ってみても、あまりに強い管理や統制によって新たなテクノロジーの活用を厳しく制限すると、イノベーションが阻害されるばかりか、現場のモチベーションや自発的な工夫が失われる結果となることが分かっています。特に日本企業のIT部門は、「ガバナンスをきかせなければ」という強迫観念を抱きがちです。また、厳格なシステム台帳の作成や詳細な承認プロセスこそがガバナンスだと考えてしまうケースが多くあります。
しかし、そのような書類中心、承認中心の形式的な管理に固執してしまうと、実際のシステム運用や開発の中身がブラックボックス化します。万が一「IT部門で統合的に運用を引き継ぐ」という状況が発生したときに、結局何も分からず対応できないという事態に陥りかねません。
かつて、企業におけるグループウェアとして一世を風靡した「Notes」は、本来は集中管理型システムとして導入されていました。しかし、結局はあちこちの部署で無数のDB(データベース)やアプリケーションが作られ、それぞれが「野良化」する状況が多発しました。
結局、どこで何がどのように運用されているのかが把握できなくなり、IT部門として管理したりサポートしたりすることが不可能に近い状態に陥ってしまったのです。
こうした歴史を振り返ると、IT部門が「管理部門」として振る舞うだけでは、企業全体のデジタル化をうまく進められないことがよく分かります。
「管理」という行為は、どうしても「管理する側」と「される側」を区別するため、組織内に分断意識を生みがちです。ITガバナンスを推進するためのCoE(Center of Excellence)や、月例のIT部門会議などの仕組みを整備している企業もありますが、実際には承認や審査ばかりが増え、スピード感のある提案が通りにくくなるなど、現場の意欲が削がれてしまうという問題があります。「管理」や「審査」からは生まれにくい新しいアイデアこそが、今のデジタル時代には必要です。
今後のIT部門のあるべき姿とは?
今後のIT部門に求められるのは、従来型の「管理部門」から脱却し、「デジタルテクノロジー活用を支援・推進する部門」に変革することだと筆者は考えています。管理そのものを否定するわけではありませんが、最低限必要なルール整備やリスク管理にとどめ、各部署が自由にデジタル技術を試行しやすい環境づくりとサポート体制こそが、現代の企業においてIT部門が果たすべき役割ではないでしょうか。
真のCoEが創発的共創を社内で活性化させる
では、実際にIT部門がどのような組織形態や運営方針を取ればよいのでしょうか。現代の企業にとって必要とされるのは、「管理」や「審査」ではなく、「コラボレーションのためのつながり」を促進する仕組みです。これが真の意味でのCoEや、フェデレーテッド・ガバナンス(Federated Governance)の考え方につながります。
真のCoEとは、単なる審査組織や統括会議ではなく、社内でデジタルテクノロジーに関する知見を共有し、成功事例や失敗事例をオープンに蓄積し、必要とする人たちがいつでもアクセスできるハブのような存在です。そこでは、従業員が自ら学習し、試行錯誤するための環境が整えられています。疑問や課題を相談すれば、専門家のアドバイスを気軽に得られます。こうした「つながり」を通じて、各現場の業務に最適化されたアイデアが次々と生まれ、それをすぐに試せるアジリティが確保されるのです。
さらに大切なのは、実装経験のないリーダーやテクノロジーへの理解が浅いマネジメント層が開発プロジェクトの意思決定に過度に介入することを防ぐ仕組みづくりです。
最新のクラウドサービスやAI技術を活用すれば、たとえ1人のエンジニアであっても設計から開発、運用に至るまで一貫して実行することが可能です。オンプレミスサーバを立ち上げていた時代とは異なり、大規模な初期投資や複雑なシステム管理は必要ないため、技術に明るくモチベーションの高い従業員がスピーディにイノベーションを生み出せる環境が整いつつあります。
「開発は事業部門、運用はIT部門」といった昔ながらの役割分担を押し付けるのはナンセンスです。開発者自身が運用まで責任を持つ方が結果的に使いやすく持続的にアップデートされるシステムが生まれやすいのです。
もちろん、どれだけAI翻訳が進歩しても、英語を母国語とする人の流暢さにはかなわないように、全て市民開発だけで賄うのは現実的ではありません。高度なセキュリティ要件や大規模なシステム連携が求められるプロジェクトでは、やはり専門家のサポートが必要です。しかし、その専門家と現場(市民開発者)が対等にコラボレーションし、お互いの得意分野を活かす体制が整備できれば、市民開発の枠を超えた大きな成果が期待できます。
従業員全員がイノベーションの担い手に
要は、「市民開発=ローコード/ノーコード」という狭いイメージを捨て、デジタル技術に関心のある従業員全員がイノベーションの担い手になれる環境を整えることがゴールなのです。
AIやスタートアップ企業のクラウドサービスを取り入れることを市民開発の一部として捉えれば、企業のデジタル活用は爆発的に広がります。IT部門に求められるのは、そのような「真の民主化推進体制」と「専門家による支援」を両立させるリーダーシップです。
管理による抑制ではなく、共創を促す「ハブ」として存在し、従業員の自主性や探求心を後押ししながら責任ある運用をサポートする――。これこそが、今の時代にふさわしいIT部門の在り方ではないでしょうか。
このように、企業のデジタル戦略が高度化し、多様なテクノロジーが登場する現代においては、IT部門が「管理」だけを生業とするのではなく、むしろ先端技術の知識や経験をもつ専門家集団として、社内のあらゆるイノベーションを支援し、推進する役割を担う必要があります。
これこそが「真のCoE」と呼べる状態であり、ひいては組織全体の競争力強化につながるのです。市民開発を制限して野良化を回避しようとするのではなく、広い意味での市民開発を積極的に受け入れ、デジタルテクノロジーに関する知見を社内で共有し、創発的共創を最大限に引き出す――。こうした姿勢こそ、今後の企業が求めるIT部門の理想像と言えるでしょう。
筆者紹介:甲元 宏明(アイ・ティ・アール プリンシパル・アナリスト)
三菱マテリアルでモデリング/アジャイル開発によるサプライチェーン改革やCRM・eコマースなどのシステム開発、ネットワーク再構築、グループ全体のIT戦略立案を主導。欧州企業との合弁事業ではグローバルIT責任者として欧州や北米、アジアのITを統括し、IT戦略立案・ERP展開を実施。2007年より現職。クラウドコンピューティング、ネットワーク、ITアーキテクチャ、アジャイル開発/DevOps、開発言語/フレームワーク、OSSなどを担当し、ソリューション選定、再構築、導入などのプロジェクトを手掛ける。ユーザー企業のITアーキテクチャ設計や、ITベンダーの事業戦略などのコンサルティングの実績も豊富。
関連記事
 内製化が進めば、SIerはいらない? 元IT部門の筆者が考える「内製化時代のパートナーの条件」
内製化が進めば、SIerはいらない? 元IT部門の筆者が考える「内製化時代のパートナーの条件」
「内製化が進めばSIerに頼る必要はないのでは」と考えがちですが、筆者の考えは違います。では、内製化を進める企業はパートナーをどう選ぶべきでしょうか。RFP評価以外に重視すべきポイントとは。 「ロー/ノーコードで内製化」は机上の空論? 成果が出ない企業の共通点【調査】
「ロー/ノーコードで内製化」は机上の空論? 成果が出ない企業の共通点【調査】
キーマンズネットでは内製化の取り組みの「現在地」に迫る読者調査を実施した。その結果から見えてきた、ローコード/ノーコードツールの導入効果が「期待を下回った」と回答したユーザー企業の意外な共通点とは。 「内製化」に取り組む大企業の割合は? 調査から浮上したDX推進企業の“ある考え”
「内製化」に取り組む大企業の割合は? 調査から浮上したDX推進企業の“ある考え”
IDCが実施した調査によって、DXを推進する大企業の中で内製化に取り組む企業の割合と、内製化の対象としている業務内容が明らかになった。IDCはここから大企業の「ある考え」が浮かび上がったとしている。 AI時代にグンと伸びる「AI以外のツール」とは? ITR調査
AI時代にグンと伸びる「AI以外のツール」とは? ITR調査
ITRの調査によると、AIブームの中、2桁成長が続いているAI以外のツールがあるという。高成長が続いている背景と併せて見てみよう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億
- 富士通、開発の全工程をAIで自動化し「生産性100倍」 自社LLMのTakaneを活用
- Chromiumにゼロデイ脆弱性 悪用コードが流通済みのため急ぎ対処を
- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明
- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌
- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由
- 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新
- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ