AWSが日本に2兆円投資する理由 大規模イベントで語られた未来の姿:AWS Summit Japan 2025
「AWS Summit Japan 2025」の基調講演において、AWSが日本市場に2兆2600億円を投資し、生成AIやクラウドを基盤とするビジネス変革、人材育成、社会課題解決を支援する姿勢を明確にした。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
Amazon Web Services(AWS)は2025年6月末に幕張メッセで「AWS Summit Japan 2025」を開催した。「ビルダーと描く新たな価値創造」と題した基調講演ではアマゾンウェブサービスジャパンで代表執行役員社長を務める白幡晶彦氏や、AWSのバイスプレジデント生成AIおよびAI/MLマーケット戦略担当のラフール・パサック氏、Anthropicの上級副社長 グローバル営業統括責任者のケイト・ジェンセン氏などが登壇した。
AWSはこの講演を通じて、ビジネスや社会の課題に挑む開発者の大胆なビジョン実現を支援する姿勢を明確にし、新たな取り組みや先進的な導入事例などを発表した。
日本への長期投資とAWSの社会的役割の再定義
白幡氏は冒頭で日本市場への強いコミットメントを示し、2027年までに2兆2600億円を国内に投資することを発表した。これはクラウドインフラの整備に加えて、生成AIを含む先端技術の実装、教育機関との連携、地域創生に至るまで多岐にわたる。
この投資の背景には、クラウドの役割が従来のコスト削減や業務効率化を超えて、社会インフラの一部として進化しているという認識がある。東京と大阪の2拠点体制によるマルチリージョン構成が言及され、高可用性とレジリエンスの確保が強調された。災害時のサービス継続性を担保する構成が既に多くの公共系システムで活用されている。
AWSはこのような社会基盤としての位置付けに加え、パートナー企業や地域と共に価値を生んでいくという姿勢が一貫して示され、スポンサーや自治体、教育機関と協調することで、技術だけでなく人と仕組みも育てていく構えが読み取れる。
同講演では日本企業の現場に深く入りこみ、技術と業務の架け橋になる支援の必要性も言及。地方自治体や医療機関との実証実験などを通じて、AWSが社会課題の解決に携わっていることが強調された。サステナブルな医療を目指すSUSMEDの治験支援システムや、核融合エネルギーの研究加速支援などが具体例として挙げられた。
AWSが描く未来像には、長期的かつ包括的な変革が重要視されており、その中心には日本独自のニーズに基づいた支援がある。2023年の「LLM開発支援プログラム」、2024年以降の「生成AI実用化推進プログラム」には既に200社以上の企業が参加し、具体的な成果が生まれているという。
生成AIの導入加速とビジネス変革の現実化
同講演では日本企業における生成AIの導入状況も発表された。AWSの調査によれば、国内企業の82%が何らかの生成AIツールを導入済みであり、36%が既に業務への実装を進めている。55%の企業がチーフAIオフィサー(CAIO)を任命し、翌年にはこの割合が84%に達するという見込みだという。
AWSはこの需要に応えるため、生成AIの実行環境を抜本的に強化している。「Amazon Bedrock」を軸に、「Claude」モデルや「Titan」シリーズの活用、GPUインスタンス(P5/P5e)のオンデマンド提供などを進めており、柔軟かつ即応的な構築が可能となっている。これにより、中小規模の企業でも大規模演算リソースを短期で利用可能になっている。
同講演に登壇したAnthropicのケイト・ジェンセン氏からは日本オフィスの開設が発表され、「日本と共に、AWSと共に、Claudeを構築する」という方針が示された。楽天や野村総合研究所(NRI)、パナソニックといった企業では既にClaudeを業務に組み込み、コード生成や文書作成、意思決定補助に活用している。
企業にとって重要なのは、モデルの性能そのものではなく自社のユースケースにいかに適合させられるかであり、AWSはモデル選択・カスタマイズ・運用監視の一連のプロセスをフルマネージドで提供し、実装コストとハルシネーションリスクの低減を同時に実現することを目指す。
レガシーシステム再構築とDX推進の実践例
設計書が残っていない、依存関係が複雑、ブラックボックス化しているといった旧来の基幹システムの問題が、日本企業における技術導入の足かせとなってきた。これに対し、AWSはAIを活用したモダナイゼーション支援ツール「AWS Transform」を提供し、システム改修の迅速化と省力化を図っている。
AWS Transformは仕様書が欠落しているレガシーシステムでも生成AIによって構造やロジックを自動解析し、設計書を再生成でき、従来は年単位かかっていた再構築プロジェクトが月単位で完了可能となったという事例も紹介されている。NRIは業界特化型生成AIモデルの独自構築や、レガシーシステムの移行支援に生成AIを組み込むことで現行システムの分析・設計における工数を約40%削減する。三菱電機でも生産システムのモダナイズにかかる工数を50%削減できたという。
これらの実践例は、AIが単なるツールではなく、事業構造を支える中核的なエンジンとして位置付けられていることを示している。もはやAIは導入するかどうかではなく、どう生かすかというフェーズに入っていることがうかがえる。
ビルダー育成と地域連携による持続的成長の構築
同講演では「ビルダー」というキーワードが繰り返し登場した。AWSは価値を創造する人々をビルダーと定義し、技術者に限定しない広義の人材像を提示した。これは単なる技術研修ではなく、創造的な挑戦を支える文化と環境を整備するという思想に基づいている。AWSは、旭川工業高専および富山高専と連携協定を締結し、AI・数理・データサイエンス分野の拠点校としての育成支援を始めている。また地域課題解決型のAIコンテストや小中学生の技術体験イベントを通じて、次世代人材の発掘と育成を全国規模で展開している。
これらの取り組みは、中央集権的なイノベーションの限界を見据えたものでもある。AWSは「イノベーションは分散型でこそ活性化する」という立場から、地方創生と教育を不可分のものとして扱っている。クラウド基盤を提供するだけでなく、それを活用する地域の人材と課題にまで踏み込む支援体制が構築されつつある。
AWSはビルダー支援を単なるスキル習得ではなく、長期的な産業構造の変革の一環と位置付け、国内のAWSパートナーとも連携しつつ、地域経済の中にテクノロジーの芽を根付かせていく方針を語っている。
AWS Summit Japan 2025の基調講演は、単なる技術発表にとどまらず、AI・クラウド時代における日本企業の未来図と、それを支える基盤・人材・社会の在り方を総合的に示すものであった。技術の進化そのものよりもそれを活用して変化を起こす意志と環境づくりが、今後の競争力に直結するという構造的な問題意識が全編を通じて貫かれていた。
関連記事
 Anthropicが日本法人を設立 「日本のために、日本と共に」
Anthropicが日本法人を設立 「日本のために、日本と共に」
Anthropicが2025年秋にも日本法人を設立することが分かった。同社が語る日本法人設立の目的とミッションとは。 横浜市がRAG導入を検証 実証で分かった「できるコト」「苦手なコト」
横浜市がRAG導入を検証 実証で分かった「できるコト」「苦手なコト」
横浜市とNTT東日本神奈川事業部は生成AIのRAG技術の実証を実施した。RAG環境構築やプロンプト調整を通じて9割の回答精度を達成し、今後の課題や人材不足にも言及している。 IBMのメインフレームがAI時代に息を吹き返しているワケ
IBMのメインフレームがAI時代に息を吹き返しているワケ
AIの普及に伴ってIBMはクラウドを中心としたソフトウェア部門にも力を入れている。2025年夏頃には新製品の発表も控えており、ソフトウェアとインフラの両輪で大企業のニーズを取り込む狙いだ。 ビジネスを変える可能性あり? Google「Gemini Diffusion」の要素技術「拡散言語モデル」とは
ビジネスを変える可能性あり? Google「Gemini Diffusion」の要素技術「拡散言語モデル」とは
Googleが発表した「Gemini Diffusion」は過去最高速のモデルよりも大幅に高速なコンテンツ生成が可能です。この背景にあるスタンフォード大学の研究成果「拡散言語モデル」を解説します。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
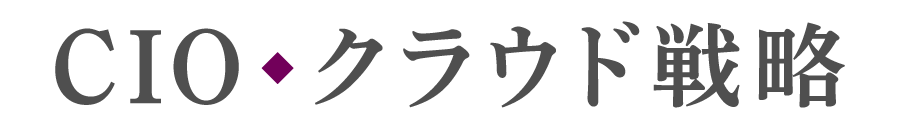
 日本への投資を発表する白幡氏(出典:編集部撮影)
日本への投資を発表する白幡氏(出典:編集部撮影) AWSとの協業を強調するジェンセン氏(出典:編集部撮影)
AWSとの協業を強調するジェンセン氏(出典:編集部撮影)