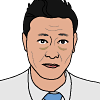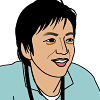仕事に生きた男の悲しい物語:目指せ!シスアドの達人−第2部 飛躍編(14)(1/4 ページ)
副社長の西田の取り計らいで、西田、ホテイビール社長の布袋四郎、ホテイドリンク社長の布袋泰博、そしてホテイドリンク・システムセンター長の園村との磯釣り1泊旅行に参加した坂口は、園村と2人、夜の宴席の後のひとときを過ごしていた。
缶ビール片手に園村は、彼の業務改革にまつわる忘れ難いエピソードを、坂口に語り始めた。
園村 「あれは……。いまから5?6年前になりましょうか」
園村は、遠くを見るような眼差しで、窓外の海に目線を移した。
ホテイドリンクを見学した際、堂々とした業務改革の話を聞かせてもらった時の感動が、坂口の脳裏に蘇ってきた。
園村がどんなエピソードを聞かせてくれるのか、坂口は神妙な面持ちで園村を見つめた。
園村 「泰博さんと私は親会社から飛び出して、独自の物流システムの構築に乗り出していました。“小が大をのみ込んででっかい物流サービス会社に成長する”という泰博さんの夢をかなえるためには、融通の利かない親会社のレガシーシステムと決別するという道を選ぶ必要がありました。親会社の情報システム部門から転籍した私とあと数名のメンバーで、プロジェクトはスタートしました。なぁに、泰博さんを小さいころから存じている私がお守り役に選ばれたんだろうと思います。転籍したメンバーが私と長年の付き合いのある部下ばかりだったのは、そのころうまくいっていなかった布袋家の親子関係において、四郎さんのせめてもの親心だったんだろうと思います」
坂口は、園村が2人の社長をいつの間にか名前で呼ぶようになっていることに気付き、その親密な間柄をあらためて認識したのだった。
園村 「坂口さんは新しいシステムを作るために、まず何から始めていますか?」
坂口 「……現状の把握、業務分析でしょうか」
園村 「そのとおりです。私たちは、ホテイドリンクのすべての物流業務を把握するために、日本中に点在している物流センターを訪ねて業務実態の調査に乗り出しました。そのなかで、私たちはある逸材に出会ったのです。小沢隆夫という青年です。当時33歳くらいでしょうか。彼は前職がトラック運転手でね、うちのトラックと事故を起こしたんですよ。そして、その示談交渉で彼の勤めていた会社と弊社がちょっともめ事になりましてね、泰博さんが自らその会社へ出向いて示談してきたんです。その時に泰博さんは小沢くんの才能に気付いて、彼をヘッドハンティングしたんです。泰博さんは、宝物を見付けたといっていました」
手に持ったビールをひと口飲み、園村はさらに続けた。
園村 「そして彼にトラックの運転手をやらせるのかと思ったら、西東京物流センターの内勤を命じたんです。そこで商品の配送計画を作る仕事に就かせたんです。彼は本当によく働きました。仕事ののみ込みも早く、恐ろしいくらいのスピードで日次、週次、月次の配送計画を完成させていくんです。どうやら、前の会社でも要領の良さでは、抜群の実力を発揮していたようなのですが、寡黙で人見知りする性格なので、周りとのコミュニケーションがうまく取れなかったのでしょうな、社内で孤立してしまっていたようなのです。なかなか1つの会社に長く勤められずに悩んでいました。それが泰博さんに一目置かれて、内勤職で実力を発揮できるようになったんです。さぞ嬉しかったんでしょう。性格も徐々に明るくなってきました」
坂口は、人の良いところを瞬時に見いだして生かした布袋泰博の力量に、あらためて感心していた。
園村 「でも、私の彼に対する第一印象は決して良いものではありませんでした……」
対立する現場とシステム部
時間はさかのぼり、いまから6年前。園村は、神奈川県相模原市にある西東京物流センターを訪れていた。抜群のセンスで配送計画を作り上げる小沢の業務プロセスを分析し、システム化するためだ。
園村 「小沢くん、はじめまして。システムセンター長の園村です。今回は小沢くんの担当している業務プロセスを聞かせてもらおうと思って来ました。といっても、いきなり順序立てて説明するのは難しいだろうから、普段の業務の様子を少しずつでもいいから教えてくれないかな」
小沢 「申し訳ないですが、園村さんにお話しすることは何もありません……」
そういうと小沢は、何事もなかったかのようにまた仕事に戻った。明らかに園村を警戒し、協力するつもりがないことをアピールしている。
そのころ、小沢は社内で有名になっていた。運送中のトラックが事故に巻き込まれたり、災害で荷物の到着が遅延したり、欠品が発生したときの危機回避能力が尋常でなく高いからだ。ありとあらゆる情報を集めて、最適なリカバリープランを短時間で仕上げる能力は抜きんでている。
当時、配送トラブルの多かった相模原に小沢を異動させたのは布袋泰博だった。小沢は自分の仕事に自信と誇りを持っていたため、園村たちが新しいシステムを作るための調査に来たことで、人生でやっと出会えた天職を脅かされると思っていたのだ。
その後、園村は小沢の元へ何度も足を運んだが、いつも態度は同じだった。
小沢 「見ていただければ分かると思います、お話しするようなことはございません……」
しかし園村はあきらめるわけにはいかなかった。小沢の業務は新システムの要素として極めて重要な部分だからだ。
配送計画の完全自動化と、交通事故などの予期せぬ障害発生時の代替計画策定プロセスのシステム化が投資対効果の観点で非常に有効であり、顧客満足度向上への貢献度も大きいというコンサルタントの見解も出ていた。
ただし、すべての自動化を目指していたわけではなく、小沢の思考プロセスの一部をシステム化することで、小沢が不在のときにも同様のパフォーマンスを維持できるようにすることを主目的としていた。そうした背景を、園村は何度も小沢に説明したが、一向に小沢は心を開かなかった。
しかし、3カ月ほど経過したころから小沢の様子が少しずつ変わり始めた。業務の手順を1つ、2つと説明するようになったのだ。園村は、自分がしょっちゅう顔を出すものだから、ついに降参したのかと思っていたが、小沢が変化したのは別の理由であった。
小沢に婚約者ができたのだ。相手は小学校からの幼馴染みで名前は美雪。なかなかの美人だった。その後分かったことだが、どうやら彼女が小沢を説得したのだった。「あなたに天職を与えてくれた会社が、あなたの不利益になるようなことをするわけがない。園村の相手を少しはしてあげるように」と。
そして、徐々に自分の仕事のことを話すようになった小沢だが、その説明はあまり要領を得たものではなかった。断片的というか、思考プロセスが部分的にあちこち飛躍しながらの説明で、業務プロセスを可視化しにくいのだ。小沢は、どうしても話の核心に迫ると言葉を濁し、まだシステム化に対して不安に思うところがあるようだった。
しかし園村も必死だった。そのころ、システム再構築プロジェクトは基幹となる物流計画機能の要件定義が遅々として進まずに、すでに2カ月の遅延を抱えていた。園村は小沢の横について一緒に作業の流れ図を作って、2人で夜遅くまで話し合った。
そして、ようやくプロセス分析が完了したとき、小沢はポツりとつぶやいた。
小沢 「これで、私の居場所はなくなるかもしれませんね……」
しかし、園村は即座にこう答えた。
園村 「そんなことは、この園村がさせませんよ! あなたは当社にとってかけがえのない宝物です。布袋社長もそのように言ってますよ、小沢くん。ITを使ってあなたの活躍の場がさらに広がるんですよ!」
小沢は黙ってうなずいた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用
- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?
- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る