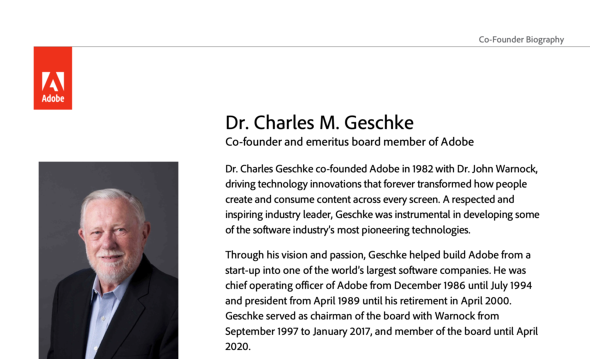チャールズ・ゲシキとジョン・ワーノックが拓いたデスクトップとデジタル、2つのパブリッシング革命を振り返る(1/2 ページ)
米Adobe創設者の一人である故・チャールズ・ゲシキ氏らが生み出した技術を、日本のDTP黎明期から使っているエディトリアルデザイナーの菊池美範さんに振り返ってもらった。
〜〜
2021年4月16日、ジョン・ワーノック氏とともにAdobeを共同設立したチャールズ・ゲシキ氏が逝去された(Adobeのプレスリリース)。享年81歳だった。
ゲシキ氏は1982年に米Xeroxパロアルト研究所の同僚であったワーノック氏とAdobeを創業した。同社は20世紀の出版革命ともいわれたDTP(デスクトップパブリッシング)の中核となるPostScript(ポストスクリプト)の技術とライセンシングによって成長を続けたが、さらにAcrobatによってPDF(Portable Document Format)をOSや機種に依存しない電子文書の業界標準としてポジションを固めた。
Adobeが現在の姿になるための基礎となったのはこの2つによるところが大きい。両氏はAdobeのテクノロジーという樹を支える大地のような存在であり、経営や開発の現場から退いた後も、社員たちの頭上に輝く2つの星であったことは間違いない。その星の一つが宙(そら)から消えた。
ご冥福をお祈り申し上げるとともに、ゲシキ氏の偉業に深い感謝を申し上げたい。
日本語PostScriptのパートナーはモリサワ
1987年、Adobe(当時はAdobe Systems)はモリサワと日本語PostScriptフォントを共同で開発することを宣言した。
まだ黎明期にあったDTPは独自のハードウェアと規格が覇を競っていた時代だ。ジャストシステムは一太郎Ver.3の好調に乗って独自のDTPシステムである「大地」を普及させるために動き、PC用の各社ワープロソフトは当時のマシンスペックと、OS(MS-DOS、Windows)の制限下でDTP的な表現の努力をしていた。
しかし、多くの文字数と組版ルールを持つ日本のグラフィックデザインや出版で使用するには限界があった。そこにAdobeはモリサワとパートナーシップを組むことで、これ以降に続く業界標準の地位を固めた。ゲシキ氏とチャールズ氏がパートナーとしてモリサワを選んだことで、基本的な日本語PostScriptフォントが利用できるようになり、Linotypeなどのイメージセッターにもこれらのフォントが組み込まれ、商用レベルの版下が出力可能になった。日本市場でのビジネスは安心して展開できるようになったともいえる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR