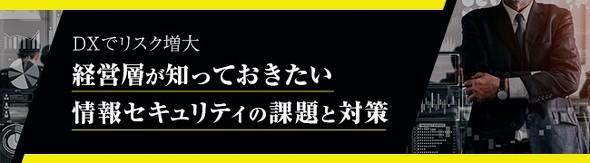「セキュリティに理解のない経営者」にならないための考え方 専門家に聞く4つの心構え:「セキュリティに理解のない経営者」にならないために(1/2 ページ)
政府がデジタル庁を創設し、社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するなど、官民や企業規模を問わずDXの取り組みが進んでいる。一方、ITの活用が広がると、企業が新たに対策すべき課題も出てくる。情報を盗まれたり、業務を停止させたりしないための情報セキュリティだ。
「企業の中には、情報漏えいを『末端の不祥事』程度に捉えているところもある。しかし現実は違う。情報セキュリティに弱みを抱えることは、ビジネスが止まる経営リスクにもなる。セキュリティはすでに、IT部門に任せるのではなく、経営者自身が取り組まなければいけない分野になっている」
セキュリティ教育に特化した私立大学、情報セキュリティ大学院大学(横浜市)の後藤厚宏学長はこう話す。業界を問わずDXが叫ばれる中、経営者はどんな姿勢で自社のセキュリティ対策に取り組むべきなのか。後藤学長によれば、経営者が持つべき心構えは大きく分けて4つあるという。
特集:DXでリスク増大 経営層が知っておきたい情報セキュリティの課題と対策
デジタル庁の創設や印鑑・FAXの見直しなど、官民でDXが進んでいる。一方、DXによる利便性の拡大は常に情報セキュリティのリスクを伴う。そこでポイントになるのが、経営層や管理職によるセキュリティへの理解とリーダーシップだ。この特集では、経営者向けの解説や最新事例、ソリューションをお届けする。
「まず経営者から始めよ」企業セキュリティの鉄則
1つ目は、とにかく経営層や幹部が少しでもセキュリティに関心を持たなければ、そもそも対策を始められないという自覚だ。「自社にとって重要な情報は何なのか、把握しているのは経営者や管理職。まずはこういった人が忙しい中でも意識を持ち、守るべき情報や止めてはいけない業務の優先順位をつけなければいけない」と後藤学長。
本来は自社が持つあらゆる情報についてセキュリティ対策を練るべきだが、企業の規模や状況によっては難しい。しかし、サイバー攻撃のリスクはもはや情報を盗まれるだけではない。米石油移送パイプライン大手のColonial Pipeline Companyがハッカー集団に攻撃を受け操業を一時停止したように、業務が止まるリスクにもなっている。
そこで必要になるのは、社内の業務構造を把握している経営層や管理職が、守るべき情報や止めてはいけないシステムを明確化することだ。重要な情報やシステムがサイバー攻撃の被害に遭う状況をシミュレーションすることで、初めて現場が対策を練れるようになるという。
「持つべき意識は自然災害への対策に近い。南海トラフ地震が起きたらどれだけの死者が出るか、避難をしっかりすれば被害者をどれだけ減らせるかを考えるように、セキュリティ対策でも、業務を支えるデジタル技術が止まればどれだけ被害が出るかといった想定が大切。そのためにはまず経営層や幹部が危機感を持たなければいけない」
関連記事
 IPA、企業のセキュリティ診断ツール無料公開 Webブラウザでセルフチェック
IPA、企業のセキュリティ診断ツール無料公開 Webブラウザでセルフチェック
情報セキュリティ対策の実施状況を企業がセルフチェックできる「サイバーセキュリティ経営可視化ツール」をIPAが公開。 コロナで企業へのサイバー攻撃も拡大 対策には「技術現場だけでなく、経営者のリーダーシップが必要」と経産省
コロナで企業へのサイバー攻撃も拡大 対策には「技術現場だけでなく、経営者のリーダーシップが必要」と経産省
新型コロナウイルスの感染が拡大した今年3月以降、企業へのサイバー攻撃の危険度が増している。経産省は、対策には経営者のリーダーシップが必要だと注意を呼び掛けた。 10大セキュリティ事件2021 2位は東京五輪へのサイバー攻撃、1位は?
10大セキュリティ事件2021 2位は東京五輪へのサイバー攻撃、1位は?
マカフィーが「2021年の10大セキュリティ事件」を発表。1位には、加盟店の名称など2000万件以上の情報が流出した可能性がある、電子決済サービス企業が利用するクラウドサービスへの不正アクセスがランクインした。 クラウドからの情報漏えい、責任は誰に? SaaSやPaaSの大前提「責任共有モデル」とは 総務省が解説
クラウドからの情報漏えい、責任は誰に? SaaSやPaaSの大前提「責任共有モデル」とは 総務省が解説
クラウドの管理ミスで情報漏えいした――こんなセキュリティ事故の責任は誰にあるのか。クラウドサービスの利用企業が把握すべき大前提「責任共有モデル」を総務省の担当者に聞いた。 クラウドの設定ミスを防ぐコツは? 100を超えるSaaSを比較した“SaaSおじさん”に聞く
クラウドの設定ミスを防ぐコツは? 100を超えるSaaSを比較した“SaaSおじさん”に聞く
クラウドサービスを導入する企業が増える一方で、設定ミスなどが原因のセキュリティ事故を心配する声も多い。では、どのような対策があるのか。クラウドの導入支援を手掛けるネクストモードの“SaaSおじさん”に説明してもらった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR