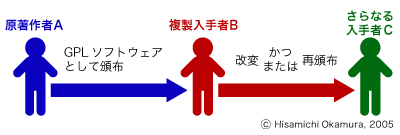いまさら人に聞けないGPLの基礎(1/2 ページ)
「GPLだとソフト売ったらダメなんでしょ?」こんなことを口走る人を目にしたことは幸いにしてないが、それに近い考えを持った人はいるかもしれない。恥ずかしい思いをする前にGPLの基礎を覚えてしまおう。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
Linuxコンソーシアムは4月27日、都内で28回目となるセミナーを開催した。Linuxのライセンスをメインテーマに据えた今回のセミナーでは、「GPLと知的財産権」と題し、弁護士で国立情報学研究所客員教授の岡村久道氏がGPLについて解説した。
GPLはなぜ生まれた?
同氏はGPLが登場した背景から説明した。コンピュータの登場当時は、利用できるリソースが限られていたこともあり、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていた。これが1970年代に入りソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めると、米国社会が急速にソフトウェア保護へと向かうことになった。この結果、米国著作権法に1980年改正でプログラムの定義規定が設けられ、同法でソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化された。
こうした著作権法によるプログラム保護に対して異議を唱えたのが、リチャード・ストールマン氏だ。同氏は1983年にGNUプロジェクトを、その推進組織としてFree Software Foundation(FSF)を1985年に設立し、フリーソフトウェア運動を提唱し始めた。ここで、「フリーソフトウェア」のフリーはそのソフトウェアのユーザーに与えられる4種類の自由、つまり「フリーダム」を意味しているのであって、「無料」を意味しているわけではない。
- 目的を問わず、プログラムを実行する自由(第0の自由)
- プログラムの動作を研究し、必要に応じて改変を加える自由(第1の自由)
- コピーを再頒布する自由(第2の自由)
- プログラムを改良し、コミュニティー全体がその恩恵を受けられるよう改良点を公衆に発表する自由(第3の自由)
とはいえ、著作権を放棄して(米国著作権法が前提)、パブリックドメイン・ソフトウェア(PDS)でソースコードを公開して無償提供してしまうと、頒布を受けたものは米国著作権法の下で、そのソースコードを改変し、作者の意図に反していわゆる「私有ソフト」(プロプライエタリ・ソフトウェア)として頒布することができてしまう。つまり、営利目的のためにクローズドな商用ソフトへと勝手に転用されてしまう可能性が生じるのである。
ここでフリーソフトウェア運動を実現するためにストールマン氏が考案した概念が「コピーレフト」である。これは、ソフトウェアをPDSにする代わりに、著作権を放棄することなく保有し、その頒布条件として、そのコードとそれから派生したどんなソフトウェアに対しても、使用・改変、そして再頒布の権利を与え、これを再頒布する人にも、この頒布条件を変更しないことを条件に改変の有無を問わず、頒布される人にもそれをコピーし改変を加える自由を与えなければならないとする概念である。
とはいえ、あくまでコピーレフトは概念であり、これを具現化するには、何らかの手段が必要となる。そこでGNUプロジェクトが考え出したのが、「GNU General Public License」、一般的には頭文字を取ってGPLと呼ばれているものである
GPLの構成と日本法との関連
現在、GPLの最新バージョンは1991年6月に発表されたバージョン2。全体の構成は、「はじめに」(Preamble)部分と、「GNU一般公有使用許諾の下での複製、頒布、改変に関する条項と条件」(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,DISTRIBUTION AND MODIFICATION)部分、「あなたの新しいプログラムにこれらの条項を適用する方法」(How to Apply These Terms to Your Programs)に大別される。このうち、本来の意味でのライセンス条項となるのは「GNU一般公有使用許諾の下での複製、頒布、改変に関する条項と条件」の部分で、全13条で構成されている。
「英文文書を正式文書とする」と明記されてるため、あくまで参考として見るべきであるが、日本語版も存在する。日本語版には、引地信之氏、引地美恵子さんが翻訳したものと、八田真行氏が翻訳したものの2種類があり、それぞれ一般公有使用許諾書、一般公衆利用許諾契約書と呼ばれている。2つの大きな違いとしては条項のズレが挙げられる。GPLのオリジナルは0条からはじまっているが、一般公有使用許諾書は第0条が第1条となっており、以降の番号も1つずつずれている。これが一般公衆利用許諾契約書では修正されている(以降の文ではこれらの日本語訳と表現が異なる部分もあるので注意してほしい)。
GPLでは第5条で、「本プログラム(または本プログラムの二次的著作物)を改変または頒布すれば、それ自体で本ライセンスを受け入れ、かつ、本プログラムまたは本プログラムの二次的著作物の複製や頒布、改変に関するこれらの条項と条件をすべて受け入れたことを示す」と規定している。
しかし、著作権法では、他人の作ったプログラムを複製しようとした場合は複製権が、改変しようとすれば二次的著作物を作成する権利(日本法でいう翻案権)が、さらに頒布しようとすれば頒布権(日本法でいう譲渡権)でそれぞれ制限される。つまり、下図で複製入手者Bは、原著作者Aの許諾を得ない限り、それらの行為を行うと著作権法を侵害したことになる。
そのためGPL第5条には前述の文に続いて、「しかし、あなたに、本プログラムまたは本プログラムの二次的著作物を改変または再頒布する許可を与えるのは、本ライセンス以外にはありません。これらの行為は、あなたが本ライセンスを受け入れないのであれば禁止されます」と規定しているのである。
つまり、「著作権侵害になりたくなければGPLを受け入れろ」ということになる。ここで別の問題が浮かび上がってくることになる。GPLはライセンスなのか(ライセンスの)契約なのかということだ。この違いは大きい。
岡村氏は、すべての条項を著作権法理だけで説明するには無理があるとしながらも「著作権侵害成立の回避をGPL適用のトリガとするのであれば、そもそもGPLは著作権法理を中心に構成すべきではないか」と話す。また、FSFの弁護士であるエベン・モグレン氏が「(GPLは)契約ではなくライセンスである」と明言していることを挙げ、GPLは「各条項の順守を条件とする一方的な許諾宣言」であると見解を述べている。
「とはいえ、日本では著作者人格権や公衆送信権などとの整合性も考えれば、ライセンスであるという考えはしっくりこないため、(GPLは)契約として捉えられることになるだろう」(岡村氏)
日本法では、プログラムの著作物にも著作者人格権が適用されるため、その改変には同一性保持権が、著作者の表示には氏名表示権との関係において、権利処理が問題となる。これらの権利は、米国生まれのGPLでは触れられていない。
では、GPLに違反すると何が起こるのだろうか?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証
- AD DSにSYSTEM権限取得の脆弱性 Microsoftが修正プログラムを配布
- .NETにサービス停止の脆弱性 広範なアプリケーションに影響
- Microsoft 365の新プラン「E7」は“AI盛り盛り”で99ドル E5にはない魅力は?
- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性
- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」
- ★4を目指すのは正解か? SCS評価制度が企業に突き付ける“本当の論点”
- 本職プログラマーから見た素人のバイブコーディングのリアル AIビジネス活用の現在地
- 偽のTeamsサポートで新型バックドアを設置 巧妙な手口に要注意
- データ激増時代に変化するIT部門の役割 データガバナンス実装の現実解
 「法律屋からするとストールマンのいうことはよく分かる」と岡村久道氏
「法律屋からするとストールマンのいうことはよく分かる」と岡村久道氏