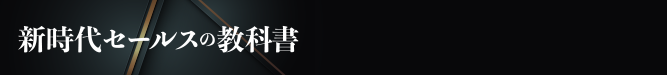「トップセールスに頼りすぎ」 駅で気絶するまで働いた元モーレツ営業マンが挑む、“営業プロセスの再構築”:ここが変だよ! 日本の営業(1/3 ページ)
「日本の営業は、トップセールスの一子相伝となっていることが多い。むしろ一子相伝されていればいい方で、なぜ売れているかの言語化もできないので再現性がない場合もあります」──そう話すのは、UNITE(東京都港区)の代表取締役社長、上田啓太さんだ。
UNITEは営業・マーケティング組織作りのコンサルティングなどを請け負う企業で、現在はインサイドセールス組織の立ち上げ・運用支援を主軸のサービスとしている。
上田さんが日本の営業組織の在り方に危機感を覚えたのには、きっかけがある。旧来型の営業組織で働いていた頃、働き過ぎて駅のホームで気絶するという壮絶な経験をしたことだ。それから8年ほどたった現在も、日本の営業組織の多くは、非合理的なままだと感じているという。
企業リストを基に片っ端から電話をかけ、展示会で多くの名刺を交換し、めぼしいビルの上から下まで往訪して名刺を渡し、夜は会食に行く──かつては当たり前だった営業の姿も、今は変わりつつある。しかし、まだまだ効率化や適切なデータの活用ができていない場面も多くある。
日本の営業は、今どのように変わるべきだろうか。話を聞いた。
「駅で立ったまま気絶し、倒れこんだ」
営業マンとしてのキャリアを歩んできた上田さんが倒れてしまったのは、2社目の企業に勤めていた時のことだ。
当時のスケジュールはハードだった。朝6時に出社し、朝礼で理念を唱和したのち、7時からミーティングを実施。ミーティングでは、営業状況について上司から詰められることが多かった。市場調査を終えたあと、ひたすら電話をかける。商談で外出する際以外は電話をかけ、200件かけて結果が出なければ300件かける、という状態だった。
どこに架電し、どういった結果だったかは記録していなかった。「そんな暇があるなら、もっと多く電話をかけねば」という方針だったという。
架電する時間が終わり、夜になると訪問先の社長に直筆で手紙を書き、上司と深夜までミーティングする。
「日々業務をこなすのに精いっぱいでした。疲労が積み重なって、2013年の冬に駅のホームで垂直に立ったまま、気絶したんです。幸い線路には落ちなくて済んだのですが……。この経験から、自分のキャリアや人生について考えるようになりました」
その後、この働き方を続けるのは難しいと考え、プルデンシャル生命に転職。同社は個人事業主として営業のプロフェッショナルが集まる組織で、保険の大切さを顧客に伝え、購買につなげるまでのプロセスがきっちりと設計されていた。
上田さんは、週2日程度プルデンシャルで保険を売りながら、残りの日々は自分の志を見つける活動に費やした。スタートアップ企業の支援イベントなどを開催する中で、あるとき、スマートキャンプ社長(現会長)の古橋智史氏と意気投合し、転職した。
SaaS比較サイトの「BOXIL SaaS」とインサイドセールス支援をする「BALES」の立ち上げ期を営業として支えた後、サロン予約アプリを手掛けるリクポで1年ほどCOOを経験し、19年にUNITEを立ち上げた。
関連記事
 マーケティング不在は“地獄”──リードを軽んじる企業が、インサイドセールスの立ち上げに失敗する理由
マーケティング不在は“地獄”──リードを軽んじる企業が、インサイドセールスの立ち上げに失敗する理由
コロナ禍をきっかけに、インサイドセールスを立ち上げる企業が増えた。その際、リードを獲得するマーケティング組織が充実していないと、失敗するという。その理由を、筆者の実体験をもとに解説する。 「売り上げが落ちてもいいから、残業をゼロにせよ。やり方は任せる」 社長の“突然の宣言”に、現場はどうしたのか
「売り上げが落ちてもいいから、残業をゼロにせよ。やり方は任せる」 社長の“突然の宣言”に、現場はどうしたのか
「来年度の目標は、残業時間ゼロ」──社長の突然の宣言は、まさに寝耳に水の出来事だった。準備期間は1カ月。取り組み方は、各部門に任せられた。現場はどう対応したのか? NEC、りそな、パーソル──“息切れしない”企業改革、大手3社に共通する「ヒト投資」
NEC、りそな、パーソル──“息切れしない”企業改革、大手3社に共通する「ヒト投資」
働き方改革、リモートワーク、DX化、インクルージョン&ダイバーシティ――変化の速い事業環境の中で、企業が取り組むべき課題は山積状態。疲弊して歩みを止めることなく、会社の活力を生み出すためにはどうすればいいのか。少なくない企業が、「ヒト投資」という答えに活路を見い出している。大手3社に、その施策を聞いた。 新卒応募が57人→2000人以上に! 土屋鞄“次世代人事”のSNS活用×ファン作り
新卒応募が57人→2000人以上に! 土屋鞄“次世代人事”のSNS活用×ファン作り
コロナ禍で採用活動に苦戦する企業も多い中、土屋鞄製造所の新卒採用が好調だ。2020年卒はたった57人の応募だったが、21年卒は2000人以上が応募と、エントリー数が約40倍に急増した。その秘訣を聞いた。 黒船来航! 「ゴロゴロしながら英語が学べる」アプリが、わずか7カ月で新規DL数を2.5倍に伸ばしたワケ
黒船来航! 「ゴロゴロしながら英語が学べる」アプリが、わずか7カ月で新規DL数を2.5倍に伸ばしたワケ
「ゴロゴロしながら英語が学べる」語学学習アプリ、Duollingo。世界で多くの人が活用しているが、日本版の担当者は1人のみ。2020年8月に着任した、Duolingo Japan Country Manager 水谷翔氏だ。そんな中でも、水谷氏が主導するマーケティング活動により、わずか7カ月で新規ダウンロード数は2.5倍に増えたという。詳しい話を聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング