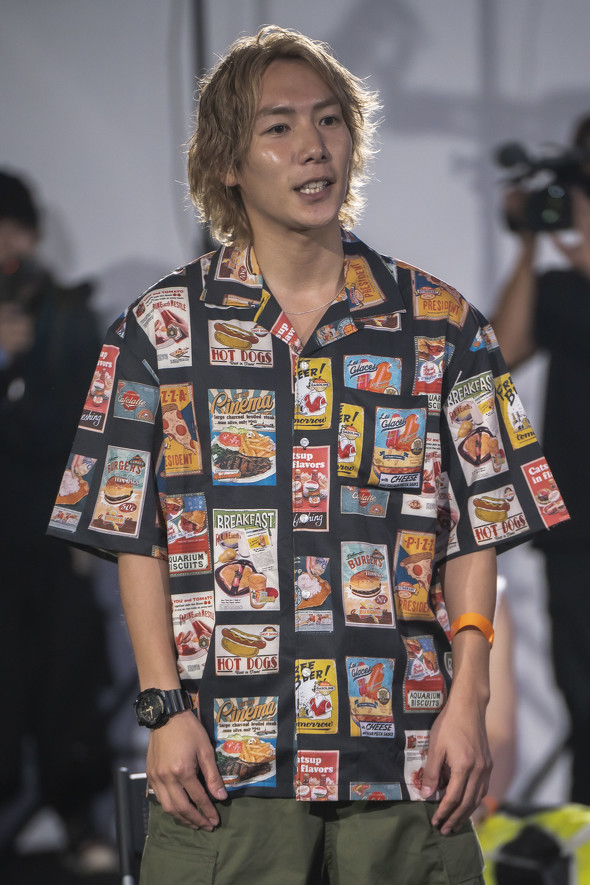朝倉未来プロデュースのBreakingDown6がバズった理由 過激化に必要なリスクマネジメント:ストーリー追求とのジレンマ(3/5 ページ)
“ほぼ格闘技のような感じ”という特性
なぜBreakingDownは多くの人に受け入れられたのか。これは人間の闘争本能による部分が大きいと思われる。その本能は、人より優れているところを見せて認めてもらいたい承認欲求に立脚していて、SNS時代が到来したことによって可視化されやすくなった。
素人の戦いであれ、プロの競技であれ、戦いには人間の闘争本能を刺激する面がある。まして、BreakingDownは基本的に素人の大会だ。「プロの戦いは遠い世界」と認識しているアマチュアも、「これなら俺でも参加できるかも」と思えるように設計してある。その証拠に、BreakingDown6への一般応募者は、過去最大の2000人に達した。
格闘家には経歴に傷のある選手も少なくない。そうした選手にとって格闘技は現実世界でセカンドチャンスを与えてくれる数少ない居場所でもある。朝倉未来、過去にはボクシングの辰吉丈一郎、海外ならマイク・タイソンなど枚挙にいとまがない。彼らが再び人生を成功させていく過程は共感を得やすいのだ。
朝倉未来もYUGOも、会見などで「ストーリー性」というキーワードを何度も発している。オーディションを利用し、ストーリー性を加味させることに秀でていて、その演出に視聴者は感情を移入するのだ。
だが、ここでBreakingDownはジレンマに陥る。ストーリー性を追求しすぎるとチープなエンタメになるからだ。一方で本格的な格闘技路線に振れば、RIZINやK-1と競合することになってしまう。かなり微妙な“さじ加減”を求められるのだ。
YUGOによると、第1回の大会から「一般人対プロ」「プロ対プロ」「1dayのトーナメント」などいろいろなパターンの試合を60以上にわたって試行し、1分1ラウンドの試合が面白いかどうかをずっと確認していたという。
BreakingDownはイベントとしての性格上、常に前回以上のものが求められる。それは企業が常に「前月比〇%増、前年比〇割アップ」などの成長を求められるのと同様だ。YUGOは以前のインタビューで「現在のフォーマットでやり続けたらそのうち飽きられるという課題感はある」と答えている。それゆえに6回目は新たに前田日明がプロデュースする総合格闘技大会「THE OUTSIDER」との対抗戦を打ち出した。
今後のBreakingDownにとっての切り札は、現在プロデュース側に回っている朝倉兄弟の参戦だろう。当人たちも前向きなコメントを発している。来年からこのフォーマットでの世界展開も予定していて、これが成功するかどうかも一つのカギとなる。
関連記事
 朝倉未来プロデュースの「BreakingDown6」、PPVチケット発売 会場は最高額100万円
朝倉未来プロデュースの「BreakingDown6」、PPVチケット発売 会場は最高額100万円
サイバーエージェントが運営する動画配信サービス「ABEMA」は、11月3日開催の「喧嘩(けんか)道 presents BreakingDown6」を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」で生中継する。 「年商1億円企業の社長」の給料はどれくらい?
「年商1億円企業の社長」の給料はどれくらい?
「年商1億円企業」の社長はどのくらいの給料をもらっているのか? 朝倉未来に聞く格闘技ビジネスの展望 「BreakingDownを世界一の団体にする」
朝倉未来に聞く格闘技ビジネスの展望 「BreakingDownを世界一の団体にする」
「1分1ラウンド」で最強を決める総合格闘技エンターテインメント「BreakingDown」。プロモートする朝倉未来さんは「世界一の団体にする」と意気込む。そのビジョンを本人に聞いた。 “1分間最強”を決める「BreakingDown5」 全21試合の対戦カードを発表
“1分間最強”を決める「BreakingDown5」 全21試合の対戦カードを発表
7月17日に開催する「喧嘩道 presents BreakingDown5」全21試合の対戦カードが発表された。今大会からは女性選手も登場させ、女性の視聴者も取り込む狙い。 朝倉未来がプロモートする「BreakingDown5」 格闘技ビジネスの構造を変えるか?
朝倉未来がプロモートする「BreakingDown5」 格闘技ビジネスの構造を変えるか?
朝倉未来さんがプロモートする「1分1ラウンド」で最強を決める総合格闘技エンターテインメント「BreakingDown」。その「BreakingDown」を運営する「バズるブランドを創る会社」レディオブック(東京都渋谷区)の代表取締役CEO・YUGOさんを新進気鋭の経済アナリスト、森永康平さんがインタビューした。 朝倉未来がプロモートするBreakingDown5.5、本日開催 DJ社長と10人ニキが激突
朝倉未来がプロモートするBreakingDown5.5、本日開催 DJ社長と10人ニキが激突
「BreakingDown5.5」が8月16日に開催。「朝倉未来YOUTUBEチャンネル」でもリアルタイムとアーカイブで動画配信する。「DJ社長vs. 10人ニキ」「こめおvs. 69ニキ」など注目の対戦カードをそろえた。 メイウェザーへの“花束投げ捨て”にRIZIN榊原代表が謝罪 「ごぼうの党」奥野代表が選ばれた経緯を聞いた
メイウェザーへの“花束投げ捨て”にRIZIN榊原代表が謝罪 「ごぼうの党」奥野代表が選ばれた経緯を聞いた
格闘技イベント「The Battle Cats presents 超(スーパー)RIZIN」(さいたまスーパーアリーナ)で、許されない非礼があった。フロイド・メイウェザーへの花束贈呈の場面で、「ごぼうの党」の奥野卓志代表が、花束を渡さずリングに落としたのだ。榊原信行代表に奥野代表が選ばれた経緯などを聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング