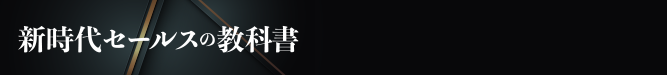LINEは営業の生産性が「10倍」に 日本企業がRevOps導入を成功させる方法は? NTTデータが解説:今すぐ取り組むべき、RevOpsのススメ(2/3 ページ)
日本企業のRevOps 「インサイドセールス」がカギ?
実現できると大きな価値を発揮するRevOpsですが、これまで解説してきた通り、組織・オペレーション・テクノロジー・データの統合に向けた壮大な取り組みとなるため、そもそもどこから着手すべきかの判断がつきづらい傾向にあります。
ここでは応用性を担保するために、RevOps実行への着手が最も困難なケースとして、伝統的なエンタープライズ企業かつ既に分業化が進んでいる状況を想定してご説明します。顧客対応をマーケティング・セールス・カスタマーサクセス(サポート)など複数の組織で分業しており、かつ各組織にオペレーション・テクノロジー・データがひも付き、大規模に分断しているケースです。
初めに結論から申し上げますが、RevOpsに取り組む上で一番に目を向けるべきは「顧客」です。
これまでご説明してきた通り、アフターデジタルな現代社会で「抜本的な収益・顧客体験価値の向上=LTVの最大化」を実現するためには、顧客の状態をリアルタイムに把握しながらパーソナライズ化した価値を届け続けることが必要不可欠です。
そして、RevOps実行に向けて最初に着手すべきことは、この「顧客の状態」をリアルタイムに把握することです。
「顧客の状態」とは、サービスを認知したばかりの状態から、サービスを利用中の状態へと遷移していくなかで、段階ごとに変化する顧客のニーズを表します。
この変化し続ける「顧客の状態」をマーケティング・セールス・カスタマーサクセス(サポート)間で把握・共有ができていれば、理想的な顧客体験に向けて各組織が協業しつつ成果につなげていくことができます。
日本企業はこれを実践し切れていないため、変化する顧客ニーズに対応できない、断絶したアプローチを各組織でそれぞれ繰り返し、収益・顧客体験に関する多大な機会損失を計上している状況です。
つまりRevOpsを実装する上でまず取り組むべきは、変化し続ける顧客ニーズを各組織がリアルタイムで正確に把握できるようになることです。
日本企業には「ボトムアップ型」が合っている
では次に、どの組織が主体となってRevOpsを実行すべきなのか、考えてみましょう。
RevOpsはこれまで解説してきた通り、組織・オペレーション・テクノロジー・データの統合に向けた非常に難易度の高い取り組みとなります。
RevOpsの取り組みが先行する米国では、全体最適化の指令塔として各組織を取りまとめる権限や予算を集約させたCRO(Chief Revenue Officer)やRevOps組織を設置した上で、各売り上げ組織を統率するような「トップダウン型のアプローチ」が主流となっています。
しかし日本の場合、トップダウン型のアプローチにトライするノウハウや予算、体制の確保が難しいのが実情です。
今回は日本企業が抱える制約下でもRevOpsを実行するための新たなアプローチである「ボトムアップ型のアプローチ」について考察していきたいと思います。
前提として、RevOps実行への着手が困難なよくあるケースとして、伝統的なエンタープライズB2B企業かつ、売り上げプロセスをマーケティング・フィールドセールス組織で分業しているようなケースを想定してみましょう。
まず、アプローチにおける二つの型(トップダウン型とボトムアップ型)の違いを明確にします。
トップダウン型
各売り上げ組織を統率するCROとその配下のRevOps組織がコントローラーとなることで、各売り上げ組織の活動をRevOps実行へと誘導
ボトムアップ型
理想的な顧客体験(顧客の状態・文脈に応じてパーソナライズされた体験)の提供を各売り上げ組織の共通目標として、マーケティング・フィールドセールス・カスタマーサクセスといった各営業組織が自律的に機能する仕組みを作る
「理想的な顧客体験」が提供できない要因として、部門間で変化する顧客ニーズの把握・共有ができていない以下のようなケースが挙げられます。
マーケティング目線
リードを獲得しても、フィールドセールスが多くのリードを放置するため、マーケティング施策の顧客反応がファクトベースで分からず、施策改善ができない。その割にフィールドセールスは「マーケティングの獲得したリードは商談にすらつながらない!」と机上の批判を繰り返す。
フィールドセールス目線
マーケティングから供給されたリードに対応しても、勉強目的で情報収集しているだけなど、商談にすらつながらないケースが多々ある。その割にマーケティングは「このリードはxxxセミナーに参加しているから受注確度が高いはず!」と机上の空論を繰り返す。
このような状況を踏まえボトムアップ型のアプローチについて、RevOps実装によってマーケティング・フィールドセールス機能がどのように変化するのか、顧客視点で整理したものが以下になります。
変化し続ける「顧客の状態」を、マーケティングとフィールドセールスの双方がリアルタイムに把握・共有できていれば、部門横断的な協力関係が必然的に生まれます。
これにより、マーケティング・フィールドセールスの分断された組織・プロセス・テクノロジー・データの統合が進み、まさにRevOpsの実行と同義な取り組みを実現できます。
そして、この2組織の中間に存在し、ボトムアップ型のRevOps実行の主体になる組織が「インサイドセールス」です。
インサイドセールスが独立した組織であったり、マーケティング組織傘下に存在したり、企業によって組織配置のパターンはあれど、重要なのはインサイドセールスが下記の役割を担うことです。
(1)非対面×デジタルで顧客対話が可能な立場から、変化し続ける顧客の本音を捕捉できる
(2)第三者的にマーケティングとフィールドセールスのオペレーション・テクノロジー・データをつなげる
こうした機能をインサイドセールスが果たせれば、RevOpsの実行に向けた流れをつくることができます。
つまり、インサイドセールスを従来通りのリードナーチャリング・クオリフィケーション(リードの育成と絞り込み)を行う部門として捉えるのでなく、「RevOpsを駆動させるインサイドセールス」として再定義するのです。
米国のようなトップダウン型でのRevOps実行が困難な日本企業においても、インサイドセールスに「抜本的な収益・顧客体験の向上を目的に各組織の活動を全体最適化する」というミッションを持たせることで、RevOps実行に向けたブレイクスルーにすることができるという仮説を構築しました。
そして、この仮説を立証するために、以下の強みをもつ3社でPoCを行いました。
NTTデータ
RevOpsに向けたコンサル及びテクノロジー×データのインテグレーション力
Magic Moment
RevOpsの実行を支援するSEP(Sales Engagement Platform)の開発・実装力
NTTデータ・スマートソーシング
テクノロジー活用含めた豊富なBPO実績に基づくインサイドセールスの実行力
具体的な内容としては、伝統的なエンタープライズ企業かつ既に分業化が進んでいる状況(RevOpsの着手が最も困難なケース)を想定し、SEPを活用した検証を実施しました。
結果、SEP活用だけで1.5倍の生産性向上が見込め、さらにSEP以外のテクノロジーやデータ(音声解析ツール、インテントデータ、生成AIなど)を活用することで10倍以上の生産性向上を目指すことができる見通しがついています。
加えて、インサイドセールスのオペレーションを起点に他部門の課題抽出・解決につなげられると確信を持つことができました。
以上のPoC結果をもって、RevOps実行への着手が最も困難なケース(伝統的なエンタープライズ企業かつ既に分業化が進んでいる状況)においても、この新たなアプローチを取り入れることで、日本企業が比較的容易にRevOpsを実行できる可能性を切り開くことができると考えています。
関連記事
 デジタル化の先に進めない日本企業 「RevOps」を阻む3つの壁とは?
デジタル化の先に進めない日本企業 「RevOps」を阻む3つの壁とは?
RevOpsが日本企業にも浸透し始めている。しかし、デジタル化の先に進めない日本企業が「RevOps」を実行するには、さまざまな障壁がある……。 「THE MODEL型」の弊害はAI活用にも 米国の営業組織が重要視する「RevOps」とは
「THE MODEL型」の弊害はAI活用にも 米国の営業組織が重要視する「RevOps」とは
AI活用が急速に進む中、注目度が高まるRevenue Operations。米国では注目度が高まっていますが、日本でも根付くのでしょうか? 案件減らし売上2倍に アドビの最強インサイドセールス部隊は、いかに大口受注を勝ち取るのか
案件減らし売上2倍に アドビの最強インサイドセールス部隊は、いかに大口受注を勝ち取るのか
アドビでは、約2年ほど前からBDRを強化している。明確に絞ったターゲット企業からの受注獲得に注力した結果、とあるチームでは≪案件数が半数以上に減少したにもかかわらず、受注金額が倍増≫した。インサイドセールスは「若手の登竜門」として新人が多く配置されるケースが多いが、同社のインサイドセールス組織は一味違うという。 「ソリューション営業」はもう古い! これからの時代に求められる「インサイト営業」の有効性
「ソリューション営業」はもう古い! これからの時代に求められる「インサイト営業」の有効性
日本では長年、ソリューション営業が正義とされ、課題解決型の営業アプローチが求められてきました。一方昨今米国では、市場動向や顧客状況の力学に迅速に適応し、顧客が自覚をもしていない未知のニーズを解き明かす「インサイト営業(Insight Selling)」が新たな営業スタイルとして注目を集めています。日本で正攻法とされていたソリューション営業は限界を迎えているのです。 シンプル・イズ・ベスト Sansanがたどり着いたインサイドセールスの最適解とは?
シンプル・イズ・ベスト Sansanがたどり着いたインサイドセールスの最適解とは?
Sansanのインサイドセールス部門が2023年12月に大幅な組織改革を実施した。顧客の従業員規模をベースにした「シンプル」で「分かりやすい」組織にしたという。組織体制を変更し、どのような変化があったのか。 2年分のアポをたった半年で獲得、なぜ? TOPPANデジタルのインサイドセールス改革
2年分のアポをたった半年で獲得、なぜ? TOPPANデジタルのインサイドセールス改革
 リードの40%が商談化するインサイドセールス「BDR」の立ち上げ方 8STEPをじっくり解説
リードの40%が商談化するインサイドセールス「BDR」の立ち上げ方 8STEPをじっくり解説
 採れない、育たない、続かない……データから読み解くインサイドセールスの深刻な課題
採れない、育たない、続かない……データから読み解くインサイドセールスの深刻な課題
「転職者が相次いで人手が足りない」「せっかく人材を確保できても、戦力になるまでに時間がかかってしまう」……インサイドセールスでは、長年深刻な人手不足が続いています。今回の記事では、さまざまな企業が公表しているインサイドセールスに関する調査データを紹介しながら、この業種の抱える構造的な課題について触れていきます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング