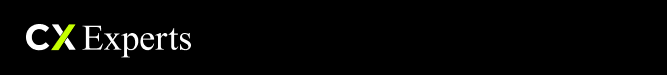コース料理込みで2万4800円! エンタメの常識を覆す「没入型コンテンツ」のすごさとは:廣瀬涼「エンタメビジネス研究所」(2/4 ページ)
参加者が演じる 「圧倒的当事者意識」が魅力の『真夜中の晩餐会』
この圧倒的没入体験から1年、新演目『真夜中の晩餐会〜Secret of Gilbert's Castle』が4月25日からスタート。筆者もメディア取材会に招待され、体験してきた。
『真夜中の晩餐会』は、1800年代ヨーロッパの貴族邸宅と麓町を舞台にしたイマーシブ体験である。参加者一人一人に設定が与えられ、現代人としてではなく、物語世界の登場人物の友人など、その時代の一員として没入する。
視点によって異なる物語が立ち上がる構造が魅力の一つである。また、参加者ごとに全く異なる体験が用意されており、一人一人が“別の景色”を目撃することになる。シャーロックが「圧倒的に置いてけぼり」ならば、真夜中の晩餐会は「圧倒的な当事者意識」だ。
まず驚いたのがその世界観へ体験者を導入する仕方だ。物語のプロローグを含むプレショーを参加者が見終わると、暗く無機質な通路を歩かされる。この時点で、何か嫌なことが始まるのではないかという漠然とした不安が広がる。
そして森を抜けた先に、信じがたい光景が広がっていた――洋館だ。まるで映画のワンシーンのように、迷い込んだ森の先に突如として現れる館。その光景に思わず現実感を失い、ここが本当に屋内の施設であることを忘れそうになる。この空間の作り込みが、まさにイマーシブ体験の真骨頂だ。
洋館へとたどり着いたと思ったのもつかの間、筆者を含む数人のゲストはまず麓町へと導かれた。これは単なる導入ではなく、「晩餐会の準備ができていない」という物語上の理由をもって町を探索するよう促される演出だ。この手法によって、体験者は能動的にストーリーに関わり、自分自身の立ち位置を実感していく。
筆者は、アトラクションの参加者としてこの麓町に初めて足を踏み入れたと同時に、物語の登場人物としてもこの場所を“初めて訪れた者”として演じていた。この「現実の初体験」と「物語上の初登場」が重なる構造が、街のリアルな作り込みに対する体験者としての没入感と、晩餐会の開始を待つ登場人物としての感情移入を同時に喚起し、物語世界へのより深い没入感を生み出していた。
ここで、特に印象に残ったシーンを紹介したい。
筆者は麓町で理髪店へと向かった。そこで筆者は椅子へと座らされ、顔にガーゼをかぶせられ、静かに問い詰められた。そして、首元に剃刀がそっと触れられる。その刃の冷たさは、筆者に「お台場にあるテーマパークに来ている」ということを忘れさせた。明確な殺意を持ってここに座らされている現状に対して、何とか命だけは助かりたいと、緊張の頂点へと追い詰められていた。
その感覚が、自然と筆者の口調を舞台俳優のように変えさせる。もはやただの観客ではない。物語の一部として、息遣いまでもが演技の一部になっていく。静寂が訪れ、刃が首元から離れる。その瞬間、自身の生唾を飲む音が響いたような気がした。背筋をつたう冷たい汗。目の前にいるのは俳優と自分だけ。他には誰もおらず、見物人もいない。それでも物語は進み続けていた。
その瞬間、自分の知らない場所でも他の体験者たちが、それぞれ異なる展開を迎えていることを意識させられた。同じ空間にいながら、誰一人として同じ物語を見ていない──それは非常に不思議な感覚であった。
体験者それぞれに異なる物語が用意され、誰も同じものを見ていない。筆者が体験したことを、別の体験者は知らない。それと同時に、筆者は別の場所で起こっている何かを知ることはできない。しかし、物語は確実に進んでいる──それを見ている人がいなくても、だ。スポットライトが当たらないだけで、それを俯瞰したとき、全てのキャラクターがそれぞれの生を歩み、それぞれの物語を持っているのだ。
このイマーシブ体験において、参加者は役を演じる当事者でありながら、同時に物語の目撃者でもある。舞台俳優のように物語の一部になりながら、客観的に見るリアルな視点も持ち合わせている。観客として、私はそのキャラクターの体験を目撃した唯一の存在だ。私だけが知る出来事があり、それは他の誰の記憶にも残らない。イマーシブシアターの本質とは、一つの固定されたストーリーを追うのではなく、無数の視点で紡がれる物語の断片を体験することなのかもしれない。
そしてこのアトラクションのメインともいえる晩餐では、パン、前菜、メイン、デザートと、まるで舞踏会の豪華な食卓そのもののような料理が提供される。テーマパークの食事とは思えないほど洗練されたビジュアルで、皿の上に広がる景色がその世界観をさらに確立させている。
食事が「演出」として溶け込んでいることこそ、この体験の特異な点だ。通常のテーマパークでの食事といえば、ショーを観ながら楽しむスタイルが一般的だ。しかし、ここでは逆だ。食事はあくまで「物語の一部」として存在し、それ自体が体験の重要な要素となる。つまり、晩餐会はただの補助的な要素ではなく、物語の構造そのものに組み込まれ、「この世界の住人として、その時間を生きている」ことを実感させられるのだ。
物語が幕を下ろし、洋館の扉を出たその瞬間、筆者は再び“イマーシブ・フォート東京”というテーマパークの一ゲストへと戻った。だが、足取りは決して軽くはなかった。物語が終わったことで、心にはぽっかりと穴が開いたような喪失感が残った。
『ザ・シャーロック』では、事件の真相を知るために登場人物のあとを追い、自ら動き回るという能動的な行為が、物語世界への没入を促していた。一方、『真夜中の晩餐会』においては、「自分」という観客のために物語に参与し、断片的に語られる物語の中に身を置き続けることで、知らず知らずのうちに深く世界観に引き込まれていく。つまり、前者が「物語を追う」ことで没入を成立させていたとすれば、後者では「物語に存在し続ける」こと自体が没入の核心となっていたといえる。
関連記事
 ディズニー・USJに見る「イマーシブ」活用術 “体験で売る時代”の勝ち手法は?
ディズニー・USJに見る「イマーシブ」活用術 “体験で売る時代”の勝ち手法は?
最近「イマ―シブ」という言葉が注目されている。この「没入体験」は、企業のプロモーションやブランディングを考える際のヒントになるかもしれない。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由
高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由
ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「え、久しぶりじゃん」 店員がタメ口の「友達カフェ」が、どんどん新しい客を呼び込めるワケ
「え、久しぶりじゃん」 店員がタメ口の「友達カフェ」が、どんどん新しい客を呼び込めるワケ
「え、久しぶりじゃん」「やっほー」――不思議なカフェが東京・原宿にオープンした。店員が全員タメ口で、友達を演じながら接客するのだ。「友達カフェ」の面白さは客がSNSに投稿する「口コミ」にもある。 営業マンからバリスタへ 68歳男性がスタバでフラペチーノを作る理由
営業マンからバリスタへ 68歳男性がスタバでフラペチーノを作る理由
スタバの象徴、緑のエプロンを身に付け、フラペチーノを作る「68歳」の児玉さん。バリスタとしてすべての業務を担当。かたくなに『バリスタはしない』と避けていました」と振り返るが……? 窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ
窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ
「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント
「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント
昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング