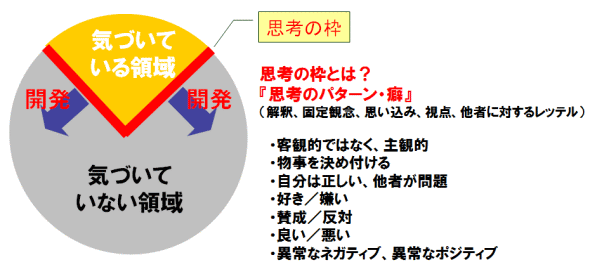職場を働きづらいものにする「思考の枠」という存在:成功するITマネージャーの「人づきあい術」
本連載ではプロジェクトチームを目標達成型の組織に成長させ、計画を着実に実践して成果を確実に得るために、ITマネージャーが果たすべき「行動」について解説していく。第1回目は生産性の低下をもたらす原因について考えてみたい。
受託開発の案件が減少しつつある今、IT業界のビジネスモデルは大きな転換点を迎えている。SIerやITベンダーのマネージャーの役割も「つくる」ことに専念できた幸せな時代から、新規開拓もしくは案件創出につながる営業的な役割がいっそう期待される時代になった。
一方、プロジェクト運営では少ないメンバーでこれまでと同じスピード感・品質を提供することが求められ、恒常的に人手不足を感じているITマネージャーは多い。本連載ではITマネージャーにメンバー個々人の生産性を高めるための土台づくりの方法をお伝えしていく。朝の出社が楽しくなる、そんなプロジェクトをつくるきっかけの一つしてもらえれば幸いである。
働きにくい職場になっていないか
短い納期、少ない人員、メンバーのスキルや経験不足など、プロジェクトに働きづらさを感じる要因を挙げればきりがない。それでもプロジェクト全体、メンバー個々人の生産性を上げたいと考えるのがITマネージャーだ。まずは何が生産性向上を妨げているのかを客観的に分析するチェックリストをご紹介したい。
このリストは、働きにくいプロジェクトにありがちな現象をまとめたものである。あなたのプロジェクトが働きやすいのか、働きにくいのかを診断するために、当てはまる項目をチェックしてみよう。
働きにくいプロジェクトの12の徴候
- ミスに対し、「自分は悪くない」と言い訳するメンバーが多い
- メンバーによって忙しさの度合いに、極端な差がある
- 定例の進捗会議以外、対面での会話がなく、コミュニケーションの大半をメールで済ませる
- プロジェクトリーダーが一人で昼食を取っていることが多い
- 昼食を固定のメンバーとしかとらない人が多い
- 朝のあいさつがない
- 「ありがとう」と言わない
- 他のメンバーがどんなプログラムの設計・開発をしているのか知らない
- 「難しい」「できない」「忙しい」がメンバーの口癖になっている
- 雑談がほとんどない
- プロジェクトリーダーが決めたスケジュール・仕様について、メンバーが調整・相談する余地がない
- プロジェクトリーダーが、メンバーの「やりがい」や「やる気」に関心を持っていない
どれくらい当てはまる項目があっただろうか。該当する項目が多ければ多いほど、そのプロジェクトは、働きにくい度合いが高いことになる。弊社の企業研修や公開セミナーに参加されたITマネージャーの平均数は4つである。
ただ、私はプロジェクトを取り巻く状況から察すると、「4」という数字は少ないのではないかと感じている。もし、メンバーにも同じ診断をやってもらったならば、もっと数字が大きくなるのではないか。
認識にギャップが生まれる理由
ITマネージャーとメンバーの認識にギャップが生まれる理由に、ITマネージャーが持つ「思考の枠」がある。働きやすいプロジェクトをつくっていく上で、ITマネージャーは自らの思考の枠を認識しなくてはいけない。
「思考の枠」とは、思い込みや固定観念、レッテルのことである。
(例)「これまでの方法で成功してきたんだから、これからも大丈夫だ。」
「うちのビジネスは○○企業が命だ!」
「彼は○○な人間だ!」
思考の枠が狭いと、人も組織も進化や成長を遂げることが難しくなり、変わることができなくなる。なぜなら、「これが絶対だ」「この他には正解はない」と思っている以上、進化や成長・変わる必要性を感じる余地がないからである。
一方で、思考の枠を広げることができれば、「今の方法は最適なのか」「他の方法はないだろうか」などと考えられるため、自分の問題点や解決策を模索できるようになり、人や組織の成功の可能性を広げられる。
思考の枠を広げる方法には2つある。1つ目は ITマネージャーとして、「自分のチェックした内容が本当に現状に即しているのだろうか、他に当てはまる項目はないのだろうか」と注意深く自問自答すること。2つ目は、メンバーの意見を聞いてみることである。思考の枠の存在に、独力で気づくのはなかなか難しい(だからこそ、思考の「枠」と呼ぶ)。そこで、メンバーからのフィードバックをもらうのである。
少し話が脇道にそれるが、営業などの他の職種に比べてITエンジニアの中には、思考の枠が極端に固い人がいる。他人からのフィードバックを受ける機会が少ないことが原因なのかもしれないが、本人はその思考の枠を「信念」と呼んだりする。そう言えば確かに聞こえはいいが、周囲からはなぜそのような考えを持っているのかまったく理解されていない。周囲から理解されないITエンジニアは孤立する。
特に業務部門など、技術的な部分で分かり合える土壌がないような相手からみれば、コミュニケーションを取りたくない人物の第一候補になってしまう。下手をすれば、「使えない人物」と評価されてしまう。そのくらい思考の枠が狭いことは、害を及ぼすものなのである。
話を「メンバーからのフィードバック」に戻すと、ITマネージャーとしてメンバーからのフィードバックを受けることは正直、気持ちのいいものではない。ついムッとしてしまったり、言い返したくなったりするだろう。しかし、ITマネージャーとして自分がどう感じるかよりも、メンバーがどのように感じているかを理解することが、働きやすいプロジェクトをつくる上でもっと大切である。
ITマネージャーは、リーダーとして次のような役割を担っている。弊社が親交を持つエグゼクティブコーチングの第一人者である世界の大企業の100人以上のCEOをコーチングした実績を持つ、マーシャル・ゴールドスミス氏の言葉をご紹介する。
『リーダーとは、他の人とともに目的達成に向けて進む人。「他の人とともに」という言葉が大事です。』
出典:マーシャル・ゴールドスミス【日経ビジネスアソシエ】(2008/12/16号)
まずはこの言葉を胸に刻み、リーダーとしてメンバー個々人の生産性が高まる、働きやすい環境をつくってほしい。そのためには、メンバーとともに「働きにくいプロジェクトの12の徴候」をチェックし、そのプロジェクトが「働きにくいプロジェクト」になってしまっている原因を突き止めることが不可欠だ。
そして、その兆候が一つでも少なくなるように、気を配り、改善に取り組むことが「働きやすいプロジェクト」をつくるITマネージャーとしての第一歩になる。特にメンバーが当てはまると指摘する項目については最優先で取り組むこと。その方が働きやすい環境をつくるため時間も短縮される。
今回は、プロジェクトの働きやすさを客観的に分析するためのチェックリスト、そして思考の枠の存在とその広げ方を紹介した。次回からは、「働きやすいプロジェクト」をつくるための具体的な方法をお伝えする。
執筆者プロフィール
青木裕(あおき ゆう)、ビジネスコーチ株式会社執行役員 ビジネスコーチ アジア 取締役。SIerにてプロジェクト運営にコーチングを導入。常駐先で運営手法が評価を得て、コーチング研修を実施。2006年、ビジネスコーチ株式会社に参画。2010年より現職。本連載記事を再編集した電子書籍「成功するITマネージャーの『人づきあい術』」が主要電子書店で入手可能です。
関連記事
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?