〜第2回 eビジネスのヒントは“開き直り”にある〜:特別連載:ITアナリストに聞け!梅山貴彦の「eビジネス展望」
<今回の内容>
■新しい業態に変化しやすいのはどの産業か?
■一例として、銀行の進化を考えてみる
■特許侵害を恐れてはいけない
■変革の材料として、「融合化」を考えてみる
■eビジネス推進者に求められるもの
これからの10年は、とにかく変革の年である。いままでやってきたもの、正しいと思っていたものを一度捨ててみる10年といっていい。仕事を進めてきて、事業を推進してきて、これが成功要因だと思っているものを捨てるところから、新しい未来が開ける。もう十分バラ色の未来が開けている人も、大切だと思っているものを捨ててみるとさらに良くなるかもしれない。
新しい業態に変化しやすいのはどの産業か?
その変革を進める要素の1つが、企業内のホワイトカラーの人々である。eビジネスにおける産業別の効率化は、管理職、財務・会計などや販売・営業職のホワイトカラーが基準になると設定すると、その割合が多いほど効率化が図れると考えられる。
つまり、金融・保険業、公共サービス、不動産業、卸売業、小売業、通信業、企業サービスなどが、新しい業態に変化しやすいといえる。図1に表されている数字は、企画、人事、財務、研究開発などのホワイトカラーと、販売する人を合わせた数を全就業人口で割った比率である。
しかし、これらの数値はあくまで可能性である。いくら金融・保険業の指数が99ポイントで、ホワイトカラー率が高く、IT化も進んでいるからといっても、現時点で華々しい状況にあるといっているのではない。現状は、合併などによって大量の不良債権を処理し、現在の事業の範囲内で再生を図ろうとしている。それが悪いといっているわけではないが、その状態はあくまで事業継続であって進化ではない。
一例として、銀行の進化を考えてみる
例えば、銀行にはどのような進化があるのか、少し考えてみることにする。A銀行という金融機関が、企業における貸し付け、資金回収、事業保険、財務コンサルティング、人事・総務コンサルティング、給与・退職金準備金、財務ASPなどの事業サービスを一手に引き受ける事業を始めたと仮定しよう。
そこで、自動車業界のeマーケットプレイス内における数社の資金調達と資金回収を、A銀行が一手に引き受けたとすると、これが新しい事業となる。もちろん、一手に引き受ける企業数社に対する、しっかりとした信用調査は必要であるが。
それらの企業の1つに、モバイル・インターネットを利用したナビゲーション・システムを販売するS電機があり、A銀行は、この企業に1000億円の貸し付けを行ったとする。これにより、S電機の負債の99%はA銀行が肩代わりすることになる。
S電機は、B自動車から、新車へのナビゲーション・システム搭載の注文をすでに受けており、これが月平均で約10億円の売り上げとなっている。通常であれば、この代金はS電機に支払われるはずであるが、B自動車は、これをA銀行に支払う。これによってS電機の一本化された負債額から、ひとまず当月の売り上げ10億円が差し引かれるのである。そうすると負債額が990億円になる。
しかし、このままでは、従業員に給与も支払えないし、当然仕入れ先の部品会社などから請求もくる。そこで、その支払いは契約借入金の範囲から自動的に処理される。社員の給与1億円、仕入れ部品代2億円などの支払い用に自動的に貸し付けが行われ、さらに、A銀行の統制サービスと資金調達サービスの審査により、当月の必要資金1億円がS電機に貸し付けされる。これで、借入金が994億円となる。
この一連のサービスによって、A銀行は、総合的な金融サービスと自動車業界のeマーケットプレイスにおいて統率力を発揮することになる。通常の金利収入に加えて、保険事業、社債発行などの証券事業や財務コンサルティング、調達手数料などによって収益面で拡大するのである。
S電機は、資金調達と資金回収の煩わしさから解放され、さらに明確な金融面での安定性と開示性を示し、株式公開企業にとっては有効なIR戦略となる。A銀行にとっては、S電機の経営状態を把握することにより、ここにさらに保険サービス、企業年金サービス、401k、社債などのコンサルティングを導入し、次々と業態を拡大していくことになる。
確かに規制緩和の問題などもあるが、できることから始めなくてはならない。規制緩和にしても、企業買収か合併により解決できるものもあるだろう。
特許侵害を恐れてはいけない
こうしたビジネスモデルはどこかで、すでに実施されているのではないか、ビジネスモデル特許に引っかかるのではないか、といった心配をすることも多いかもしれない。確かに、例に挙げたような金融サービスは、まったく同じではないが、ヒントになるサービスを提供する企業は存在している。しかし、そのようなことを恐れていてはいけない。
特許とは、それ自体でもうけるためではなく、発明者の権利を守りつつ、より多くの人に使用されることが目的でできたものである。変化や進化を望むものは、ビジネスモデル特許料のことなど、いったん忘れなくてはならない。
もともと日本人は加工や改良がうまい。それが最近は、著作権を盾になぜか改良発明が進んでいないような気がする。日本人はもっとまねをすべきである。発明者へのライセンス料の支払いなど気にしてはいけない。良いものができ、事業化できれば、相互に利益が生まれる方法が必ずあるはずである。
ライセンス料を支払ったとしても、ニュー・エコノミーは生まれる。独創性に過剰にこだわってはいけない。中国や台湾、香港などアジアの最近のパワーは、安い労働力からのみ発生しているのではなく、どんどん良いものを取り入れることで拡大しているのだ。日本が戦後急速に復興したのも、模倣や加工からである。知の技術もまねて、加工して広げていけばいい。
公共サービスでいえば、病院が入院患者向けのポータルサイトや、自宅療養患者へのサービスなど。不動産業では、個人ローンサービスとクレジットカードを組み合わせた事業展開。卸売業、小売業は、それぞれの業者でeマーケットプレイスをつくり、そのインフラを携帯電話通信業者が提供するなど、さまざまなものが検討できる。
企業サービスでは、財務から法務、人事まで、すべてのバックオフィス業務を代行してくれるeマーケットプレイスなど。こういったものが、eビジネスにおいては、実現可能となっている。
話がだいぶそれてしまったが、あらゆる産業は、変革の可能性を秘めている。とにかく冒頭にも述べたように、まずは変化を考えてみることである。
変革の材料として、「融合化」を考えてみる
もう1つのニュー・エコノミーへの変革の材料は、融合化である。eビジネスにおける融合化は、企業内から外に向けて組織や人材が移管・流動し、そこで別の組織と融合して、新種(ハイブリッド)の組織体となることである。
そこで、融合化しやすい組織・人材は? と考えると、まず出てくるのは管理・統制者である。つまり、社長、本部長、部長といったマネジメントをしている人間である。人の管理というものは、産業や業種をそれほど問うものではないはずである。優秀なマネージャは、どんな産業に行っても優秀なはずである。
ピーター・ドラッカーは『[新訳]経営者の条件』(P・F・ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社刊)で、「ほかの人間をマネジメントできるなどということは、証明されていない。しかし、自らをマネジメントすることは、常に可能である。そもそも、自分をマネジメントできない者が、部下や同僚をマネジメントできるはずがない。」と述べている。
マネージャの仕事とは、企業の方向性を理解し、部下の力を把握して、会社の方向性に沿って、最大限の成果を導き出すことである。つまり、どの業種においてもマネージャに求められる資質には変わりがない。こうした資質はさておき、業種に依存しないという点では、インターネットやeビジネスなどのITを駆使できるマネージャがどのくらい社内にいるか、というのが1つの基準になる。
その次に融合化しやすい人材が、事務・財務である。こちらも業種を越えて、人事や経理会計業務はどの業界でも必要である。技術的・専門的な知識を有する人材は、研究者や教育者などで一見、業種が偏っているようなところもあるが、「一芸に秀でるものは、多芸に通ずる」である。
そのほかの業務では、「インフラ」とは通信や運輸の仕事をする人、「原材料」は鉱業や農業などといった仕事をする人、「製造」は直接ものをつくっている人、「販売」は販売する人、「サービス」は、清掃業やホテルやレストランでの接客業などのサービスに従事する人などである。
ニュー・エコノミー組織のための融合化において、これら8つの業務の適合性はどのくらいなのだろうか。大胆にも評価基準を5段階評価で作成してみた。管理・統制は5点、事務・財務は4点、技術・専門は4点、インフラは3点、原材料は1点、製造は2点、販売は3点、サービスは3点と単純に点数化し、それを就業人口の割合にかけて融合化基準として指数化している。
そうすると図3のようになる。金融・保険業(81)や不動産業(78)、公共サービス(77)、通信業(75)、卸売業(75)などで、融合化指数が高くなっている。どこまで異業種や川上、川下産業に対して融合化できるのかがカギとなり、難なく吸収・合併・買収ができてこそ、ニュー・エコノミー企業といえる。
eビジネス推進者に求められるもの
先ほど、管理者の話をしたが、ECRで2001年2月に「eビジネスの推進者は、誰か」というWebによるアンケート調査を実施した。その結果が図4である。
案外、淋しい結果となった。155人の回答のうち、自社がeビジネスに取り組んでいると答えた人の割合は66.4%にのぼった。この数字からみて、回答者はどちらかというと先進企業の集団といえるだろう。
にもかかわらず、「eビジネスの推進者は、誰か」という問いに「社長、経営者」と答えたのは、24.5%にとどまっている。逆に「わからない、無回答」が41.3%を占めている。これで本当に国際競争に勝っていけるのだろうか。
経営者が、eビジネスを実験的なものと見ている間は、だめである。本気になって、腹を据えてかからねば、変革やニュー・エコノミーは夢物語である。この原因の1つに、eビジネスをニュー・テクノロジと錯覚している部分がある。図5は、産業構造での融合ポイントである。
自分の周りに存在する川上産業や顧客を考えてほしい。eビジネスは未知の買い手と売り手を瞬時に結ぶものである。この接点すべてに融合ポイントが存在すると考えたうえで、何ができるのかを、これまでの事業と比較してプロフェッショナルな経営者の視点でとらえてほしい。
経営者は、技術者ではないのは分かっている。技術を知ることは最重要項目ではない。ポイントは、技術は買ってくるもの、足りないものだけ開発する、まねをする。誤解しないでほしい。安易な発想ではなく、まねをして改良することが重要である。まね、組み合わせ、改良、これらを何度もやって、考え抜くということである。独自性にばかりこだわってもしかたがない。
日本人は、すべてといっていいほど、まねして、加工して、この2000年を過ごしてきたのだから、漢字だって、米作りだって、車だって、日本独自のものなど、ほとんどないような気もする。開き直りのパワーを持った、eビジネス推進者がいまこそ必要なのだ。
(第3回へつづく)
著者プロフィール
梅山貴彦
情報産業界で15年の経験を持つIT関連のアナリスト。IDC Japan株式会社では調査担当副社長を務め、eビジネス、インターネット、パソコン、PDA、コンシューマ機器、ネットワーク、コミュニケーションなどの調査分野を統括。2000年9月にイーシーリサーチ株式会社(以下ECR)を設立、代表取締役社長に就任。ECRでは、調査プログラム全体の設計や新しい概念の調査手法なども推進している
略歴
1986年2月 テクノシステム・リサーチ アシスタント・ディレクター
1989年11月 株式会社日立ハイソフト マーケティング部
1990年1月 株式会社日立製作所 パーソナルコンピュータ 商品企画部
1993年1月 IDC Japan株式会社 リサーチグループ シニアアナリスト
1997年5月 同社 調査担当副社長就任
2000年9月 イーシーリサーチ株式会社 代表取締役社長 & CEO就任
*ECRホームページ「e談話室」もご覧ください
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明
- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?
- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ
- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌
- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ
- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認
- 東海大学、ランサムウェア被害を報告 19万人超の個人情報が漏えい
- 保守の「脱・人月ビジネス」化は進むか それでも残る仕事は何か
- そのセキュリティ業務、自前と外注のどちらが正解? 勘に頼らない判断のこつ
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
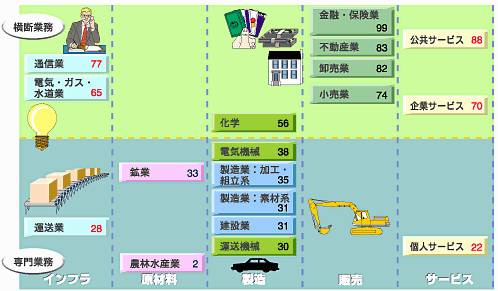 図1 産業別効率化の基準
図1 産業別効率化の基準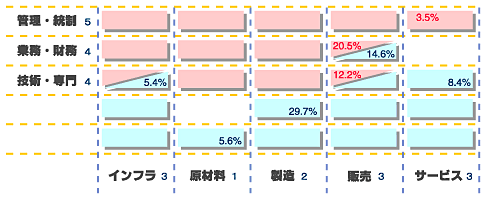 図2 融合化基準
図2 融合化基準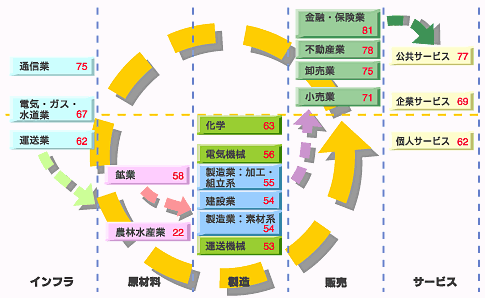 図3 産業別融合化基準
図3 産業別融合化基準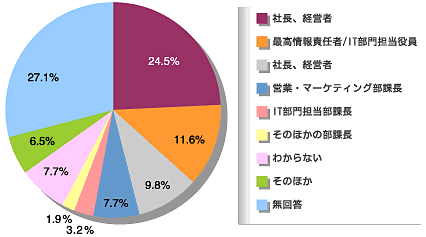 図4 eビジネスの推進者
図4 eビジネスの推進者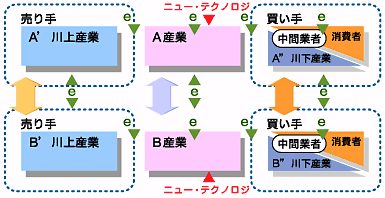 図5 産業構造での融合ポイント
図5 産業構造での融合ポイント
