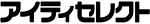CSRを分析すると見えてくる「日本的問題」:企業にはびこる「間違いだらけのIT経営」:第6回(2/2 ページ)
糸口を見せてくれる英国の取り組み
まず強制するものに、ソニーで導入した「内部通報」制度、あるいはアサヒビールやイオンなどが採用した取引先に資材の調達条件として法令順守などを課すものがある。
自覚を促すものとして、新手法のCSR状況を診断するソフトなどがある。
制度面では、環境マネジメントのように国際規格を制定する試み、松下電産が心理テストにCSR意識を取り入れて経営幹部登用に利用する制度などがある。
しかし以上の対策は、いずれも対症療法的である。対症療法も必要ではあるが、企業にCSRを根付かせるためには根本療法的な対策が求められる。
風土の改善はそれに近い。属人的組織風土の改善のためにその適切性と安全文化の成熟度を格付けして公表する機構の設置、モニター制の採用などを前出の岡本が提案している。
またCSRを重要視する英国では、社会問題の解決に企業は何ができるかと言う視点からCSRを始める。企業が地域社会に支えられていることを、社員が実際の貢献活動を通じて認識していくための体制が作られている。経営トップがホームレス生活者の現場を訪問する活動もあると言う(朝日新聞05年1月28日)。この辺に、根本療法の糸口の一つが見えてくる。
対策を考える時も、「建前・本音論」の観点から触れておかなければならない。
カントの純粋実践理性の「義務論」は、ただ単に義務のための義務を尽くすことを求めた。
近年では、米国の潮流としてロバート・ソロモンの「アリストテレスに還れ」がある。すなわち人間として自然に振舞う「関係の倫理」、すなわちアリストテレスの徳の倫理(徳のある人間になる)を主張する。そこから「人と人の関係を重視する」「人との約束だから重んじる」と言う考え方になる(南村博二著「私たちの企業倫理」創成社)。ここで、ドラッカーの「利益は結果であって目的ではない」「事業活動が目的である」が思い出される。
しかし、本音の視点から見たとき「義務論」や「関係の倫理」論は果たして企業の現場になじむのか。もし筆者が実務を経験する中でCSRの取り組みに矛盾を感じていなかったら、「義務論」や「関係の倫理」を現場になじむものとして素直に受け入れていただろう。
次回は、企業の現場の視点から見た本音の対策と、合わせてITの出番について考えたい。
関連記事
Copyright© 2010 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止
- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用
- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」
- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題
- 「欧州 AI法」がついに成立 罰金「50億円超」を回避するためのポイントは?
- 日本企業は従業員を“信頼しすぎ”? 情報漏えいのリスクと現状をProofpointが調査
- 「プロセスマイニング」が社内システムのポテンシャルを引き出す理由
- AWSリソースを保護するための5つのベストプラクティス CrowdStrikeが指南
- トレンドマイクロが推奨する、長期休暇前にすべきセキュリティ対策
- VMwareが「ESXi無償版」の提供を終了 移行先の有力候補は?