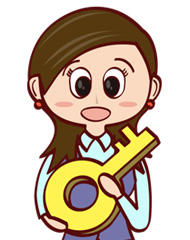最近よく聞く「SaaS」「クラウドコンピューティング」……正体は何なの?:キーワードで学ぶセキュリティの基礎
「レイコさん、SaaSとクラウドコンピューティングって何ですか?」「これはまた、かなりイマドキな単語ですこと」「雑誌でも今一番ホットなキーワードみたいに紹介してあって、だから私も興味を持ったんですけど……」
大手総合商社のメデア商事。入社2年目、総務部の山田カナは、昼休みに先輩の葛城レイコからITセキュリティの用語についてレクチャーを受けることになった。
カナ レイコさん、この間、カレの読んでる雑誌をチラッとのぞいてみたんですけど、分からない用語がバンバン出ていて、後でレイコさんに聞こうと思ってメモって来ちゃいました♪
レイコ はい、はい。で、聞きたいのは何?
カナ えっと、SaaSとクラウドコンピューティング。
レイコ これはまた、かなりイマドキな単語ですこと。
カナ 雑誌でも今一番ホットなキーワードみたいに紹介してあって、だから私も興味を持ったんです。
レイコ そう……。でも、この間教えた「Web 2.0」と同じで、さほど意味のあるキーワードだとは思わないけどなぁ。
カナ どういう意味ですか?
レイコ 「Web 2.0」ほどヒドくはないけど、技術用語というよりはマーケティング用語に近い感じ。既存のテクノロジーに敢えて新しい名称を付けることで、新技術というイメージを広めて、ビジネスに結びつけようっていう意図が強い気がするの。
カナ へぇ、そうなんですか。
レイコ 例えば、SaaS。これなんだと思う?
カナ どうしてもSARSウイルスしか頭に浮かばないんですけど(苦笑)
レイコ スペルが違うじゃない(笑)。SaaSは「Software as a Service」の略。ソフトウェアをパッケージとして売るんじゃなくて、サービスとして提供するってこと。
カナ う〜ん、何だかピンと来ないです……。
レイコ 普通、ビジネスで使うソフトってパッケージで購入してパソコンにインストールして使うでしょ? マイクロソフトのOfficeとか。
カナ そうですね。
レイコ でもSaaSは、ソフトをパソコンにインストールして使うんじゃなくて、その機能をインターネット経由で使うもので、料金はソフト代ではなく使用料の形で支払われることになるの。
カナ インターネット経由でソフトの機能を使うっていうと、Yahoo!のメールとかですか? ブラウザで使うやつ?
レイコ イメージとしては「Gmail」とか「Googleカレンダー」「Googleドキュメント」みたいな感じ。これらのサービスをGoogleではGoogleAppsと呼んでいるけど、いわばGoogleの用意したWebのプラットフォーム上で動作する“ソフトウェア”と呼べるかもしれないわね。Gmailで受け取ったWordファイルなどをGoogleドキュメントで表示できたり、お互いに連携するのもSaaS的な特徴かもしれないわ。
でも、さっきのYahoo!メールじゃないけど、Webメールなんて昔から当たり前のようにあったでしょ? で、そういうサービスを提供する事業者を「Application Service Provider」略してASPって呼んでたの。こちらもSaaSとは似てるけど、基本的にはひとつのサービスで完結していることが多いわね。はっきりとした境界線はないけど、プラットフォーム上で好きなソフトウェアを選べたり、それぞれが連携できたりするのがSaaS、ひとつのサービスで完結しているのがASP――って言えるかも。
カナ じゃあ「クラウドコンピューティング」って何なんですか?
レイコ これもSaaSとほぼ同じと思っていい。インターネット経由でサービスを提供するもの。うるさく言う人の中には「SaaSはクラウドコンピューティングの1要素に過ぎない」っていう人もいるけど。
カナ どういう意味ですか?
レイコ クラウドコンピューティングがインターネット経由で提供するサービスはソフトの機能以外にもいろいろあるってこと。だからクラウドコンピューティングの中でソフトの機能を提供するものをSaaSと呼ぶってことみたい。それにクラウドコンピューティングを強く提唱している人たちは「クラウド」という単語の意味を重要視してるみたいね。
カナ 紛らわしいです……。ちなみにクラウドって「雲」って意味ですよね?
レイコ そう、要は利用者がサーバを明確に意識しなくても、「もやもや」っとしたインターネット上の「サービス」だけを意識すればいいように構築されたサービス形態ってことらしい。
カナ わけ分かりません……。
レイコ まあ私もよく分からないからカナにとっても難しいかもね。SaaSにしろ、クラウドコンピューティングにしろ、言葉の意味よりもまずは使ってみることが重要なのかもしれないわ。
今日のまとめ
- SaaSは「Software as a Service」の略。ソフトの機能をインターネット経由の「サービス」の形態で提供するもの。
- クラウドコンピューティングとはサービスをインターネット経由で提供するもの。このうち、ソフトの機能を提供するサービスをSaaSと呼ぶ。
著者紹介 山賀正人(やまが・まさひと)
セキュリティ関連の話題を中心に執筆中のフリーライター。翻訳(英語、韓国語)やプログラミング、システム構築のコンサルなど活動は多岐に渡る。JPCERT/CC専門委員。Webサイトはこちら。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路
- NTTデータ、仮想化基盤「Prossione Virtualization 2.0」発表 日立との協業の狙いは
- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」
- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説
- Apple、「macOS」や「iOS」に影響するゼロデイ脆弱性を修正 悪用確認済み
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- Palo Alto Networks製品にDoS脆弱性 再起動やサービス停止の恐れ
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選