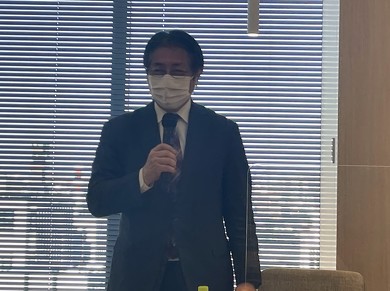インフレもたらしたサプライチェーン混乱は、ピークを超えた?(1/4 ページ)
原油高などに伴う値上げが国内でもニュースになっているが、世界でインフレといえば最も注目されるのが米国のインフレだ。11月10日に発表された10月米消費者物価指数(CPI)は前年同月比で6.2%と加速。エネルギーや食品を除いたコアCPIでも4.6%と上昇し、米国のインフレは加速している。
米国のインフレは遠い他国の話ではない。米国は世界最大の消費国であり、日本にとっても最大の輸出先だ。またインフレの状況によって米中央銀行にあたるFRBの政策が決まり、それは世界の経済に影響を与える。
インフレ加速は世界のエコノミストにとっても想定外だったようだ。三井住友DSアセットマネジメントの吉川雅幸チーフマクロストラテジストは、「みんなこんなにインフレが加速するとは思っていなかった。供給のボトルネックは想定外」と振り返る。
今回のインフレは、珍しい供給不足インフレ
インフレには原因によっていくつかの種類がある。景気が強く需要が大きくなることで起こるデマンドプル型インフレは、一般に良いインフレだと言われる。逆に、原材料高などを原因としたコストプッシュ型インフレは、悪いインフレの典型だ。インフレ期待が重なると、労働者は賃上げを求め、それに伴って企業は製品を値上げするというスパイラルに入るからだ。景気がよいわけではないので、スタグフレーションに入ってしまう危険がある。
しかし、吉川氏は「今回のインフレは珍しい供給不足インフレだ」と話す。これは供給される数量が絞られたことで価格が上昇する形のインフレだ。
コロナ禍が東南アジア諸国でまん延し、工場などが止まったことで、必要とされる部品が入ってこず、生産が遅れた。自動車などが典型的だが、ジャストインタイム方式が進み在庫を持たなくなった製造業では、グローバルなサプライチェーンの問題に弱い。
関連記事
 どうなるインフレ? 流動性相場はまだまだ続く
どうなるインフレ? 流動性相場はまだまだ続く
昨今インフレが話題だ。米国ではインフレ率が急上昇し、国内でも原油高資源高の影響やガソリンや日常食品などで値上げが続いている。コロナ禍からの経済回復がまだ完全ではないなか、インフレが襲うと、不況下で物価上昇が起きる「スタグフレーション」の声さえ聞かれる。 インフレが来る? 通貨からの逃避続く世界経済
インフレが来る? 通貨からの逃避続く世界経済
コロナ禍の拡大は続いているが、株式市場は好調を維持している。この背景には何があるのか。「貨幣からの逃避を垣間見た、それが今年のマーケットだった」。そう話すのは、フィデリティ投信のマクロストラテジスト重見吉徳氏だ。 インフレと金利と株式市場
インフレと金利と株式市場
製造業の急回復で銅などのコモディティ価格が上昇し始め、米国経済が正常化すれば労働力不足となり、インフレが起こりやすくなるのでは、といったことが心配されている。しかし、これらは株価下落をもたらすとは思えない。“経済回復・正常化”→モノの価格・賃金の上昇→インフレ懸念・金利上昇→“経済悪化・株価下落”という因果は、経済回復・正常化→経済悪化・株価下落であり、矛盾しているからだ。 石油価格上昇 インフレによるスタグフレーションの心配はない?
石油価格上昇 インフレによるスタグフレーションの心配はない?
昨今、原油価格の高騰などから、景気後退とインフレ(物価上昇)が同時に起こるスタグフレーションを警戒する声が聞かれる。1970年代のオイルショックの際には、景気後退で給料が上がらないにもかかわらず物価が上昇し、生活者にとって極めて厳しい状況となった。 コロナ後のインフレを考える
コロナ後のインフレを考える
エジンバラやロンドン拠点の株式・債券のファンドマネジャーから、これから5年程度の中長期で投資環境を考えるときには「世界的なインフレの可能性」を想定した方が良い、という話題が出された。後になって振り返ってみると転換点になっているかもしれない、ということだ。 理由は半導体だけではない 自動車メーカー軒並み減産と大恐慌のリスク
理由は半導体だけではない 自動車メーカー軒並み減産と大恐慌のリスク
7月から9月にかけて、各社とも工場の操業を停止せざるを得ないほどの減産を強いられた。この問題、本当に理由が中々報道されていないように思う。メディアの多くでは「半導体」が減産の原因だとされてきた。実際のところ、半導体そのものも理由の一部ではあるのだが、あくまでも一部でしかない。生産に大ブレーキをかけたのはもっとごく普通の部品である。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング