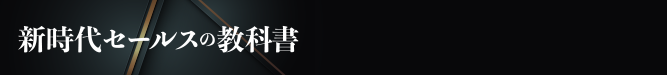「電話なんかで営業できるか」 富士通のインサイドセールス、逆風の中でどう成果を出したのか?:属人営業からの卒業〜「俺の顧客リスト」はもうダサい!〜(1/3 ページ)
日本企業の営業組織が変わり始めている。これまでスタンダードだった「属人営業」は、過去のやり方だという認識が強まってきた。
モノを売る提案から、SaaSなどのコトを売るソリューション提案への変化。営業活動を“勘や経験に頼らない”ための、デジタルツールやデータ活用の浸透──と、営業組織を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。
そして、コロナ禍による営業スタイルの変革が決定打となった。必然的に顧客先への訪問回数は減少し、従来手法の限界が露呈。しかし、古くから「俺の客意識」が強く、営業慣習が染みついている大企業では、大きな組織変革やデジタルツールの浸透は容易ではなかった。
そんな彼らのロールモデルとなり得るのが「富士通」だ。もちろん、同社の営業組織内でも「俺の客」という意識は強くあった。組織内のメンバーだとしても自身の手の内を明かしたくないという、典型的な「属人営業組織」だった。しかし、それでは刻一刻と変化する市場で競争力を保ち続けられない。
2020年にたった3人で発足したインサイドセールスは同年、営業と連携しながら合計600社1400部門にアプローチし、100件ほどの新規獲得、33件の受注という成果をたたき出した。
長年続いてきた「当たり前」を壊すのは一筋縄ではいかない。「反発しかなかった」状態から、どのようにインサイドセールスは組織の中で不可欠な存在に代わっていったのか? 富士通CRO室 Head of Deals Creation 友廣啓爾氏と、CRO室 Deals Creation シニアディレクター 及川美智代氏に話を聞いた。
説明は300回以上に 「お手並み拝見」「電話なんかで営業ができるか」
今でこそ社内でインサイドセールスの存在感は増してきたが、発足当初は懐疑的な見方が強かった。最初の3カ月は、経営層からプレイヤー層にまでインサイドセールスの意義や実現できることなどを説明して回る日々が続いた。
「説明する中で、どのレイヤーでも大企業あるあるの『俺の客に触るな』問題が一番意見として多く出ました。1人の営業が1社を長く担当している結果、そこに他の人間が介入することで案件が取られるのではないか、クレームにつながったらと懸念されていました」(友廣氏)
上層部には、THE MODELもインサイドセールスも知らない人もいた。現場のメンバーからは「電話でお客さまとの信頼関係が築けるわけがない。足を運んでなんぼ」という意見も当たり前のように出た。
説明の場を300回以上設けたが、ポジティブな意見はほとんどなかったという。「ただ、社内で説明を重ねたり、外部メディアなどを活用して発信したりする中で、若手営業社員から『富士通ってこんなこともやっているんだ』と興味を持ってもらえることはありました」(及川氏)
インサイドセールスは営業のバディであり、顧客を奪う存在ではない。潜在顧客のニーズを探り、確度の高いリードを発掘し営業につなぐという仕事を丁寧に説明した。結果、同年11月に22の営業部門でPoCをスタートさせることになった。
実施期間は約3カ月間。アプローチリストを一巡できる期間であることと、PoC止まりにせず早期に成果を証明したいという思いから設定した。営業部門からは「お手並み拝見だね」との発言もあったというが、3カ月という短い期間でどのように組織内に浸透させ、成果を出していったのか。
関連記事
 「営業から買う」は時代遅れ B2Bテック製品の購買ジャーニー、どう変化している?
「営業から買う」は時代遅れ B2Bテック製品の購買ジャーニー、どう変化している?
B2B営業の購買ジャーニーが変化してきている。これまで当たり前だった「営業から買う」というスタイルはすでに時代遅れになりつつある。なぜだろうか? 購買者の変化を踏まえ、今後の営業のあり方を考えてみよう。 ChatGPTが変える営業 「プロダクトセールス不要説」を唱える米国企業の意図とは?
ChatGPTが変える営業 「プロダクトセールス不要説」を唱える米国企業の意図とは?
ChatGPTは営業のあり方をどう変えるのか? ChatGPT誕生を受け、米国の企業では「プロダクトセールス不要説」が唱えられ始めている。一体どういうことなのかというと…… なぜ、日本企業の営業組織は「AI」と「データ」を正しく使えないのか?
なぜ、日本企業の営業組織は「AI」と「データ」を正しく使えないのか?
なぜ日本企業の営業組織は「AI」と「データ」を正しく使えないのか? 効果的な活用を阻む日本企業特有の課題と、解決策を前後編にわけて解説していきます。 ChatGPTが受注率も算出できる「良い営業データ」とは? AI時代のデータの作り方
ChatGPTが受注率も算出できる「良い営業データ」とは? AI時代のデータの作り方
AI時代に求められる「良い営業データ」とはどういうものでしょうか? 良い営業データとAIを組み合わせることで、さまざまな営業業務の自動化が可能になります。実際に良い営業データをChatGPTに入れてみたところ…… 米国で「営業マネジャー不要論」が話題 AIが代替できない「営業の仕事」はあるのか
米国で「営業マネジャー不要論」が話題 AIが代替できない「営業の仕事」はあるのか
「営業職はAIに代替されるのか」というテーマは、日本のみならず世界中で話題になっており、米国では「営業マネジャー不要論」が持ち上がっています。なぜ米国ではそのような議論に発展したのでしょうか? そのワケと日本企業への影響を解説していきます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング