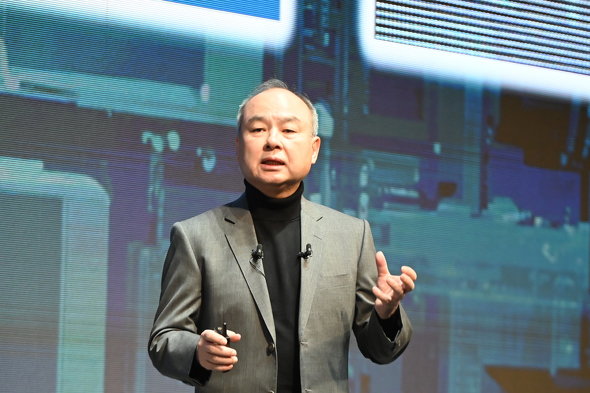孫正義が原点「無番地」で得た挑戦意欲 「人にはみな、夢を見る権利がある」:『志高く』(1)(1/2 ページ)
この記事は、井上篤夫氏の著書『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社文庫、2024年)に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。
孫正義には、いまでも夢に見る原風景がある。それは線路下のトンネルと、そこを駆け抜ける幼い自分の姿だ。
「いつも暗いトンネルが怖くて、通るとき、うわーんって泣いてたんです」
大声で泣きながら全速力で走って、声が涸れるころ、トンネルの先に光が広がってくる。明るい世界が開けている。
2020年10月、孫は生地である佐賀の当時住んでいた地域、トンネル、線路、川を訪ねた。3歳とか、5歳のころ、いとこや兄たちも通ったトンネルは、まだあった。大人になった自分が見てもけっこう長い。記憶にあるより出入口は狭く、一般車両は入れない。暗いトンネルを泣きながら通った感覚がいまでもまざまざとよみがえる。どきどきして、胸が締めつけられるような感じになる。
「でも、トンネルを抜けたときの喜びは、また何ともいえない虹のような世界なんです」
佐賀県鳥栖(とす)市五軒道路無番地。ここが孫の原点だ。
著者プロフィール:井上篤夫(いのうえ・あつお)
作家。1986年にビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)、テッド・ターナー(CNN創業者)を単独取材した。1987年、孫正義を初インタビュー、以来37年余にわたって密着取材を続けている。『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社)はベストセラーとなり、英語・韓国語に翻訳された。『志高く 孫正義正伝 完全版』(実業之日本社文庫)2010年オーディオブックアワード ビジネス書部門大賞受賞。『志高く 孫正義正伝 新版』(実業之日本社文庫)『事を成す 孫正義の30年ビジョン』(実業之日本社)『孫正義 事業家の精神』(日経BP)『とことん 孫正義物語』(フレーベル館)、『フルベッキ伝』(国書刊行会)は2023年日本英学史学会 豊田實賞を受賞。『ポリティカル・セックスアピール 米大統領とハリウッド』(新潮新書)『追憶 マリリン・モンロー』(集英社文庫) 『素晴らしき哉、フランク・キャプラ』(集英社新書)ほか。訳書に『マタ・ハリ伝 100年目の真実』(えにし書房)『今日という日は贈りもの』(角川文庫)『マリリン・モンロー 魂のかけら』(青幻舎)などがある。
父親から受けた「最強の教育」とは?
「国鉄の所有地でした。そこに不法侵入で、韓国から小さな漁船の底に隠れるようにして、おやじの両親なんかが渡ってきた」
食べるものがない。住む場所もない。日本語も分からない。だから、一からのスタートではない。ゼロにも達しない、マイナスからのスタートだった。
「無番地です。住むところもないホームレスが、番地のない場所にたどり着いた」
韓国から渡ってきた祖父たちは、トタン板を拾ってきて、雨風をしのぐバラックを建てた。集落は自然にできた。
無番地は住んではいけない場所だ。国鉄の職員などが、野焼きのように焼き払う。「せいせいした」と思ったかもしれない。だが、翌朝には元通りになっていた。また別のトタン板が張ってある。それを何度も繰り返すうちに、焼いても無駄だ、すぐまたよみがえると諦めた。
「勝手に住み着いた人たちです。逞しい。生存能力というか、踏まれても蹴られても、生きていくという意欲が強いんです」
生きるなと言われても、生きていかなければならない。
「おやじたちには、そういう逞しさがある。だから、ぼくはおやじのパート2で、ぼくが創業者というより、おやじが創業者のパート1です。映画『ゴッドファーザー』だったら、『ゴッドファーザーPART2』を見るほうが好きだ。父と子の物語を描いているから」
「おやじは最強の教育者です」
孫が小学1年生に上がった、6歳か7歳ぐらいから、父は母に厳命した。
「正義と呼び捨てにしてはいかん。正義さんと言え」
その後、母は常に「さんづけ」で呼んだ。
「6歳から正義さんですよ。母が尊敬を込めて接してくれるから、そういう立場の人間にならなきゃいけないと思った。いわば六つ子の魂」
それが父の帝王学だった。六歳の息子に、人々のために生きる心構えを教えた。
小学校1年生のときから、大人になったら何万人もの部下を持つ、そういう責任ある立場になると決めていた。だから、クラスで学級委員長を選ぶときにも、最初から自ら手を挙げて、「おれがやる」と立候補した。常に自分が先頭に立つ、そういう気概でいた。
父の教育方針に則(のっと)ったものだ。
「物の考え方を教わりました。だから、おやじからは褒められたことしかない。それはもう最強の教育だったと思います」
少年時代の孫は、なぜトンネルを抜けて行ったのか。
「トンネルの向こうに大木川(だいきがわ)という川がありました。おやじの一番末の弟を成憲(しげのり)と言うんですが、叔父だけど年が近いから、いとこのお兄さんみたいな感じ。いつもいっしょに遊んでくれて、そこにもいっしょに魚を捕りに行ってた」
大木川は九千部山(くせんぶさん、山頂からは北に博多湾、南に筑紫平野と有明海を望む、標高約848メートルの山)を源流に鳥栖市を貫いている。夏は子どもたちの水遊びの場だった。
孫は幼いころは、みんなが川で魚を捕る様子を見ているだけだったが、小学校の中学年になると一緒に川のなかに入った。網を川の端に据え、みんなと協力して魚を網に追い込む。ザリガニやドジョウが入ったりもするが、捕りたいのはハヤだ。きれいですばしこい魚で、体長は7センチから10センチぐらい。祖父の孫鐘慶(ソンジョンギョン)は川魚が好きだった。捕った魚を祖母の李元照(イウォンジョ)が佃煮や煮魚にする。
だが、祖父に食べてもらうという本来の目的は、孫少年の頭になかった。ひたすら魚を捕りたかった。毎日のように捕りに行った。
小学校のころには無番地から引っ越していたが、休日には父の兄弟姉妹、親戚らがみな集まって、祖父母といっしょに食事をするのが習慣だった。だから、毎週末と夏休みにはいつも大木川に行った。
「そのときに上手な魚の捕り方をいっぱい学んだ。夜の9時とか10時ぐらいに行くといい。夜ぼりというんですけどね。魚も眠いから、うまく脅かしたら、昼間よりたくさん捕れる。だから、いまでも川が大好きです」
真夏の夜の川。その光景が孫の脳裏に深く焼きついている。『ザ・フォール』などで知られる世界的な日本画家、千住博(せんじゅひろし)に屏風に描いてもらったほどだ。
当時は毎日が冒険だった。トンネルをくぐるだけでも冒険だった。夜ぼりで魚を捕るのは、もっとどきどきする冒険だ。
「ユニコーンたちに投資して、10年先のことを考えて心が高揚するのも、子どものときにトンネルを抜けて川に魚を捕りにいった感覚の延長線上にある。無番地で過ごしていたころに感じたどきどき感、わくわく感と、まるっきり同じ」]
関連記事
 孫正義「SBGを世界で最もAIを活用するグループに」 AGIは10年以内に実現
孫正義「SBGを世界で最もAIを活用するグループに」 AGIは10年以内に実現
ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長は10月4日、都内で開いた自社イベントに登壇し「SBGを世界で最もAIを活用するグループにしたい」と力説した。 NVIDIA製を“28倍”効率化 生成AI時代のゲームチェンジャー「サンバノバ」の正体
NVIDIA製を“28倍”効率化 生成AI時代のゲームチェンジャー「サンバノバ」の正体
米SambaNova Systemsは、AIに強いプロセッサーを開発しており、市場の大部分を占めるNVIDIA製のチップに代わるものとして期待が集まっている。同製品を28倍、効率化したと称するサンバノバ共同創業者のロドリゴ・リアンCEOにインタビューした。 孫正義の「先を見通す力」とは? ソフトバンク・ビジョン・ファンド“参謀長”明かす
孫正義の「先を見通す力」とは? ソフトバンク・ビジョン・ファンド“参謀長”明かす
ソフトバンク・ビジョン・ファンドで「参謀長」と呼ばれている佐々木陽介さん。孫正義氏の先を見通す力や卓越した判断を見る機会もあったという。日本のスタートアップ市場に未来はないのか。佐々木さんに話を聞くと、一味違った日本の将来図が見えてきた。 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング