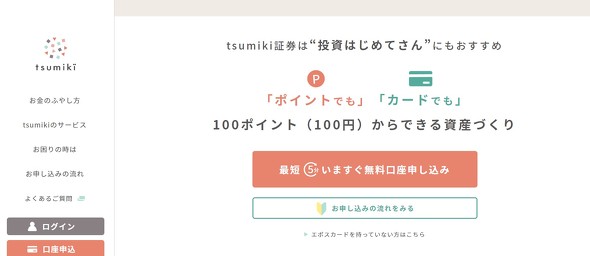日ハム、JAL……他業種の「銀行サービス」参入が加速 一方「証券サービス」は鈍化、なぜ?:古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」
近年、銀行業界への異業種参入、いわゆるBaaS(Banking as a Service)が盛り上がっている。かつてはプレーヤーに数えられるのは伝統的な銀行のみだった業界だが、フィンテックの台頭や規制緩和の波を受けて、異業種からの進出が顕著になっている。
楽天銀行のソリューションを活用することで、預金額に応じて運賃の割引を受けられる新しい銀行サービスを提供する「JRE銀行」の事例が記憶に新しい。当日は申し込みが殺到し、口座開設案内のメールの配送遅延が発生するほどの人気ぶりだった。
同様に、住信SBIネット銀行も「NEOBANK」というブランドでJALペイメント・ポートやヤマダデンキ、北海道日本ハムファイターズの興行業務を行うファイターズ スポーツ&エンターテイメントといった異業種からの銀行業参入をサポートしており、銀行業務のサービス化が止まらない勢いだ。新規参入者に対する規制が緩和されることで、従来の銀行業務にとらわれない新しいビジネスモデルを持つ企業が、テクノロジーの力を借りて参入可能な土壌が整っている。
2010年代中盤ごろから注目されてきた「フィンテック」は、直近の円安や金利上昇といった経済動向への関心の高まりも相まって、ようやく本格的な普及期に入っている。最新のテクノロジーを駆使して効率的な金融サービスを提供することで、異業種からの参入者は従来の銀行業務と差別化を図り、顧客に新しい価値を提供できる可能性が高まっている。
一方、証券業への異業種参入は下火──原因は?
一方、証券業界への異業種参入は停滞している。目立った例といえば、2018年の丸井グループによるtsumiki証券と、2023年のドコモのマネックス証券買収くらいだ。日経平均株価が一時バブル期のピークを超え、現在も高水準を維持しているにもかかわらず、異業種の証券業参入は下火になっている。
背景には、証券業界特有の市場環境や規制、新NISA(少額投資非課税制度)の影響がある。新NISAの導入により、個人投資家の投資枠が最大1800万円に拡大された。これにより、多くの個人投資家が証券会社の収益の柱であった取引手数料を払わずに済むようになり、証券業界全体の手数料収入が減少している。
証券会社はかつて、NISA口座の売買手数料を無料にすることで顧客を引き込み、そこから特定口座や信用取引に移行させることで収益を確保していた。しかし、新NISA制度により、ほとんどの顧客が手数料のかからないNISA口座で資産形成を完了するようになり、収益の確保が難しくなっている。
また、手数料無料化の流れも証券業界への新規参入を阻む要因となっている。米国の大手証券会社チャールズ・シュワブが株取引の手数料を無料化したことを皮切りに、日本でもSBI証券や楽天証券が株式の売買手数料を無料化した。これにより、従来のビジネスモデルが通用しなくなり、新規参入者は新たな収益モデルを構築する必要がある。
さらに、日本の証券市場はすでに成熟しており、主要なプレーヤーが確立されているため、新規参入者が市場シェアを獲得するのは非常に難しい状況である。既存の大手証券会社は長年の経験と豊富なリソースを持ち、強力な競争力を誇っているため、新規参入者がこれらの企業と競争するのは容易ではない。
NISA口座は一つの証券会社しか保有できないため、取扱商品が充実している大手の証券会社に投資資金を集中させる動きが生まれ、新規参入の壁を一層高めている。
また、少額投資サービスの展望も厳しい。かつて注目を集めた「100円投資」のような少額投資サービスは、新NISAの一般化に伴い、投資信託の普及と投資単価の低下を招き、付加価値を提供しにくくなっている。少額投資は投資額が小さいため、証券会社にとって収益性が低く、コストがかさむ。
このように、日本の金融業界では銀行業界への異業種参入が進む一方で、証券業界への異業種参入は停滞している。背景には、各業界特有の市場環境や規制、新NISAの影響がある。銀行業界は安定した収益モデルや規制緩和、フィンテックの進展により、異業種参入が容易になっている一方で、証券業界は個人投資家のための制度がむしろ業界の疲弊を招いている。
証券会社が生き残るためには、取引手数料に依存せず、信用取引などの金利収入を多く負担する大口顧客の囲い込みや、投資信託の組成といった安定した収益源の確保が重要だ。証券会社はデジタル技術を活用した新たなサービスの提供や、顧客教育の強化を通じて、価値あるサービスを提供し続けることが求められる。これにより、競争の激しい市場環境でも持続的な成長を実現できるだろう。
銀行と証券のサービス化は、低金利環境が続く中で、各社が新たな収益源を模索し、顧客に柔軟なサービスを提供するための鍵となる。日本の金融業界は大きな変革期を迎えており、デジタル技術を活用したイノベーションが、その未来を形作る重要な要素となるだろう。
筆者プロフィール:古田拓也 カンバンクラウドCEO
1級FP技能士・FP技能士センター正会員。中央大学卒業後、フィンテックベンチャーにて証券会社の設立や事業会社向けサービス構築を手がけたのち、2022年4月に広告枠のマーケットプレイスを展開するカンバンクラウド株式会社を設立。CEOとしてビジネスモデル構築や財務等を手がける。Twitterはこちら
関連記事
 “時代の寵児”から転落──ワークマンとスノーピークは、なぜ今になって絶不調なのか
“時代の寵児”から転落──ワークマンとスノーピークは、なぜ今になって絶不調なのか
日経平均株価が史上最高値の更新を目前に控える中、ここ数年で注目を浴びた企業の不調が目立つようになっている。数年前は絶好調だったワークマンとスノーピークが、不調に転じてしまったのはなぜなのか。 不正発覚しても、なぜトヨタの株は暴落しないのか
不正発覚しても、なぜトヨタの株は暴落しないのか
2024年に入って、トヨタグループ各社で不祥事が発覚し、その信頼性が揺らぐ事態を招いている。世界的な自動車グループの不正といえば、15年に発覚したドイツのフォルクスワーゲン社による排ガス不正問題が記憶に新しいが、トヨタグループは比較的、株価に影響がないようだ。なぜこのような差が生まれているのか、 「バブル超え」なるか 日経平均“34年ぶり高値”を市場が歓迎できないワケ
「バブル超え」なるか 日経平均“34年ぶり高値”を市場が歓迎できないワケ
日経平均株価が3万5000円に達し、バブル経済後の最高値を連続で更新し続けている。バブル期の史上最高値超えも射程圏内に入ってきたが、ここまで株価が高くなっている点について懸念の声も小さくない。 ブックオフ、まさかの「V字回復」 本はどんどん売れなくなっているのに、なぜ?
ブックオフ、まさかの「V字回復」 本はどんどん売れなくなっているのに、なぜ?
ブックオフは2000年代前半は積極出店によって大きな成長が続いたものの、10年代に入って以降はメルカリなどオンラインでのリユース事業が成長した影響を受け、業績は停滞していました。しかしながら、10年代の後半から、業績は再び成長を見せ始めています。古書を含む本はどんどん売れなくなっているのに、なぜ再成長しているのでしょうか。 孫正義氏の「人生の汚点」 WeWorkに100億ドル投資の「判断ミス」はなぜ起きたか
孫正義氏の「人生の汚点」 WeWorkに100億ドル投資の「判断ミス」はなぜ起きたか
世界各地でシェアオフィスを提供するWeWork。ソフトバンクグループの孫正義氏は計100億ドルほどを投じたが、相次ぐ不祥事と無謀なビジネスモデルによって、同社の経営は風前のともしび状態だ。孫氏自身も「人生の汚点」と語る判断ミスはなぜ起きたのか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング