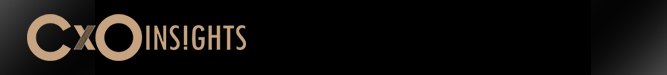NECは生成AIでどう変わる? トランプ政権誕生の影響は? 森田社長に聞いた(1/2 ページ)
NECは生成AI領域で、2025年度末までに約500億円の売り上げを目指している(関連記事)。米国企業が生成AI開発をリードする中、国内IT企業として、いち早く国産の大規模言語モデル(LLM)の開発を進めてきた(関連記事)。
独自の生成AI開発は、そのまま安全保障に結び付く問題でもある。LLMの構築には大量の半導体が必要となり、世界規模での半導体獲得競争に参戦する形になるからだ。防衛事業を手掛ける同社は、経済安全保障の観点からも独自の生成AI開発に取り組んでいる。
2024年、生成AIは企業の業務ツールへの導入が進んだ。2025年はどう変わるのか。前編【NEC森田社長に聞く「2025年の投資戦略」 BluStellarとDX人材活用はどうなる?】に続き、森田隆之社長に生成AI開発の狙いや、今後の見通しを聞いた。
生成AIを巡る国家間競争 2025年の展望は?
――生成AIについて、2025年度末までに約500億円の売り上げを目指す方針です。具体的な計画を教えてください。
生成AIは今、急速に進展していると思っています。特に業務系へのAI適用がこの1年で加速度的に進むと考えています。特に(個人専用のAIが予定の管理や買い物などを代行する)AIエージェントの話がいろいろ出てきています。
われわれNECでも研究所で3年ほど前から「AIオーケストレータ」という名前で、AIエージェントの研究開発を進めています。データアセットの取り組みや、著作権や倫理系の仕組みが出来上がっていくことで、業務への適用が徐々に実現していくでしょう。つまり、業務で使っていくAIがいよいよ出てくると思います。そのあたりも含めて、業務の中で生成AIが活躍してくると思っています。
――2024年は各社が生成AIサービスを展開しています。こうした中で、NECの事業展開の方向性は?
私たちの強みは、生成AIをゼロから作っていることだと思います。研究開発のために3年前の時点で既にGPU約1000基を持っていて、それを使用できる環境にありました。
NECでは、どのように生成AIが作られ、進化していくのかについて、深い理解に基づく事業展開が可能です。また、米国でも進んでいる小規模言語モデル(SLM)などは当初からわれわれは用意していますが、NECではスマホ、サーバ、データセンター、クラウドなど、それぞれに搭載できるサイズの言語モデルを持っています。
LLMについては協業していますが、データセットを含めて閉鎖的に学習可能で、われわれ独自で進化させて提供できます。そういったものを使って業務や業種に特化したさまざまなアプリケーション領域にAIを提供していきたいですし、市場としてもその領域が最終的に大きくなると思います。
――AIの運用には膨大な電気を消費します。日本の電力調達環境をどう見ていますか。省電力化についても教えてください。
米NVIDIAのチップはAIに最適化したチップではなく、もともとゲームやグラフィックスのプロセスから始まったので、余計な機能がたくさん付いています。そういう意味では、AIに最適化したチップのアーキテクチャの研究開発が、さまざまな企業で進んでいます。既に市場にプロトタイプとして出ているものもあります。消費電力的には今後、5分の1から10分の1になるようなチップが出てくると思います。
一方で当面は、学習などさまざまな領域で今のNVIDIAを中心とするGPUでの普及が進むと考えています。そうすると電力の問題は、かなり大きな問題になるでしょう。例えばデータセンターで見た時に、今までのデータセンターとは処理の頻度が違うので、3〜4倍の電力消費量の差になると思います。
この部分が国の競争力につながってきます。電力についてAI領域で何らかの政策や施策が実施されないと、国際的競争の観点でも不利になる可能性があると思います。そのあたりは政府でぜひ検討していただきたいと思いますし、検討いただいているかと思います。日本が国際的な競争の中できちんとプレゼンスを発揮していく上でも、電力はAIの開発と合わせて十分に配慮しなければならない問題だと考えています。
――国産半導体企業であるラピダスへの出資におけるメリットとデメリットは?
NECは半導体からイグジットした歴史があります。一方で当社の先端技術については、われわれが半導体の設計をして、TSMCなどに生産を委託しています。このマーケット状態では、TSMCに依存していると言えます。設計なども米Broadcom(ブロードコム)やNVIDIAに依存していますが、それでは競争が足らないと考えています。
日本の中でラピダスのような少量多品種で、半導体の設計サポートを実現できることは、ユーザー企業である当社としては非常にウエルカム(歓迎)だと考えています。そういう意味で、最初にこの話を聞いた際に、先端半導体のユーザー企業として支援することで2022年に出資に応じた背景があります。現状もその立場は変わっていません。ユーザー企業の立場として応援するということでもありますし、何か要請があれば、その立場で考えることになります。
関連記事
 NEC森田社長に聞く「2025年の投資戦略」 BluStellarとDX人材活用はどうなる?
NEC森田社長に聞く「2025年の投資戦略」 BluStellarとDX人材活用はどうなる?
2025年度は中期経営計画(中計)の最終年度だ。2025年、NECはどのように変わっていくのか。その方針を森田隆之社長に聞いた。 “孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」
“孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」
「部下と議論するより面白い」と株主総会で会場を沸かせた孫正義氏のChatGPTの使い方とは。 孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?
孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?
ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は、個人専用のAIが予定の管理や買い物などを代行する「パーソナルエージェント(PA)時代」が数年以内に到来するとの見方を明らかにした。 NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?
NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?
ECの森田隆之社長は12月12日、アイティメディアなどのグループインタビューに応じ、生成AIを開発する国内企業との協業について「競争するところと協調するところは常に意識しており、そういう(協業する)動きになると思っている」と説明した。 NEC責任者に聞く「生成AIの勝機」 マイクロソフトCEOとの会談で下した決断とは?
NEC責任者に聞く「生成AIの勝機」 マイクロソフトCEOとの会談で下した決断とは?
「生成AIをブームで終わらせたくない」と意気込むNECの吉崎敏文CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)に開発方針などを聞いた。 NEC森田社長に聞く「新卒年収1000万円施策」の効果 魅力的な職場を作ることこそマネジャーの仕事
NEC森田社長に聞く「新卒年収1000万円施策」の効果 魅力的な職場を作ることこそマネジャーの仕事
NECは顔認証に代表されるように世界でも有数の認証技術を持っている。加えて月や火星探査などの宇宙開発など夢のある技術開発に長年注力してきた。今後の展望を森田隆之社長に聞いた。 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング