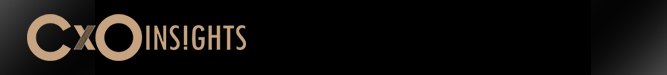ロングセラー「ゆかり」誕生秘話 品質にこだわる三島食品の「努力と挑戦」:地域経済の底力
「良い商品を良い売り方で」
これは、広島市の食品メーカー・三島食品が掲げる基本方針である。創業以来、同社は何よりも商品の品質を高めることを重視してきた。そう口にするのは容易だろう。ただし、それを愚直に、時にはコストを省みずに実践しているのが、三島食品のこだわりである。
そして、顧客に歩み寄り、ニーズに応える。これらが相まって、大ヒットかつロングセラーのふりかけ商品「ゆかり」が生まれたといっても過言ではない。
赤しそふりかけのカテゴリーでおよそ8割のシェアを誇るこの圧倒的なブランド力は、いかにして作られたのだろうか。比類なきふりかけブランド誕生の背景には、同社の努力と挑戦があった。
当時は「炊き込みわかめ」が一番人気だった
1949年に創業した三島食品は、ふりかけでは後発のメーカーとして事業をスタートした。既に広島県では1901年創業の田中食品が先行して商品を販売していたため、しばらくは営業面で苦労が続いたという。
「他社が持っていた市場の中に入っていくということで、かなり苦戦を強いられたようです。いろいろな工夫をして、売り上げを伸ばしていこうと、ふりかけの量り売りも行っていました」と、三島食品の野口英善常務取締役は述べる。
市販用商品だけでなく、他社に先駆けて業務用商品の販売を始めたほか、早々に広島から県外へ進出することを決める。1957年に大阪、58年に東京、59年に名古屋と相次いで出張所を設けた。なお、同社は海外展開も早く、40年以上も前にブラジルに拠点を構え(現在は撤退)、その後、米国に1988年、中国には1990年に進出を果たした。それだけ新市場の開拓は待ったなしの状況だったのだ。
県外で営業活動を展開する中、名古屋の担当者が目をつけたのが、赤しその漬物という独自の食文化だった。これが東海エリアでよく売れていたのである。
「他の地域でも(赤しそは)梅干しに入っているから少しは食べていたでしょうけど、名古屋では、梅干しを漬けた後の赤しその葉っぱだけを食べる習慣がありました」と野口氏は説明する。
これを商品化したいと担当者は訴えたが、漬物の販売は社長が認めない。何度も押し問答があった末、ふりかけであればということで、商品の開発に着手する。そうして完成したのが「ゆかり」である。1970年、最初は業務用として大袋に詰めて発売。とはいえ、すぐには売れなかった。
しばらくして、とあるタイミングで学校給食に「ゆかり」が採用されることに。そこからじわじわと認知度が高まっていき、全国へと導入が広がっていった。
実は当時、学校給食には「ゆかり」だけでなく、混ぜごはんの素「炊き込みわかめ」も提供していた。
「『炊き込みわかめ』も1970年に発売した商品です。私が入社してすぐ、営業担当と一緒に学校を回ったことがありまして、小学校ではわかめごはんが一番人気だったのです」
その後、「ゆかり」も「炊き込みわかめ」も市販用を発売したが、後者のカテゴリーシェアは丸美屋食品工業が伸ばしていった。
「もし私たちのマーケティングが強ければ、うまくわかめの市場も獲得して、ひょっとしたら『ゆかり』よりも売っていた可能性はありますね」と野口氏は苦笑する。
一方で、前向きに捉えると、当時は「ゆかり」の存在感がなかったため、他社も赤しそのふりかけに手を出さなかったのではないかと野口氏は推察する。
「『ゆかり』があまり目立たなかったから、丸美屋さんも力を入れなかったのかなという気はしますね。他社がしそのふりかけを販売しようとした時には、もう私たちがブランド力を持っていたから、負ける気はしませんでした」
赤しその品種改良に踏み切る
学校給食による普及を追い風に、70年代半ばには「ゆかり」の市販用に踏み切る。そこにはある程度の自信があった。
「給食で食べたお子さんが家に帰り、お母さんに『給食で出た赤いごはんが食べたい』というようになっていました。牧歌的な時代だったので給食センターの調理員に分けてもらっていた人もいたようです。であれば、スーパーでも売れるのではないかとなって市販用の発売につながりました」
ただし、いきなりヒットしたわけではない。当時は「瀬戸風味」「かつおみりん」といった既存の商品の方が売れ筋だった。
とはいえ、じわじわと、徐々に売り上げを伸ばしていった「ゆかり」。すると今度は、別の問題に直面する。原料となる赤しその品質(香り)の担保である。そのため何度も生産地に足を運んでは農家とコミュニケーションを取り、商品の改良を重ねた。
それ以前から近畿や中部、四国の農家とともに質の高い赤しそ栽培に取り組んでいたが、在来種では質も量も限界があった。そこで1988年、当時の社長だった三島豊氏の大号令の下、赤しその新品種開発がスタートした。それから11年後の1999年、新たな品種が完成。翌年には農林水産省に「豊香」の名称で出願登録した。
さらに2006年には広島県北広島町に自社農園事業「紫の里」を設立し、翌2007年より赤しその栽培を開始した。三島食品では現在、国産および中国産合わせて年間約3000トンの赤しそを使用している。
コスパが悪くても素材の品質にこだわる
三島食品の品質に対する追求は「ゆかり」に限った話ではない。他の商品でも徹底したこだわりを見せる。
一例を挙げると、「青のり」の原料であるスジアオノリは、広島県福山市で陸上養殖に取り組んでいる。ふりかけに使うかつお削り節は、自社工場で一から削っているし、いくつかの商品で利用するごまは、生ごまを調達してきて、これも自社工場で煎っているのだ。
ここまでやっているメーカーはほとんどいないという。なぜなら生産効率が悪いからだ。それでも三島食品は、できるだけ素材から自分たちの手で作ることを心掛ける。場合によってはコストを度外視したとしてもだ。
「良い商品を作るには、良い原料を使わないといけないというのが、創業者の口ぐせでした。原料へのこだわりと、それをしっかりと商品化するのが基本的なスタンスです。これは譲れません」と野口氏は強調する。
品質にこだわるという創業以来の変わらぬ理念が、比類なきふりかけブランドを生み出し、多くの人々に愛され続ける存在へと成長させた。そのロングセラー商品の裏には同社の長年の努力と挑戦の物語が詰まっていたのだった。
著者プロフィール
伏見学(ふしみ まなぶ)
フリーランス記者。1979年生まれ。神奈川県出身。専門テーマは「地方創生」「働き方/生き方」。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」を経て、社会課題解決メディア「Renews」の立ち上げに参画。
関連記事
 「ゆかり」一本足打法からどうやって抜け出した? 三島食品の運命を変えた“事件”とその後
「ゆかり」一本足打法からどうやって抜け出した? 三島食品の運命を変えた“事件”とその後
押しも押されもせぬ広島・三島食品の看板商品、ふりかけの「ゆかり」。ただし近年、「ゆかり」一強だった状況が変わりつつある。いま、三島食品で何が起きているのか? その中身を取材した。 新潟市へ「オフィス移転する企業」が倍々で増えている理由
新潟市へ「オフィス移転する企業」が倍々で増えている理由
今までにはない施策を打ち出したことで、近年、新潟市へオフィス移転する企業が倍々で増加中である。成果が生まれている要因を探った。 初音ミク、セガ……札幌市のITコンテンツ企業誘致 市長が明かす「大札新」の狙い
初音ミク、セガ……札幌市のITコンテンツ企業誘致 市長が明かす「大札新」の狙い
札幌市が企業誘致を進めている。東京のIT企業やコールセンターが、札幌市での人材確保を狙って進出するケースが多く、企業からの注目が集まっている。 なぜ北海道「人口5000人の町」に23億円の企業版ふるさと納税が集まったのか
なぜ北海道「人口5000人の町」に23億円の企業版ふるさと納税が集まったのか
のべ23億円以上の企業版ふるさと納税を集めた「人口5000人の町」が北海道にある。理由を町長に聞いた。 ハイハイン休暇にハッピーリターン制度 亀田製菓が人事改革を加速させたワケ
ハイハイン休暇にハッピーリターン制度 亀田製菓が人事改革を加速させたワケ
亀田製菓が組織・人材改革を急ピッチで進めている。「ハイハイン休暇」や「ハッピーリターン制度」といった制度をこの数年で矢継ぎ早に創出。常務執行役員で、管理本部 総務部長の金子浩之氏に狙いを聞いた。 女性管理職比率20%は射程圏内 亀田製菓が取り組んだ「3つの変革」とは?
女性管理職比率20%は射程圏内 亀田製菓が取り組んだ「3つの変革」とは?
亀田製菓は2019年に経営トップが「ダイバーシティ元年」と宣言。女性に限らず、多様な人材が活躍できる組織づくりをグループ全体に広げようとしている。同社はどのように進化したのか。古泉直子常務に聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング