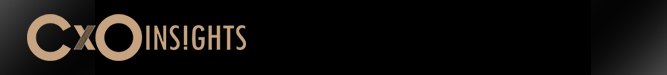大赤字で始まった「がん啓発ライブ」、なぜ10年続いた? ヘルスケア企業社長に聞く「慈善事業のROI」(1/2 ページ)
エムスリーグループのヘルスケア企業3Hメディソリューションが主催する音楽チャリティライブ「Remember Girl’s Power!! 」(通称・オンコロライブ)。がん啓発や治験参加をテーマに、2016年から続けてきている。
10回目となる2025年は、9月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)の4日間、池袋西口公園野外劇場とサンシャインシティ噴水広場で開催。いずれも誰でも立ち寄れるオープンスペースで、観覧は無料(一部有料エリア)。さらに公式サイトの配信ページを通じてオンラインでも無償公開する。
実はこのオンコロライブは4回目まで、チケット販売による有償のライブだった。ところが2020年のコロナ禍を機に、オープンスペースによる無償へと切り替えた。そして無償化を機に協賛企業が増え、イベント規模を拡大に成功した経緯がある。
なぜ、有償モデルから無償化への転換を決断できたのか。その決断の裏にどんな葛藤があったのか。3Hメディソリューションの滝澤宏隆社長に聞いた。
 滝澤宏隆(たきざわ ひろたか)米国カルフォルニア州立大学にて学位を取得。損害保険会社、ゲーム開発会社のシステム開発、Webサイト開発を担当。ITによるヘルスケアイノベーションを目指し、2005年にクリニカル・トライアルの立ち上げに参画し、業界に先駆けて被験者募集システムを構築。2009年に代表取締役に就任
滝澤宏隆(たきざわ ひろたか)米国カルフォルニア州立大学にて学位を取得。損害保険会社、ゲーム開発会社のシステム開発、Webサイト開発を担当。ITによるヘルスケアイノベーションを目指し、2005年にクリニカル・トライアルの立ち上げに参画し、業界に先駆けて被験者募集システムを構築。2009年に代表取締役に就任治験業界最大の課題は「参加者不足」
――3Hメディソリューションは治験事業を長く手掛けてきました。オンコロライブも、治験の啓発が一つのテーマになっています。日本の治験業界が抱えてきた課題とは何だったのでしょうか。
日本の治験業界における最大の課題は「被験者が集まらない」ことなんです。恐怖感や誤解が根強い。例えば「治験に参加すると副作用で病気になるんじゃないか」といった誤解が一般的には残っています。やってみれば分かりますが、安全性には十分に配慮されていますし、必ずしも怖いものではありません。ただ、それがどうしても一般には伝わりにくいのです。
――そういう意味でもオンコロライブは啓発活動として大きな役割を果たしているのですね。
そうです。オンコロライブのテーマには「小児がん・AYA(Adolescent and Young Adult、15歳から39歳までの若年成人)世代のがん啓発」と同時に「臨床試験の啓発」が入っています。いずれも社会的にまだ浸透しきっていないテーマだからこそ、イベントやライブという形を通して、多くの人に触れてほしいと考えています。
――実際にこの10年間やってきて、ビジネスモデルの変化もありました。当初は有料チケット制から、今は無償モデルに変わっています。振り返ってみて、転換点になった出来事や、特に印象に残っていることはありますか。
やはり大きかったのは、音楽プロデューサー(ポップカルチャーフェス「@JAM」総合プロデューサー)の橋元恵一さんや、豊島区と協業できたタイミングですね。それまでは、毎回「どの会場を押さえるか」から始まり、キャパシティの制約に悩んでいました。箱が300人しか入らなければ、当然その規模以上には広がらない。ですが豊島区と組み、公共のオープンスペースを使えるようになったことで、会場の問題が一気に解消しました。それだけでなく、通りすがりの人でも参加できるようなオープンな環境で実施できるようになり、影響力が格段に増したのです。
集客の手応えで言えば、少なくともそれまでの10倍以上に広がったと思います。閉じられた会場だけでなく、オンラインも含め、偶然立ち寄って目にする人が増えた。これは私たちが目指している「できるだけ多くの人に伝える」という目的に直結していました。
赤字を補ったのは本業とサポーター
――確かにオープンスペースでの開催だと、リーチできる範囲が全く違いますよね。米ニューヨークのセントラルパークなどではチャリティーの大規模フリーライブが文化として定着していますが、日本ではまだ途上です。その一つの形をオンコロライブが担っているのかもしれませんね。
そうですね。私自身、米国留学時代にそうした文化を目にしていましたが、日本でそれを実現するのは簡単ではありません。ただオンコロライブが10年を経て、そうした文化の一つになってきたのは確かだと思います。
――チケットによる有償時代のオンコロライブを、どう振り返りますか。
最初の数年は「毎回大赤字をどう埋めるか」という我慢比べでした。実行委員長の柳澤昭浩さんとも「じゃあ今回はどうカバーしようか」と議論しては次に進む、そういう繰り返しです。ただ、それを経験したからこそ少しずつ改善ができるようになり、赤字幅も年々減っていきました。
――どういう形で赤字を穴埋めしていたのですか。
ライブ単体では赤字でも、他の事業や番組企画、サポーター企業との取り組み、本業のビジネスの中で補ってきました。会社全体で見れば収益は確保できますので、一イベントだけ切り離して考えるのではなく、「次に生かす」という位置付けでした。最初はデータもなく手探りでしたが、毎年の経験で「このくらいの規模なら成立する」という感覚がつかめるようになったのです。
――なるほど。失敗や赤字を糧にした10年だったのですね。
そう思います。最初から順調にいくことはありませんでしたが、改善の積み重ねによって今の形にたどりつけました。その意味では、赤字を経験しなければ今のオンコロライブもなかったと感じています。
――無償化への最初のきっかけは、コロナ禍での開催となった2020年のイベントでした。このイベントは無償かつオンライン配信のみになりましたね。
そうですね。いろいろな条件や環境変化が重なった結果ですけれど、確かにコロナ禍は大きな要因でした。その上で大きかったのは、橋元プロデューサーという音楽プロデューサーの助言です。「こういう形でやるなら、無償化して多くの人を集めた方がいいのでは?」という提案を受けて、私たちの中でも考え方が切り替わったんです。そこが一つのパラダイムシフトでしたね。固定観念にとらわれず、思い切って変えることの大切さを実感しました。
4年間の試行錯誤が成功の土台に
――とはいえ、無償化を決めるまでには迷いもあったのではないですか。
もちろん迷いました。協賛企業がどのくらい集まるかも分からない状況で、制作費は確実に出ていくわけですから、不安は大きかったです。ただ、最終的には「これでやってみよう」と決断しました。根拠は正直なかったですね。通常の仕事でもそうですが、根拠が立っているものは「チャレンジ」とは言えないと思っています。不確実だからこそチャレンジなのです。
――とはいえ、思い切った「チャレンジ」だったと思います。
そうですね。それにちょうどそのタイミングで柳澤さんと話している中で、「自治体の協力を得られないか」という話が上がったんです。そこでふと思い出して、知り合いの豊島区の議員にダメ元で話を持ちかけてみたところ、すぐに「それはぜひ協力したい」という話になり、あっという間に共催が決まりました。こちらも予想していなかったスピード感でしたね。
以前からその豊島区議とは顔を合わせる程度の関係ではありましたが、特別に強い縁があったわけでもありません。ただ思い切って相談したことで、予想以上に早く事が進みました。その流れで会場の支援につながり、無償化が実現できたんです。
――一つ一つ道が切り開かれた形だったんですね。
まさにそうです。無償化という思考の切り替えも、制約条件があったからこそ生まれた工夫だったと思います。むしろ制約がある中で「どう実現するか」を考えることに価値があった。それが結果的に新しい形を生んだのだと感じています。
――2016年から2019年までの4回を有償モデルでやってきて、失敗や試行錯誤を重ねたからこそ無償化という決断ができた面もありますよね。
それは間違いなくそうですね。何もないところに突然成功は降ってきません。必ず数々の失敗があって、その中から学びや気付きがあって、新しい形が生まれるんだと思います。そういう積み重ねがなければ、今回の決断もなかったはずです。
――これはビジネスのケース・スタディとしても学びが大きいようにも思います。
多くの人が恐れる失敗も、実際には大したことはないんです。失敗しても死ぬわけではない。むしろ失敗してでもチャレンジした方が、得られるものは大きい。成功すればもちろん大きな価値になりますし、失敗してもそれは次につながる価値になる。やる意味は十分にあると思っています。
関連記事
 「がん啓発ライブ」を有償→無償モデルに転換したワケ ヘルスケア企業の挑戦
「がん啓発ライブ」を有償→無償モデルに転換したワケ ヘルスケア企業の挑戦
がんの臨床試験(治験)と最新のがん医療情報に特化した情報サイト「オンコロ」が主催し、10年目を迎える「オンコロライブ」。現在は無償で実施しているものの、第1〜4回目までは、チケット販売制の興行形態で開催していた。2020年のコロナ禍を機に、無償・協賛という新たなビジネスモデルにピボットした経緯がある。実行委員長に転換の意味を聞いた “年100回以上”のライブ通いで築いた信頼 無名チャリティーライブが取った「弱者の戦略」とは?
“年100回以上”のライブ通いで築いた信頼 無名チャリティーライブが取った「弱者の戦略」とは?
がん啓発音楽イベント「Remember Girl's Power!!」(通称・オンコロライブ)が10年目を迎える。有名ではないチャリテイーライブをどのように支え、豊島区との連携を経て規模を拡大してきたのか。がん啓発というテーマでどのようにブランディングを進めていったのか。実行委員長に聞いた。 ヘルスケア企業が音楽ライブを主催 挑戦の先に「社長が目指したもの」とは?
ヘルスケア企業が音楽ライブを主催 挑戦の先に「社長が目指したもの」とは?
エムスリーグループの3Hメディソリューションは、2016年から音楽ライブ「Remember Girl’s Power!!」を通じたがん啓発活動を展開している。滝澤宏隆社長に企画の意図と本業への影響、これまでの10年で目指したものを聞いた。 コロナ禍で製薬業界に訪れた転換点 ヘルステック企業が実現を目指す「バーチャル治験」とは?
コロナ禍で製薬業界に訪れた転換点 ヘルステック企業が実現を目指す「バーチャル治験」とは?
新型コロナウイルスの影響によって、医療や医薬品業界のビジネスモデルが大きく変わろうとしている。病院などに足を運ばなくても受けられる「バーチャル治験」の実現に向けて期待が高まった。 「若年性がん」に光を ヘルスケア企業がチャリティーライブを10年、続けてこれたワケ
「若年性がん」に光を ヘルスケア企業がチャリティーライブを10年、続けてこれたワケ
がん啓発音楽イベント「Remember Girl's Power!!(通称・オンコロライブ)」が9月で10回目を迎える。3Hメディソリューションは10年間、どのようにイベントを支え、豊島区との連携を経て規模を拡大してきたのか。オンコロライブ実行委員長に聞いた。 音楽プロデューサー・亀田誠治が語る 日比谷音楽祭が人材育成の“現場”になるワケ
音楽プロデューサー・亀田誠治が語る 日比谷音楽祭が人材育成の“現場”になるワケ
日比谷音楽祭を支える一連の取り組みには、組織運営や人材マネジメントに通じる実践的な学びが随所に凝縮されている。実行委員長を務める音楽プロデューサー・亀田誠治氏にインタビュー。人材育成や多様な立場の人々がつながり合う現場づくりの核心に迫っていく。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意
ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意
ソニーグループを再生させた平井一夫元社長兼CEOが自ら実践し、体験を通じて会得したビジネスリーダーに必要な要件とは?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング