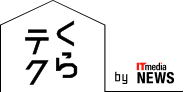「金属魂」的、FinePix X100のある生活(金属と皮の濃密な関係):矢野渉の「金属魂」的、デジカメ試用記(2/3 ページ)
レザーケースがやってきた
発売日から1カ月以上、4月になってやっとレザーケースが手もとに届いた。皮の質は申し分ない。適度な硬さが心地良く、安心感がある。定番の裏の起毛布地もしっかりしていて長く使えそうだ。このケースはかなり凝っていて、フロントの留め具部分は磁石になっている。また、本体の固定は三脚穴を使わずにストラップ金具部分に引っ掛ける方式なので底部の盛り上がりがまったくなく、ケースのフタを閉めた状態でも立つ。このようなケースは初めてではないだろうか。
残念に感じたのはストラップだ。三角環(ストラップ取り付け金具)に掛ける部分だけが黒いプラ素材になっている。ここはやはりすべて皮素材で行きたいところだ。また、このケースは本体+金属キャップの状態の寸法で作られているので、フードを一緒に持ち歩こうとすると収納場所がない。逆にフードを付けるとキャップと、取り外したリングを入れる場所がない。
そこで手持ちのクラシックストラップと、キヤノンのフードケース(どの機種用なのかは分からない)を取り付けてみると果たしてぴったりのサイズだった。
革ケースを使うようになってから、X100を外に連れ出す機会が増えた。カメラバッグを持つほどでもない時にでも、とりあえず安心して携帯できるのはうれしい。今のコンパクトデジカメは数あるガジェットのひとつに過ぎず、機械としての面白さはあるのだが、写真を撮るという行為においては存在が軽すぎるような気がする。X100のように多少のストレスを感じつつ、それでも割と気軽に持ち歩ける、ぐらいの存在が一番「写真を撮る」気分にさせてくれるのだ。
ここでもうひとつ問題が持ち上がった。天気の良い日などは、僕はフロントの革カバーを外してフードを付けっぱなしで外に出たりする。その時のレンズキャップがないのだ。キャップを付属させなかったのは、撮影が終わったらフードを外せということなのかも知れないが、いかにも面倒だ。保護フィルターは割れた場合を考えて極力使いたくない。そこで、これもX100の雰囲気を壊さないようなかたちで手持ちの機材を漁(あさ)ってみた。
その結果、しっくりくるのはペンタックスのタクマーレンズ(M42マウント)用のかぶせ式金属フードだった。X100のレンズ前のアダプターには49ミリフィルター用のネジ山が切ってあるので、そこにガラス部分をはずしたフィルター枠を取り付ける。するとこのかぶせ式フードがぴったりはまるのだ。
もうひとつの方法は純正フードをはずして、hamaブランドで発売されている49ミリ用フードを使う方法だ。先端にフードキャップが付いている。ただしこの商品は24ミリ用なのでフードの効果があまり期待できないことと、光学ファインダーの視界を半分ぐらい覆ってしまうので、EVFのみの使用となることに注意が必要だ。
色々と古い機材を取り出しているうちに、X100を「あの時代」に戻してやろうという気になった。写真が、カメラが輝いていた時代。過去を美化していると言われても結構だ。僕らはその時代に経験を積んだのだから。
まずはストロボ。これは思い切ってグリップタイプでいきたい。写真のものは東芝のQCC3200という機種。30年以上前のものだがまだ普通に使える。レトロモダンな形とツートンカラーのデザインがX100とよく合っているだろう。パナソニックだけではなく、昔は東芝も日立(kakoというブランド)も、コンデンサを作っている会社は皆ストロボも売っていたのだ。
次にレリーズ。X100はシャッターボタンに機械式レリーズ用のネジ山が切ってある。これは感激だ。高級コンパクトデジカメでは初ではないだろうか(ライカやR-D1はレンズ交換式なのでコンパクトデジカメではない)。電磁レリーズが悪いわけではないのだが、コネクタがUSBだったりするとおじさんは意味もなく落ち込むのである。
機械式レリーズならたくさん持っているが、ここはプロンター(Prontor)というセレクトで。プロンターはドイツのシャッターメーカーだ。いわばシャッターを知り尽くしている会社なのだ。写真のレリーズは小型軽量、しかし耐久性に優れた素材を使っている、僕の常用の機材だ。
僕はX100というカメラに、早急に結果を求めすぎたのかもしれない。このカメラとのひと月以上の対話のなかで、お互い譲るところは譲って、ずいぶんと関係は改善されている。どの道、死ぬまで使い続けることは決まっていることなのだ。だからもっとゆっくりと慣れて行けば良い。
デジタルの数字ではなく、ダイヤルの角度で絞り値が理解できたりする感覚というのは、考えてみれば若い頃には普通にやっていたことなのだ。それだけ神経を研ぎ澄ませて写真を撮っていた。オートフォーカスになり、AEの精度があがり、僕らは少し楽な方へ流れてしまったようだ。
あの頃に戻れるわけではないし、あんな苦しい修行時代は二度と御免なのだが、X100があれば少しだけあの頃の感覚を取り戻せる気がする。今の自分を確認するためにも、X100は常にそばに置いておきたいカメラなのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR