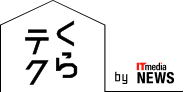「COOLPIX P300」第3回――雪山へP300を連れ出す:長期試用リポート(1/2 ページ)
ニコン「COOLPIX P300」(以下P300)の使い方をある程度をマスターしたところで、ゴールデンウィークに突入した。筆者はGWは長野県と岐阜県の境にある穂高岳で取材があったため、P300と出かけることにした。
旅程は4日間あるが、途中で仕事をしなければならない関係で荷物の中にMacBook Airを入れた。このため装備重量が増加し、苦肉の策としてP300を含む、USBで充電できる各種デバイスの予備電池をすべて置いて行くことにした。MacBook Airから充電できるからだ。
経費削減のためテント泊を行う関係で荷物重量は20キログラム近くまでふくれあがった。ここに一眼レフと交換レンズを加えるのはさすがにつらいため、カメラはP300と予備としてシグマのDP2だけを持つことにした。
軽快な撮影リズム
上高地についたのは夕方の17時過ぎ。ここから徒歩で涸沢まで6時間かかるため、途中にある徳沢と言うところで1泊することにした。翌朝の出発時間は決まっているため、徳沢にいかに早く着くかで睡眠時間が決まる。
道中のP300を使った撮影はISOオートを活用し、撮影設定についてあまり考えなくても済むようにした。時間に余裕がない中でも、サッと撮影できるのは有り難い。
予定より少し早く徳沢に入れたので、睡眠時間を長めに確保できた。翌朝からは打って変わって雪の世界に突入する。
この日の穂高岳周辺は、雪崩の跡がたくさんあってとても緊張感のある情景だった。腰をすえて写真を撮るのは安全が確保されたところに限られ、それ以外のところでは常に雪崩が起きることを意識し、万一雪崩に飲まれた際に自身の位置を知らせるビーコンを身につけて行動した。
雪解け時期は雪崩に加えて、落石にも注意が必要だ。また、足下は本来、川が流れている場所なので、氷を踏み抜いてしまう可能性もある。このため、行動時間をできるだけ短くすることで遭難リスクを軽減する必要がある。結果的に撮影時間を短縮するほかなく、行動時に数秒立ち止まって撮影するというスタイルとなった。P300は軽いので首にさげていても苦しくならない。ネックストラップだとブラブラしてしまうので、ザックに適当に引っかけた。
涸沢にテントを張って2泊目。翌日は稜線(りょうせん)にある穂高岳山荘に宿泊するため、テントは涸沢に残置し、装備を軽量化して稜線を目指すことにした。3時間ほどの登攀中は霧や吹雪、一転して晴れ間が出るなど天候がめまぐるしく変わった。
稜線の山小屋、穂高岳山荘に到着し、ピッケルとP300だけを持って奥穂高岳へ向かうことにした。
穂高岳山荘から奥穂高山頂までの所要時間は夏期で50分。冬季は状況により変化する。難所は稜線まで上がるハシゴが連続するエリアだ。その後も絶壁と呼ぶにふさわしい急登が続くため、気の抜けない展開となる。
ここでの撮影は滑落を防ぐ装備であるピッケルを常に持っている必要があったため、必然的に片手で撮影することになる。P300はそのようなシーンでも確実に撮影することができた。また、液晶画面でフレーミングするのは周りにも気を配りやすい。
しばらく稜線を歩いていると、ジャンダルムと呼ばれる岩峰が見えてくる。比較的歩きやすい稜線を詰めれば、奥穂高岳山頂に到着。しかし、足場が少ないのと時間が押していたためすぐに下山を開始した。
翌朝、3日かけて登ってきたルートを1日で下山する。前日とちがって天候もよく、途中からは半袖で下山した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR