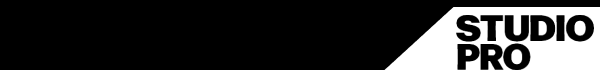スマホ全盛期に、なぜ“小さなカメラ”か――5940円のトイカメラでよみがえった撮影の楽しさ:小寺信良のIT大作戦(1/2 ページ)
一般的には動画の人と思われている筆者だが、実は写真もかなりやってきたつもりだ。すでに連載としては終了しているが、2007年7月から2010年12月まで、Business Media 誠(現:ITmedia ビジネスオンライン)において、フィルムカメラとオールドレンズの連載を持っていた。なぜビジネスチャンネルでこんな連載をやることになったのか今となっては謎だが、おそらく2005〜6年ぐらいにオールドカメラのリバイバルブームが起こったのがきっかけだったのだろう。
2010年頃には中国製のトイレンズが流行った時期もあったが、それには興味が持てなかった。トイレンズはオモチャだが、オールドレンズは古くても本物である。傍から見ればどちらも「所詮は遊び」なのだろうが、筆者の中ではその差は大きかった。表現とテクノロジーの葛藤が興味の本質であり、「おもちゃがこんなに良く写る」ということは本筋ではなかったのだ。
連載が終了してもしばらくフィルムカメラで写真を撮っていたが、近所のDPE店が閉店してしまって現像に出すのが面倒になり、次第にミラーレスカメラにオールドレンズを付けて撮るようになった。
ただなんだろう、撮る楽しみの半分以上は失われてしまった感じがした。ミラーレスカメラなら、ファインダやモニターで見えているものがそのまま撮れる。それは写真を撮るというより、もはやレンズごとの記録である。
2014年頃にはInstagramのブレイクから、「映える写真」を前提としたスマートフォン撮影文化が大きく拡大した。飲食、ファッション、観光などの消費も、スマホ写真の出来不出来に左右されるようになっていった。
この頃に写真を撮ることを覚えた世代の人たちは、いまだ写真のメインはスマートフォンであろう。撮る→加工→投稿までが完結している。当時のコンパクトデジカメも何とかこのフローに乗ろうとしたが、失敗した。やはり2つのデバイスを同時に使えというのは、写真そのものよりも投稿した結果の方に興味がある人たちには、無理があった。
個人的にはこの頃から、次第に写真を撮る行為から遠ざかっていった。メシが出てくるたびにみんながいそいそとスマホを取り出して写真を撮るという状況に、なんだかしらけてしまった。写真を撮り終わるまで、こちらはおあずけをくらった犬みたいに箸をつけるのを待たなければならないのも、無意味な時間であった。
写真を撮るというモチベーションとは
スマートフォンのカメラは、家の中ではいつもそこらへんに置いてあるので、子供や猫の写真を撮るには便利である。だが外出しても、プライベートな意味でのストリートスナップをスマホで撮るという気にはなれなかった。
写真が好きだった人でも、スマホがあればいつでも撮れると思いつつ、言われてみれば撮らなくなったという人は、それなりに多いのではないだろうか。街には多くの被写体やアングルがあるが、写真を撮るぞというつもりでスマホをポケットに入れている人は、さっと取り出して撮ったりするのだろうか。
だがスマホには決済情報や個人情報がたくさん入っており、無くしたり壊れたりすると被害甚大ものとなってしまった。気軽にポケットに入れて盗まれたりしたら大変だ。そんなことから、スマートフォンは次第にカバンの中に入れて持ち歩くようになった。これではいいアングルを見つけても、ますます写真を撮る気にはならない。モチベーションが下がるとは、こういうことだろう。
だがそうした気持ちが反転したのは、意外にも昨年暮れに気まぐれで購入したトイカメラがきっかけだった。OPT NeoFilm100という、フィルムみたいな形をしたミニカメラだ。価格は5940円。
面白いのでどこかでレビューでもしようと思って購入したのだが、東京出張の際に持って行ったら、自分でも驚くほど楽しかった。小さいので手に持っていても邪魔にならず、気が向いたらすぐに撮れる。
トイカメラなので、画質的には見るべきものはない。若い人なら「エモい」と感じるのかもしれないが、それはこうした低画質を経験したことがないからだ。カメラ業界が長いオジサンからすれば、「ああこれCMOSが出始めの頃に中国製のカメラでこういうのあったわー」という画質である。
だが写真を撮るモチベーションとは、カメラ片手に街をぶらつくということから始まるのだということに気がついた。確かにフィルムカメラで写真を撮っていた頃は、いつもカメラを左手から提げているか、小さなものはポケットに突っ込んでいたから、すぐに撮る気になった。逆に撮る気があったから、そのように持っていたのだろう。やる気とカメラの持ち方は、表裏一体だ。
当然、街を見る目も変わる。何か撮ってやろうという視線で見るからだ。ただの見知らぬ通りも、そうした動機づけがあれば宝の山だ。
こうした気持ちは、撮った写真をネットに上げて自分の成果としたいという欲求とは別のものだ。撮った瞬間にアートとして完成する、風景とカメラと自分とのライブセッションのようなものだと言える。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR