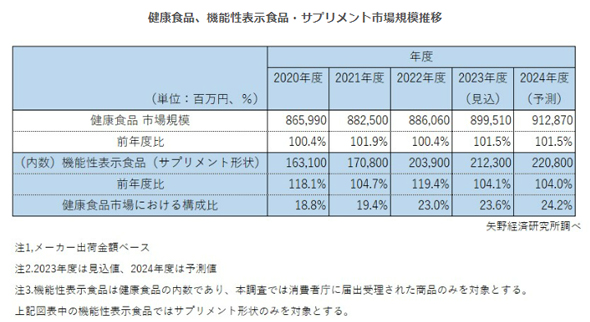小林製薬の「紅麹」問題 「機能性表示食品」見直しの背景に何があるのか:スピン経済の歩き方(5/7 ページ)
» 2024年04月10日 06時00分 公開
[窪田順生,ITmedia]
もしも、小林製薬の危機管理担当者だったら……
このように機能性表示食品にとって「リスク」にしかならない環境が整っていく中で、ここからは小林製薬の危機管理担当者になったつもりで想像していただきたい。
24年1月以降、全国各地の「かかりつけ医」などから、紅麹のサプリメントを摂取した患者に「健康被害」が確認されたとの報告が次々と入ってきた。多くの人は先ほどの「常識」と照らし合わせれば、きっとこんな風に危機感を抱くのではないか。
「機能性表示食品制度をつぶしたくてしょうがない医療界に、次々と健康被害の情報が集まっている。これは対応を間違えると、制度そのものがひっくり返る問題になるぞ」
もちろん、こういうものはセンスもあるので、どこまで危機感を抱くのかは人それぞれだろう。ただ、少なくとも「健康被害の報告がたくさん出てきたけれど、まだ原因も特定できないんだから公表も報告もしなくていいか」とはならないのではないか。
しかし、小林製薬はそういう「悪手」を取った。一般消費者に健康被害が拡大している局面で、「原因究明よりも顧客の安全を優先する」という危機管理の鉄則を無視して、「社内論理」を優先した。結果、自社だけではなく「機能性表示食品制度」全体を“地獄への道連れ”にしてしまった。
「結果」を厳しく判断させていただくと、小林製薬の社内には残念ながら、この問題がこれからどう発展していくのかと先読みをした「リスクシナリオ」を描ける人材、または「危機管理のプロ」がいなかったのではないかと思わざるを得ない。
関連記事
 バーガーキングがまたやらかした なぜマクドナルドを“イジる”のか
バーガーキングがまたやらかした なぜマクドナルドを“イジる”のか
バーガーキングがまたやらからしている。広告を使って、マクドナルドをイジっているのだ。過去をさかのぼると、バーガーキングは絶対王者マックを何度もイジっているわけだが、なぜこのような行動をとるのか。海外に目を向けても同じようなことをしていて……。 物流2024年問題で叫ばれる「多重下請撤廃」 それでも“水屋”がなくならないワケ
物流2024年問題で叫ばれる「多重下請撤廃」 それでも“水屋”がなくならないワケ
物流の「2024年問題」がいよいよ本格化していく。全日本トラック協会が「多重下請構造」について「2次下請までと制限すべき」と提言しているが、筆者はそう簡単になくならないと考えている。なぜかというと……。 優秀な若手がどんどん辞めていくが、「社内運動会」をやっても防げないワケ
優秀な若手がどんどん辞めていくが、「社内運動会」をやっても防げないワケ
パナソニックが若手社員約1200人を対象に実施した「社内運動会」が話題になっている。「組織間の交流」が目的だったが、若手社員の反応はどうだったかというと……。 「辞めたけど良い会社」 ランキング ワースト30社の特徴は?
「辞めたけど良い会社」 ランキング ワースト30社の特徴は?
辞めたけれど良い会社は、どのような特徴があるのか。IT業界で働いた経験がある人に聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング
アイティメディアからのお知らせ
SpecialPR
SaaS最新情報 by ITセレクトPR
あなたにおすすめの記事PR