ナレッジマネジメントのIT化と家族経営の八百屋:顧客指向開発のすすめ(3)
ナレッジマネジメントの例として筆者がよく使うのは、八百屋さんとの比較である。家族で経営している八百屋さんでは、おじさんもおばさんもお得意さまをよく把握している。ナレッジマネジメント成功のポイントはそんなところに隠されている。
顧客を起点とした企業組織
自分が所属する企業の全社組織図を、じっくりと見たことはあるだろうか。企業が社内向けに作る全社組織図は、上位から機能別に細分化され、下位組織まで記載されていることが多い。
一方、顧客起点で企業組織を考えたとき、どの部署がどのように関係し、どのように処理が流れていくかを見て取れる組織図となっているだろうか。通常の企業組織図と顧客起点の組織図の比較は、図1の例のようになる。
通常の企業組織図では、顧客との関係が複数あることが分かりにくい。一方、顧客起点で組織図を作ってみると、顧客接点が複数あり、顧客との取引や顧客のサポートを遂行していくために企業内の各種機能が存在することが分かる。また、複数の顧客接点間の連携は、通常の企業組織図からは見えてこないことも分かるはずである。
図1に示す顧客起点の企業組織図イメージ例では、代理店を管轄する営業部署、顧客と直接取引する営業部署、コールセンター(電話)、Web/電子メールのやりとりをハンドリングするコンタクトセンター、そして事務センターなどを顧客接点の例として挙げた。事務センターが顧客接点である理由は、顧客に請求書や利用明細を送ったり、顧客から申込書を受け取ったりする機能を持つためである。
顧客を起点とし、さまざまな顧客接点と社内の関連部署間を連携・協調させていくためには何が必要であろうか。
組織間をつなぐナレッジの共有
組織間の連携の第一歩は、「情報の共有」である。そもそも組織の構成員が情報共有することに必要性・有益性を感じなければ、いくらシステム構築をしたりネットワーク基盤を整備しても、本当の意味での情報共有は進まない。つまり、組織間の連携を実現するためには、組織の構成員の意識や組織の文化を変えていく必要がある。そして、ここで共有が必要な「情報」とは、informationだけではなく、ナレッジ(=knowledge)が大きく含まれるものである。
社内で情報共有するためにはITによるアシスト(自動化)も必要ではあるが、まず学習(学ぶ)する組織、情報共有する文化=自働化が重要である。学習する組織を作るためには、組織にインタンジブルアセット(見えない資産)があることを認識させるところからスタートしなければならない。
ナレッジマネジメントを浸透させるための条件は、自働化が主、自動化(IT)が従である。どんな立派なナレッジマネジメントソフトを入れても使う気がなければタダの箱である。
自働化とは「自ら考えて動く(働く)」である。この自働化とは、他人や機械に任せることではない。自ら問題を見つけ自ら解決するように、人間が能動的な状態になることである。命令されたことしかやらないのではなく、常に問題意識・改善意識を持ち、「自分で働く」ことである。外的要因、内的要因の変化や、予期せぬトラブルに対して、組織構成員おのおのが自律的に対応する。自働化している構成員は常に問題意識を持っており、現状に満足しないため、常に改善を考え実行していくことになる。
次に情報共有する文化であるが、地道な啓蒙(けいもう)活動と地道な成果の積み上げが必要である。情報を共有する文化なしに、やみくもに行っても成果につながらない。そのためには、SECIサイクル、PDCAサイクルを(推進者側が意識して)回していく必要がある。SECI(Socialization、 Externalization、Combination、Internalization)サイクル、PDCA(Plan、Do、Check、Act)サイクルを回しているうちに、組織に情報共有する文化として根付く。
図3のSECIサイクルは、組織としての知識創造プロセスとしてスパイラルの形を取る。単なるサイクルではなく、暗黙知と形式知の相互作用が起こり、知識変換の4つのモードを通じて増幅されていくことになる。
学習する組織とは、外的要因・内的要因の急激な変化により生み出されるさまざまな問題に対応するため、企業内外の状況を構成しているさまざまな要素の複雑な相互作用を把握する力を養い、組織構成員のコミットメントと創造性を高め、チームや組織として個々人の力を結集するスキルを養うことを目指した概念である。
顧客起点でSECIサイクルを回し、顧客とのWin-Winモデルを創出し続けることは、学習する組織でなければ実現不可能である。
自らが学び、学んだことを組織に還元し、形式知化し、そして対話するというSECIサイクルにより、目に見えない資産(インタンジブルアセット)を持続的に創造し続けていくことで、競争優位をつくりだすことが可能となる。さらに組織構成員自身の自己実現をも実現する、こうした組織こそが学習する組織であり、これを実践し続ける企業や組織だけが、顧客指向ということができる。
図1の比較に示すような、単に機能別に組織化された「管理する組織」を超越し、「学習する組織」への変革を図ることによって顧客(あるいは関係先との)とのWin-Winモデルを実現する。
組織としてのアンラーニング
組織としての成功体験が強ければ強いほど、成功体験に裏付けされた判断を下すことが多い。これでは環境の変化に対して後れを取る。環境の変化に後れを取ることを防ぐためには、組織としてアンラーニング(学習棄却)を身に付けなければならない。
ここで、なぜ学んで身に付けたものをアンラーニングしなければならないのか、というところが理解できない人が出てくる。だが、そのように「アンラーニングは不要だ」と考えてしまう人には、時間軸という概念が欠落している。つまり、「学び」「身に付けたこと」が「いま」そして「今後」役に立つ情報なのかということを再考しないということである。
例えば、電話をかけるときに電話機の横にあるハンドルをグルグル回すというのは日常生活においてはすでに役に立たない。ハンドルが付いている電話機は電話機としての価値はすでになく、骨董としての価値のみである。現在電話をかけたければ数字のボタンを押すケースが最も多い。ハンドル式(自分で発電、程よいところで受話器を取って相手の番号をいう、交換手がつなぐ)→ダイヤル式(受話器を上げ、ダイヤルするとパルスを交換機が読んで相手先につなぐ)→プッシュ式(パルスかトーンを交換機が読んで相手先につなぐ)という変遷の中で、日常生活に必要な「電話のかけ方」としてアンラーニングが必要である。回すべきハンドルが存在しないのに、そのハンドルを回すかけ方を電話のかけ方として認識しておく(身に付けておく)ことは無意味である。電話のかけ方のロジックはアンラーニングされ新たにラーニングされる必要がある。
ラーニングとして、これまでに身に付けた知識を、アンラーニング(学習棄却)し、リラーニング(再学習)し直すことで、顧客の変化・ビジネス環境の変化に対応できる組織となる。
アンラーニングとは、古い技術、役に立たなくなった能力を単純に捨て去ることではない。また、ただただ新しい方法をありがたがって受け入れればよいというものでもない。新旧2つの選択肢がある場合、新を採用するのか、旧を採用するのか、あるいは新旧のブレンドとなるのか、さまざまな選択肢を考慮する必要がある。その判断は、外的要因、内的要因、組織の能力、経験を比較し、多面的にバランスよく考えることにより行われるべきである。アンラーニングとはそのような場面で、組織の限界、あるいは過去に学習したこと(≒経験則)の限界を把握する能力ともいえる。
またアンラーニング以前に、自分の学んだことが基本なのか応用なのかという認識を持つ必要がある。応用ばかりでは、「木を見て森を見ず」どころか「枝葉を見て森を見ず」になるからである。「経験がないからできない」などと言い出すのは、応用ばかりを身に付け、基本を身に付けていない組織に多い。ここでもアンラーニングのスキルが役に立つ。身に付けたことが応用であるならば、応用の応用たる部分はいったんアンラーニングし、基本として把握すべき部分を再度体系的に学ぶべきである。基本をリラーニングしておく準備を済ませておけば、経験がないことに対しても対応にかかる時間は短縮される。
ナレッジ共有の実現
企業内でナレッジを共有していくためには、何らかのナレッジマネジメントの仕組みが必要となる。
筆者がよく例として使うのは、八百屋さんとの比較である。家族で経営している八百屋さんでは、おじさんもおばさんもお得意さまをよく把握している。そして、さまざまな取引(大根やねぎなど)や旬の野菜のお勧め、その日の夕食に合わせた野菜の組み合わせのお勧めなど、スーパーマーケットでは不可能な濃密な情報量を会話の中でやりとりする。その中から、重要顧客にはおまけをしたり、重ければお届けしたりという付加価値を提供する。そしてその情報共有は、おじさんおばさんという八百屋さんの共同経営者間の会話で行われる。
これと同じ会話を企業内で行おうとすると、ミーティングばかりで仕事をする時間が取れないことになる。そこで必要となるのがナレッジマネジメントの仕組みである。ナレッジマネジメントでは、先に述べたようにSECIサイクルを基軸として、インタンジブルアセットとしてのナレッジの蓄積と共有を行う。
ナレッジマネジメントをIT化するときに最も気を付けなければならない点は以下の4点である。
- 何を共有するのかを定める(何を共有すると効果があるのかを理解しておく)
- コラボレーション方法、反応を返す方法を定める
- 1、2を実現するツール、パッケージソフトを選択する
- 既存システムとの連携方法の検討
先にパッケージソフトを選定し、その後で内容や使い方を考えるようでは、本来その企業であるべき情報共有に至らず、使われずに終わることも多々ある。導入に当たっては、企業にとってあるべきナレッジマネジメントの形を熟考すべきである。
また、実現したいナレッジマネジメントの姿が、Wikiやblogなどのナレッジマネジメント専用ではないツールなどでも実現可能であれば、積極的に採用を検討すべきである。
今回は、組織とナレッジという観点から述べた。次回はアーキテクチャとしての組織間連携はどうあるべきか、組織とプロセスやITによる支援という観点から述べる。
筆者プロフィール
營田 茂生(つくた しげお)
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
セキュリティサービス本部 シニアコンサルタント
大学時代は構造化プログラミングを学ぶ。日立ソフト入社後,主として保険、証券会社システムのシステムエンジニアリングに従事後,現在は仮想化ビジネスを推進中。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に
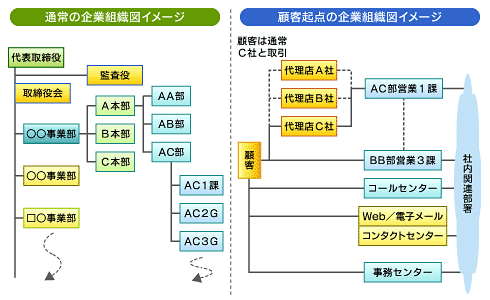 図1 通常の企業組織図と顧客起点の組織図の比較
図1 通常の企業組織図と顧客起点の組織図の比較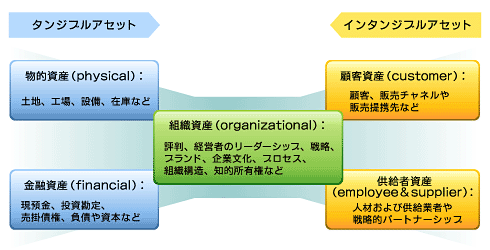 図2 インタンジブルアセット(見えない資産)の重要性
図2 インタンジブルアセット(見えない資産)の重要性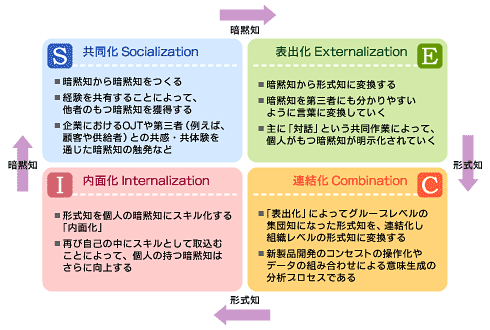 図3 SECIサイクル
図3 SECIサイクル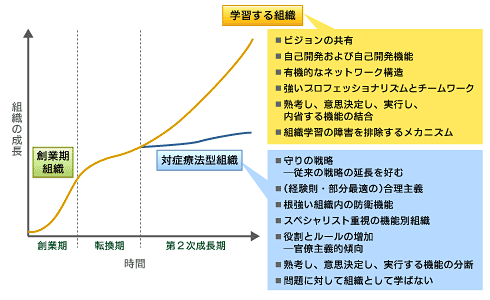 図4 学習する組織とは
図4 学習する組織とは 図5 組織としてアンラーニング(学習棄却)を身に付ける
図5 組織としてアンラーニング(学習棄却)を身に付ける