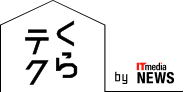“ネット家電”が少し身近に、家電各社のスマート戦略:2013 International CES(1/4 ページ)
1998年ごろ「インターネット冷蔵庫」と呼ばれるものがシャープから登場して大きな話題になったことを記憶している。その後2000年代に入ると、やはりシャープから「インターネット電子レンジ」が登場して話題となった。だが当時のインターネット家電といえば、液晶ディスプレイにWebブラウザを表示するくらいの機能しかなく、画面上でレシピを確認する程度のものだった。
それから10年、昨年2012年にはパナソニックからNFCを使ってスマートフォンとの連携が可能な家電製品が登場し、各社も白物家電にネットワーク機能を搭載してインターネットとの接続や機器同士の連携を可能にする試みをスタートするなど、ネットワークと家電を組み合わせた仕組みがより身近なものになった印象を受ける。こうした傾向は、1月上旬に米ラスベガスで開催された「2013 International CES」でも感じられ、少ないながらもより実用的なものが登場した。今回はその一部を紹介していこう。
2013年、ネットワーク家電はより身近に
「家電同士を接続して、より便利に集中管理しよう」という試みは以前からあり、実際、冒頭のシャープのインターネット冷蔵庫も機器内部にPC機能を組み込み、これをホームサーバとして周囲のネットワーク対応家電を接続して集中管理しようというものだった。もっとも、各家電をインテリジェント化するために高コストになり、小型化も難しくなるという問題があるほか、当時はまだ無線LANやZigBeeといった手軽なネットワーク接続の手段が確立されておらず、ネットワーク接続そのものの難易度が高かった。技術の進歩と低コスト化が進み、これらの課題に解決の目処が立ったのはつい最近の話だ。
また、仮に家電のネットワーク化に成功して集中制御が可能になっても、具体的な用途提案がなければ「単に割高な家電」になるだけで、そのメリットを訴えることはできない。正直にいって、Webブラウジングやレシピ確認機能だけでその点を訴求するのは難しく、より便利さをアピールする提案が必要だ。
しかし今回のCESでは、より現実的な便利さを訴える製品が増えてきたという印象を受ける。例えば、以前と比較して家電のネットワーク化と集中制御ハードルが下がったと感じたのがLGとSamsung(以下サムスン)の韓国系メーカーブースだ。ブース内に置かれたネットワーク家電はすべてWi-Fi接続に対応しており、インターネットを介して管理用のクラウドに接続可能になっている。NFCに対応したスマートフォンを家電に“タッチ”することで、スマートフォンのアプリから各家電の制御が可能。またネットワーク接続に対応したテレビからも、制御画面からグループ化されて接続状態にある各家電を操作できる。
ポイントがいくつかある。まず、すべての対象家電がWi-Fi接続に対応しており、専用のタッチパネルで製品単体であっても、ある程度インテリジェントに操作できることだ。またLGのNFCタグを組み合わせた例のように、ある決まったルーチンワークで家電を制御する場合(例えば電灯の一斉消灯など)、“タグ”にこのルーチンを実行する“トリガー”を登録しておき、タッチだけで実行できる。アプリで個別制御するのもいいが、玄関脇に設置したタグにスマートフォンをかざしてワンタッチで命令を実行できるのであれば、そちらのほうが手軽だろう。これはスマートフォンとNFCをうまく組み合わせた例だといえる。
ただし、まだまだ使い勝手の面で微妙な点もある。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR