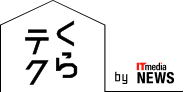全て“当たり”にするこだわり、刀鍛冶を思わせるブレーキ焼き入れ――「日本のものづくり」マインドが凝縮されたGT-R:西川善司の「日産GT-Rとのシン・生活」(1/6 ページ)
IT系ライターの西川善司さんはクルマ愛好家でもあり、スポーツカーに関する記事も執筆している。そんな西川さんが手に入れることになった最新スポーツカー「GT-R nismo Special Edition」を切り口に、これからのクルマのものづくりを解き明かしていく。
前回から少し時間が空いてしまったが、2回目となる今回は、日産「GT-R」という車が「日本の工業製品」として、非常にユニークな存在となっている点に言及したいと思う。
「混流生産」という選択が生んだ恩恵(1)〜絶対的な価格を下げ、生産ラインの稼働率を押し上げた
前回は、「筆者と日産GT-Rとの衝撃的な出会い」について語りつつ、「なぜ人々はコストパフォーマンスを度外視した買い物をすることがあるのか」という話題について触れた。
そんなわけで、「日産GT-Rとの衝撃的な出会い」を果たした筆者だったが、実際に実車を手に入れるのはその“出会い”から2年後の2012年になってからである。
筆者がGT-Rに興味を持ったのは、前回で紹介したように、当時の開発責任者であった水野和敏氏との出会いがきっかけだが、車両そのものに敬服を抱くようになったのは、GT-Rを製造している日産の栃木工場の製造ラインを見学してからだ。
GT-Rは、栃木工場における、「フェアレディZ」や「スカイライン」に代表される日産のFR(前搭載エンジン/後輪駆動車)車種の製造ラインで混流生産されており、これは今も当時も変わっていない。
当時の開発責任者の水野氏は「GT-Rの設計上の絶対的な高性能」は「高精度に生産できる製造技術がなければ実現し得ない」と考えており、プロジェクト最初期には、GT-R専用製造ラインを設立することで実現されるべき、と考えていたようである。
当時の日産の社長であったカルロス・ゴーン氏は、社内の誰よりも「GT-Rは日産のブランドの象徴である」と理解を示していたものの、一方で「日産はスーパーカーメーカーではなく、量産車メーカーである。その枠組みを超えてまで取り組むべきではない」とも考えていた。そこで、結局は、栃木工場のFR製造ラインで製造することが決定されたのであった。
しかし、この「混流生産」採用の決断は、結果的には「よい選択だった」と関係者達も振り返っている。
その最大の恩恵は、価格を絶対的に抑えられた、ということだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR