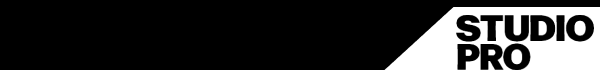GoPro「凋落」の理由、華々しいスタートアップの紆余曲折を振り返る 大きな分岐点は8年前に:小寺信良のIT大作戦(4/5 ページ)
そして戦国時代へ
18年3月には、毛色の変わった製品がリリースされた。「GoPro Fusion」は、前後にカメラを搭載した、いわゆる360度カメラである。どうせ全方位撮るんだから、ということで、ディスプレイは搭載しない。
ただ当時としては、360度カメラの参入はかなり遅い。リコーやカシオ、ニコン、そしてInsta360が全天球や半天球カメラに参入したのは16年頃で、ある意味このあたりがピークである。Fusionの発表自体は17年の「HERO6 Black」と同時だったが、発売まで半年かかる製品を先に発表するということは、やはりその年の目玉が欲しかったのだろう。
ただ360度撮影の考え方が、他社と違っていた。多くのカメラは360度の映像を、見る時に見回すことができるというVR指向で考えていたのに対し、Fusionは全天球を撮影して、最終的には特定の画角に切り出して使うという、ノーファインダー撮影的なスタンスであった。確かにそれはそうなのだが、そうした方向性は当時スタンドアロンカメラ化しはじめていたInsta360と競合した。 ある意味、虎の尾を踏んだ格好である。
だが18年に登場した「HERO7 Black」は、スポーツ向けカメラとしてGoProは別格、と感じさせたカメラだった。このとき搭載された次世代の電子手ブレ補正「HyperSmooth」が、あり得ないほどのスタビライズ性能をたたき出したのである。この機能によって、中国の粗悪なGoProクローン製品を駆逐すると同時に、日本メーカーも沈黙させた。
だがGoPro一人勝ちの状況は長くなった。19年にはDJIがまさにGoProスタイルそのままの「Osmo Action」をリリースしてきた。すでにDJIはドローン専門メーカーではなく、小型ジンバルカメラの「Osmo」や「DJI Pocket」をモノにした、カメラメーカーへと成長していたが、今さらジンバルなしでGoProと競合しても勝てるのか? という疑問も残った。
Insta360も、親指大のウェアラブルカメラ「Insta360 GO」をリリースした。直球でGoProと同じ形ではないが、マーケットはかなり近い。確実にGoProの牙城を削りに来た格好だった。
19年にGoProは、2つの製品をリリースした。「HERO8 Black」は5から7までずっと同じだったボディーを刷新し、「モジュラー」と呼ばれる周辺機器と合体して機能拡張できる作りとした。このため、HDMI端子が本体からなくなり、モジュラーを別途購入しなければ映像出力が出せなくなった。これはネット中継でサブカメラや手元カメラとして利用してきたユーザーにとっては、GoProを見限る大きな理由となった。
「GoPro MAX」は、Fusionに続く360度カメラである。小型化してディスプレイも付けるという格好で、要するに前後にカメラがあるGoProである。360度にこだわらず、前だけ、後ろだけでも記録できる。ただGoProの代わりとして使うには、出っ張ったレンズが破損の危険もあり、Fusion同様いったい誰向けなのか、マーケットがはっきりしない謎カメラであった。360度カメラはこれ以降登場していない。
20年には、Insta360がGoProとストレートに競合する「Insta360 ONE R」をリリースした。カメラ、プロセッサ、バッテリーとモジュールごとに分解できるカメラだが、組み合わせればGoProスタイルになる。そもそもGoProマウントを備えている時点で、競合する気まんまんである。カメラモジュールを交換すれば360度カメラにもなり、FusionやMAXとも競合した。
20年の「HERO9 Black」は、また新設計のボディーとなった。サブスクに加入すると本体が割引になるというキャンペーンを始めたのも、この頃である。要するにクラウドサービスで付加価値を付けるという差別化だ。カメラ的には前面ディスプレイがカラー化して自撮り対応するといった変化は見られるが、それはすでに「DJI Osmo Action」や「Insta360 ONE R」で実装されていた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR