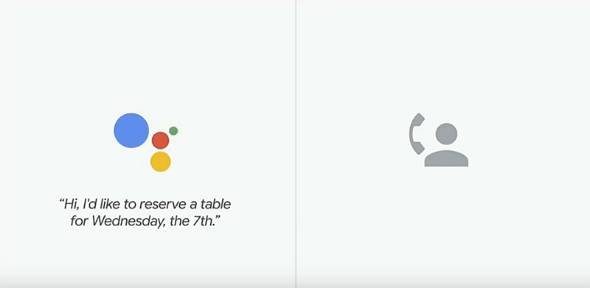「AIスピーカーに話し掛けるのが恥ずかしい」がもたらす、ちょっとした大問題:“いま”が分かるビジネス塾(3/3 ページ)
音声インタフェースは利用者が育てなければならない
Googleのデモは、AIが自分に代わって電話を掛け、レストランなどに予約を入れるというもので、片方の話し手がAIだとは気付かないほどやり取りはスムーズだった。あくまでこれはデモであり、現実にはここまでスムーズなやり取りは難しいだろう。だが、AIによる会話が想像以上のレベルまで進歩しているのは間違いない。
つまり、音声操作は次世代の中核的なインタフェースになる可能性が高いということなのだが、ここで大きな問題が発生してくる。音声を使ったインタフェースは、利用者数が多ければ多いほど精度が上がり、利用者数が少ないと精度が下がってしまうという欠点を持っている。
キーボードやタッチパネルは、ひとたび仕様が固まってしまえば、全員にとって条件は同じになる。ところが音声操作の場合、利用者がツールを育てていくという側面があり、全員が同じ条件でツールを利用できるとは限らない。
米国など、英語圏で、かつ人口が多い地域のサービスは、使い勝手が日々向上する一方、マイナーな言語で利用者数が少ない地域ではサービス水準がなかなか上がらないということが十分にあり得るだろう。ビジネス的に採算が合わないと判断された場合、その言語でのサービスが中断されてしまう可能性もある。
実際、主要言語圏以外の地域に住む人にとって、人工知能の操作を英語で行うことは当たり前のことであり、それは小国の宿命でもある。
日本市場は、同一言語を話す、生活水準の高い消費者が1億人以上存在するという、世界的にも数少ない有利な条件を備えている。英語版に続いてすぐに日本語版のサービスが登場するのはこうした市場環境のおかげであり、このアドバンテージは日本人に極めて大きな利益をもたらしている。
AIスピーカーのような「育成型」インタフェースでは、普及が進まない場合、日本語でのサービスが打ち切られてしまう可能性は決してゼロではないだろう。恥ずかしがって利用を躊躇していると、サービスそのものが使えなくなる可能性があることも理解しておいた方がよいだろう。
加谷珪一(かや けいいち/経済評論家)
仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。
野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。
著書に「AI時代に生き残る企業、淘汰される企業」(宝島社)、「お金持ちはなぜ「教養」を必死に学ぶのか」(朝日新聞出版)、「お金持ちの教科書」(CCCメディアハウス)、「億万長者の情報整理術」(朝日新聞出版)などがある。
関連記事
 銀行マンが転職できるか真面目に考えてみた
銀行マンが転職できるか真面目に考えてみた
メガバンクの大規模な人員削減計画が大きな話題となっている。そこで注目されるのが銀行マンの去就だが、彼らが他業種に問題なく転職できるのか考察してみた。 なぜメルカリはホワイトな労働環境をつくれるのか?
なぜメルカリはホワイトな労働環境をつくれるのか?
メルカリの福利厚生がホワイトすぎると話題だ。多くの日本企業は働き方改革を実践するため、残業時間の規制などに躍起になるが、根本的な誤解も多い。メルカリの取り組みを知ることで働き方改革の本質が見えてくるはずだ。 伊藤忠がファミマを子会社化、商社とコンビニの微妙な関係とは?
伊藤忠がファミマを子会社化、商社とコンビニの微妙な関係とは?
伊藤忠商事がファミリーマートを子会社化する。しかしながら、特定商社によるコンビニの子会社化は双方にとって諸刃の剣となる。商社とコンビニの微妙な関係について考察したい。 電話やメールでのコミュニケーションが不要になる日は近い
電話やメールでのコミュニケーションが不要になる日は近い
AI社会の前段階としてツールを使った業務の自動化や効率化に注目が集まっている。近い将来、電話はほぼ消滅し、電子メールでのやり取りも激減している可能性があるだろう。 セブンの「時差通勤制度」に見る、働き方改革の“限界”
セブンの「時差通勤制度」に見る、働き方改革の“限界”
セブン&アイ・ホールディングスが時差通勤制度を導入する。評価すべき取り組みだが、一方で、一律の時間枠で社員を拘束する点においては、何も変わっていないと解釈することもできる。同社の取り組みが現実的なものであるが故に、多様な働き方を実現することの難しさが浮き彫りになっている。 「忖度御膳」空振りのうわさから考える、ファミマの“迷い”
「忖度御膳」空振りのうわさから考える、ファミマの“迷い”
ファミリーマートが発売した「忖度御膳」の売れ行きが悪いのではないか? とネット上で話題になっている。もともと数量限定であり、販売不振が本当だとしても、同社にとって大きなダメージにはならないだろう。しかしながら今回の一件は、曲がり角を迎えたコンビニビジネスの現状を浮き彫りにしたという点で非常に興味深い。 マクドナルドとモスバーガーを比較できない理由
マクドナルドとモスバーガーを比較できない理由
マクドナルドが完全復活を果たす一方、モスバーガーは業績の伸び悩みに直面している。同じハンバーガー店なので、どうしても比較対象となってしまうのだが、経営学的に見ると両社はまったく異なるビジネスをしているのだ。 加速する「AI型店舗」 小売の現場はこう変わる
加速する「AI型店舗」 小売の現場はこう変わる
AI時代の到来で小売店も大きく変わろうとしている。AIを活用した次世代型の店舗は、従来の小売店のビジネスをどのように変えるのか。先進企業の事例を紹介しつつ、解説する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング