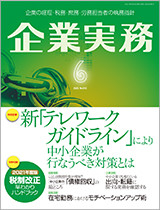出向・転籍の進め方 必要な手続き、人事的な配慮、助成金制度など解説:コロナで増えている(1/5 ページ)
コロナ禍により事業の再編が行われ、それに伴って中小企業でも出向・転籍が増えています。出向・転籍について確認し、必要な手続き、人事的な配慮、助成金制度などについて解説します。
出向とは、会社間で労働者を移動させることをいいます。コロナ禍では業務量が増加する業種と、業務量が減少する業種とで二極化したこともあり、業務量が減少した業種から業務量が増加した業種への人材の移行の手段として出向への注目が集まっています。
出向には現在の所属先に籍を置いたまま別の会社で働く在籍出向と、所属先を現在の会社から出向先の会社に変更する移籍出向の2つがあります。両者は同じ出向であっても、労務管理の際に注意すべき点はかなり異なります。
また、世間一般では在籍出向については単に出向、後者の移籍出向は転籍と呼ぶことが多いため、本稿でも在籍出向のことを出向、移籍出向のことを転籍としていきます。
出向を行う際の労務上の注意点
(1)出向労働者の同意と出向規定
出向では、現在の所属先に籍を置いたまま別の会社で働くことになりますが、同じ会社内での異動とは異なり、勤務先の変更を伴うため、賃金などの労働条件、キャリア、雇用などの面で不利益が生じやすくなります。
そのため、出向を行う場合、基本的には労働者の同意が必要です。ただし、密接な関連会社間の日常的な出向であって、出向に関する包括的な規定が定められている場合はこの限りではありません。密接な関連会社間の出向で、労働者の同意を不要とするための規定には最低限、以下の内容を定めておく必要があります。
- 出向先での賃金・労働条件
- 出向の期間
- 復帰の仕方 など
(2)出向元と出向先の責任の配分
出向において出向労働者は、出向元と出向先で二重の労働契約を結ぶことになります。
その関係上、出向労働者の労務については、出向元と出向先の会社のどちらが、何について、どの程度責任を負うのか、という部分が問題となってきます。
また、過去の通達では「出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用がある」としています。
つまり、労働基準法等の適用についても、出向元と出向先の責任の配分によって、その適用の範囲等が変わってきます。そのため、出向元と出向先で締結する出向契約においては、出向期間などのほかに、出向労働者に対するこうした責任についても会社間で明確化しておく必要があります。
厚生労働省が発行している『在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック』では、出向元と出向先の出向契約において定めておくべき事項として以下のものを挙げていますので、出向を行う際はこれを参考に、出向元と出向先の責任の配分を話し合うとよいでしょう。
- 出向期間
- 職務内容、職位、勤務場所
- 就業時間、休憩時間
- 休日、休暇
- 出向負担金、通勤手当、時間外手当、その他手当の負担
- 出張旅費
- 社会保険・労働保険
- 福利厚生の取扱い
- 勤務状況の報告
- 人事考課
- 守秘義務
- 損害の賠償
- 途中解約
- その他(特記事項)
出向契約に明確な定めがない部分の責任の配分については、解雇権や復帰命令権など出向労働者の地位に関しては出向元が、労務提供請求権や指揮命令権など出向労働者の就労に関しては出向先が負うのが合理的とされています。
(3)出向労働者の賃金と保険料負担
会社間の出向契約において重要となるのが、出向労働者の賃金の扱いです。特にその支払方法については、会社間の取り決めによってさまざまな形が取られており、「出向元が支払う」「出向先が支払う」「出向元と出向先の両方が別々に支払う」のほか、賃金自体は出向先が支払うものの、それと同額を出向元が出向先に支払うことで実質的に出向元が出向労働者の人件費を負担する、といった形もよくみられます。このように、出向労働者への賃金の支払方法については、会社間で自由に決めることができます。
その一方で、出向労働者の賃金で注意しないといけないのが、社会保険や労働保険の保険料です。
関連記事
 定年再雇用「60歳以降、1年ごとに1割給与を減らす」はOKですか?
定年再雇用「60歳以降、1年ごとに1割給与を減らす」はOKですか?
定年再雇用を新設する際、「60歳以降、1年ごとに1割給与を減らす」制度は問題ないか。実例を踏まえ、人事コンサルタントが解説する。 1on1ミーティング、研修受け放題サービス導入……なぜ失敗? 良かれと思った育成施策の落し穴
1on1ミーティング、研修受け放題サービス導入……なぜ失敗? 良かれと思った育成施策の落し穴
あらゆる人事施策には、メリットとデメリットがあります。他社にとっては良い施策でも、自社で導入してみると合わなかったということも起こり得ます。今回は、マネジメントや人材育成に対する誤解を紹介します。 なぜあなたの会社は「内定辞退」が減らないのか? 効率の良い防止策、悪い防止策
なぜあなたの会社は「内定辞退」が減らないのか? 効率の良い防止策、悪い防止策
内定辞退が多い会社の特徴はどこにあるのでしょうか。また、どうすれば解決できるのでしょうか。本記事では、内定辞退を防ぐための考え方を説明します。 “テレワーク手当”の新設で生じる、社会保険の手続き「随時改定」とは?
“テレワーク手当”の新設で生じる、社会保険の手続き「随時改定」とは?
テレワーク手当の新設など、年度の途中で給与額に一定以上の変動があった際に行う必要がある社会保険の手続き「随時改定」について、解説します。
© 企業実務
Special
PR注目記事ランキング