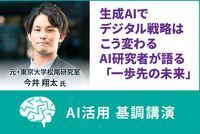私たちはもてあそばれている? 「本の帯」がもたらす“あざとい”3つの効果とは:令和の無駄学(1/2 ページ)
【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!
生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」
【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)
【視聴】無料
【視聴方法】こちらより事前登録
【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。
生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。
連載:令和の無駄学〜僕らにはもっと無駄が必要だ〜
合理的で効率化が求められる社会。どんどん便利になる社会。何不自由なく生きられる社会。しかし、それと逆行するように人々の幸福度は下がっている。
もっと豊かで人間らしい暮らしを得るには、時間的な余白や、一見どうでもいいような機能、生活必需品ではないものの購入など、いうなれば「無駄」が必要なのである。無駄こそ心にゆとりをもたらし、無駄こそ周囲へのやさしさにつながる。真の豊かさを求める上での最強の武器である「無駄」について、社会を解剖していく。
世の中が加速度的に便利になる中、効率は良くなったものの面白さが失われてしまった……。だからこそ、今の時代には「無駄」が必要なのである!
そんな考えのもと鼻息荒く始まった本コラム。第6回目となる今回は、言われてみれば別になくてもよさそう……? そんな本の帯が持つ効果について、ちょっと意外な事実も含めてお話しします。
早速ですが、本の帯って実は海外ではみられない日本特有の文化だということをご存じでしょうか? 一説によると、本の帯が最初に付けられたのは大正3(1914)年であるとされています(※1)。付いていないほうが持ち運びやすいけれど捨ててしまうのも惜しい……なんだか少し不思議な存在です。実際、周りにも捨てずにとっておく人が一定数いるように感じます。
※1:評論家/作家の紀田順一郎氏による読売新聞への寄稿(1994年4月)、記田氏サイトへの再録「たかがオビ、されどオビ」より(2010年11月10月)
今回は、読書が好きな生活者や消費行動の専門家へのインタビューも交えながら、本の帯がもたらす効果について、その実態をひもといていきます。
本の帯って、実際どんな存在ですか?
まずは私の周囲の読書家たちの中で、「書店で本を購入する際、帯をよく参考にする」という方々に意見をきいてみました。
- 評価が高い作品や実写作品の原作など、一般的にいま注目されている本がひと目で分かるので便利(50代・女性)
- あきらかに違和感のある文言やデザインだと、つい中身が気になる(30代・男性)
- 書店で本の帯を見て、新しい作品を知ることが多い(20代・女性)
- 帯に、他の作家が推していると書いてある本は、つい魅力的に感じてしまう(50代・男性)
- もともと違う本を買う予定で書店に行った際、次に読みたい本の候補が帯から見つかることが多々ある(20代・女性)
どうやら、新情報として注目したり、選書の基準にしたりする人が多いようです。
また、過去に本の帯がもたらす効果についての卒業論文をご指導されていた、会津大学短期大学部 産業情報学科 八木橋彰准教授によると「本という商材は、非計画購買が約7割。つまり、別作品の購入目的で書店におとずれた際ついでに買うケースや、衝動買いするケースが他の商材と比べると多い」とのこと。
関連記事
 サンリオはなぜ強い? 「かわいい」だけじゃない、ファン作りの3つの極意
サンリオはなぜ強い? 「かわいい」だけじゃない、ファン作りの3つの極意
近年は大人でもかわいいキャラクターに「思わずハマってしまった」「推しキャラがいる」という人は珍しくありません。しかしなじみがない方は「大人なのに、かわいいキャラクター?」「なんであんなに夢中になるの?」「無駄じゃない?」――そんな風に思ってしまうこともあるのではないでしょうか。かわいいキャラクター業界をけん引する企業、サンリオでプロデューサーを務める池内慎一朗さんに、消費者を夢中にさせる、その裏側にある仕掛けについてお聞きしました。 私たちはなぜ「黒い箱」に高級感を感じるのか “高見え”の正体に迫る
私たちはなぜ「黒い箱」に高級感を感じるのか “高見え”の正体に迫る
なんとなく、「黒い箱」って高級感を感じませんか? 世の中には“高見え”を意識した商品がたくさん存在します。この“高見え”とは一体何なのでしょうか? クリエイターやプランナーに伝えたい いいアイデアには「寄り道」が必要なこれだけの理由
クリエイターやプランナーに伝えたい いいアイデアには「寄り道」が必要なこれだけの理由
読者の皆さんは最近、寄り道していますか? 実は、寄り道はアイデアや企画を考える際に多くのメリットをもたらします。本記事では、寄り道の持つ可能性を考察してみましょう。 なぜ歯磨き粉はミント味? ヒット商品の誕生には「無駄」が必要なワケ
なぜ歯磨き粉はミント味? ヒット商品の誕生には「無駄」が必要なワケ
みなさん、最近無駄話をしていますか? 博報堂ヒット習慣メーカーズでは、これらの「無駄」こそ今の社会に必要なものだと考えています。本記事では、無駄こそが真の豊かさを求める上で最強の武器になると思う理由についてお話しします。 丸亀シェイクうどんの大ヒット 背景にある「あえてひと手間」が持つ効果とは……?
丸亀シェイクうどんの大ヒット 背景にある「あえてひと手間」が持つ効果とは……?
世の中には、「あえてひと手間」加えることでヒットした商品がたくさんあります。例えば、丸亀の「シェイクうどん」の大ヒットでも、「あえてひと手間」が効果的に作用しています。 D2Cはオワコンなのか 多くのブランドが淘汰された背景に“闇深い”事情【マーケターがいま読むべきヒット記事3選】
D2Cはオワコンなのか 多くのブランドが淘汰された背景に“闇深い”事情【マーケターがいま読むべきヒット記事3選】
個人情報保護やサードパーティCookie規制に加え、目まぐるしいスピードで移り変わるトレンド………。マーケティングはどんどん複雑化し、継続的な新規顧客の獲得や、ファン育成の難易度が増しています。今回は、マーケターが今抑えるべきトレンドを紹介した人気記事を、ITmedia ビジネスオンライン編集部が厳選してお届けします。 「広告費0」なのになぜ? 12年前発売のヘアミルクが爆売れ、オルビス社長に聞く戦略
「広告費0」なのになぜ? 12年前発売のヘアミルクが爆売れ、オルビス社長に聞く戦略
12年前発売のヘアミルクが爆売れし、2023年のベストコスメに選ばれた。「広告費0」「リニューアルも一切なし」を貫いてきたのになぜ? オルビス社長に戦略を聞いた。 “勝ち手法”だった「インフルエンサーマーケ」 急激に失速した2つの要因
“勝ち手法”だった「インフルエンサーマーケ」 急激に失速した2つの要因
D2Cの“勝ち手法”だった「インフルエンサーマーケティング」が急激に失速した。「D2C」を取り巻く市場は厳しい中、企業は従来の「インフルエンサーマーケティング」の認識をアップデートする必要がある。 D2Cはオワコンなのか 多くのブランドが淘汰された背景に“闇深い”事情
D2Cはオワコンなのか 多くのブランドが淘汰された背景に“闇深い”事情
D2Cビジネスは冬の時代を迎えている。なぜ多くのブランドが淘汰されたのか……。背景に3つの理由がある。 数学好きにはたまらない? サントリー特茶が広告に「計算問題」を仕込んだワケ
数学好きにはたまらない? サントリー特茶が広告に「計算問題」を仕込んだワケ
 「みさえのインスタ」がリアルすぎる? 55万人のフォロワーを魅了した広告企画がすごい
「みさえのインスタ」がリアルすぎる? 55万人のフォロワーを魅了した広告企画がすごい
 「バカじゃないの?」とも言われた――4℃は「ブランド名を隠す」戦略で何を得たのか
「バカじゃないの?」とも言われた――4℃は「ブランド名を隠す」戦略で何を得たのか
SNS上で一部ネガティブなイメージが語られ、度々話題を集めているジュエリーブランド「4℃(ヨンドシー)」。9月にブランド名を隠した期間限定のジュエリーショップ「匿名宝飾店」をオープンし、話題に。瀧口社長が「匿名宝飾店」を振り返って感じた手応えは……?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング