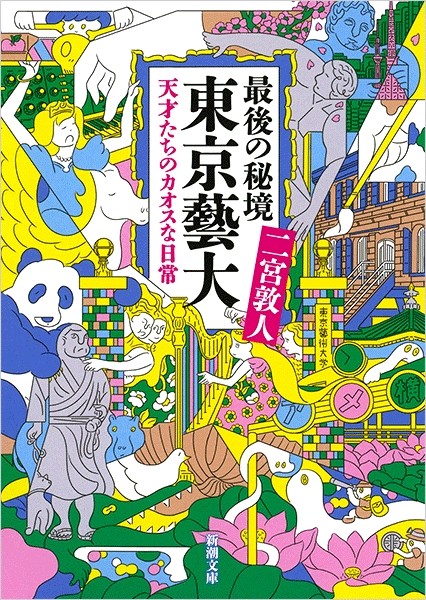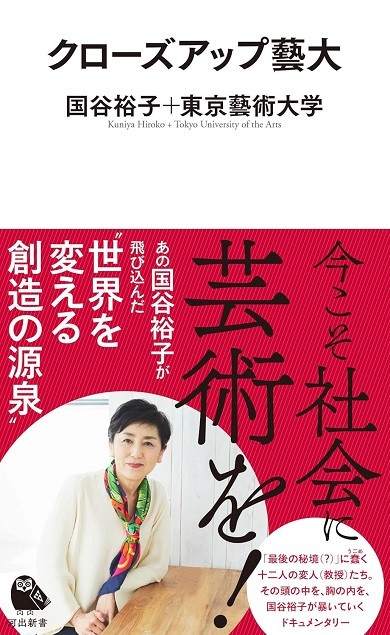箭内道彦教授に聞く東京藝大のブランド戦略 少子化時代の課題とは?:美大でも進む産学連携(1/2 ページ)
日本の美術、音楽大学の最高峰で、その入試倍率から「東京大学よりも難しい」ともいわれる東京藝術大学。国内最高の権威を持つ東京藝大であっても、少子高齢化による時代の変化への対応は、大きな課題だという。
かつては美術学部で50倍以上を超える入試倍率の学科もあったものの、今では10倍を切る科も少なくない。失われた30年の影響もあって、卒業後の進路に対して不安を抱く風潮もあるという。
東京藝大は2016年、書籍『最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常―』(二宮敦人、新潮社)で話題になった。その後も「クローズアップ藝大」「藝大よ、地球を救え。」など、メディア上での独自のブランド展開を進めている。「藝大よ、地球を救え。」では、企業や自治体と藝大生とのマッチングを通じて、産学連携の未来を提示する。閉じた大学から開いた大学への転換を進めている藝大は、画材メーカーのトゥーマーカープロダクツが主催する「コピックアワード」に毎年、審査員も出している。
その東京藝大のブランディング戦略を担当しているのが、箭内(やない)道彦教授だ。箭内教授はクリエイティブディレクターとして、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、資生堂「uno」、リクルート「ゼクシィ」、サントリー「ほろよい」などのブランドを手掛けてきた第一人者である。前編【生成AI時代、広告クリエーターはどう受け止める? 東京藝大・箭内道彦教授に聞く】に引き続き、箭内教授に東京藝大のブランディングについて聞いた。
 箭内道彦 1964年福島県郡山市生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、博報堂を経て、2003年に独立し、風とロックを設立。タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」等、数々の話題の広告キャンペーンを手掛ける。福島県クリエイティブディレクター、東京藝術大学学長特命・美術学部デザイン科教授、2011年NHK紅白歌合戦出場のロックバンド「猪苗代湖ズ」のギタリストでもある。企画、制作、演出、撮影、出演、執筆、教鞭、作詞、作曲、MC、パーソナリティー、イベントの実行委員長、商品開発、など、領域を自在に超え、従来の概念を解体しながら、その全てを「広告」として、クリエイティブディレクション、ブランディング戦略を手掛ける
箭内道彦 1964年福島県郡山市生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、博報堂を経て、2003年に独立し、風とロックを設立。タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」等、数々の話題の広告キャンペーンを手掛ける。福島県クリエイティブディレクター、東京藝術大学学長特命・美術学部デザイン科教授、2011年NHK紅白歌合戦出場のロックバンド「猪苗代湖ズ」のギタリストでもある。企画、制作、演出、撮影、出演、執筆、教鞭、作詞、作曲、MC、パーソナリティー、イベントの実行委員長、商品開発、など、領域を自在に超え、従来の概念を解体しながら、その全てを「広告」として、クリエイティブディレクション、ブランディング戦略を手掛ける箭内道彦にとっての広告ブランドとは?
――箭内教授はタワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」など数々のブランドを作ってきました。箭内教授にとってブランディングとは何なのでしょうか。
幼少時からずっと、自分が他人にどう思われるかを気にして、好きでいてほしいとばかり考えていました。そんな自分がとにかく嫌でした。
ところが、藝大を卒業して博報堂に入社し、広告という仕事に出会って、人目を気にするこの性格を生かせる仕事であることに気が付きました。タワーレコードを好きになってもらうにはどうしたらいいか。ゼクシィがもっと人々に愛されるためには何をしたらいいのか。今までコンプレックスに感じてきたことがプラスに使える。僕は「天職に出会えた」と、一気に目の前が明るくなりました。
ブランディングには、シンボルを作ったり、キーカラーを設定したり、ステートメントを開発したりと、さまざまな入口がありますが、いずれも企業やブランドが時代や人々から受け入れられるための、好きになってもらうための方法を考える作業だと思っています。
――箭内教授はブランドを考えるときに、何を大事にしていますか。
「自分が好きなものしか広告しない」とNHKの「トップランナー」という番組のゲストに出た時に言ったことがあります。オンエアを観(み)ていた知人たちから「そんなことを言ったら仕事が来なくなっちゃうぞ」と心配されました。でもやっぱり僕は良くも悪くも、自分が好きなものを応援したいとか、もっと知ってほしいとか、そういう素人的な仕事の仕方をあえてしています。
自分との関係を見つけることもブランディングの手掛かりになる。昔、婦人服の仕事の依頼が来たことがあります。僕は婦人服を着ませんので、「これは無理だな」と思いました。でも、その服を着て頑張っている女性を想像すると、自分も応援したくなります。そう考えると、そこに“関係”が生まれるわけです。
母と子のお菓子であるビスコの仕事が来たときも同じでした。世界中の人たちは母親から生まれてくる。自分は母でも子どもでもないけれど、母がいる。そこに関係が生まれて自分事になるんですよね。どうやったら自分事になるかという好きの探し方をしていると、人は、世の中のほとんどのことと関係があるのです。「嫌い」という感情ですら、そこに“関係”がすでに生まれているのです。
「閉じる部分」と「開く部分」のアートブランディング
――今では藝大の「大学改革・ブランディング戦略担当」として、大学のブランディングも担当しています。母校でのブランディングはまさに「好き」の極みではないかと思いますが、どのように仕事をしていますか。
故郷という意味で言えば、僕は出身地である福島県のクリエイティブディレクターや郡山市のフロンティア大使もしています。藝大も福島県も、どちらも自分の故郷。恩返しの意味も込めて携わっています。
今の若い人たちは違って来ていますが、日本人の大半は、自分で自分の自慢をするのが美徳ではないと教わってきた人たちです。ですから、自己PRが下手で、損をしていることが多いと思います。そういった点で、「まだ伝わっていない魅力」は、全ての人が持っていると思います。
本人たちが気が付いていない魅力に気付いてもらえるきっかけを自分が作って、その対象がキラキラ輝き出す瞬間が、広告の仕事をする上で最上の喜びです。藝大や福島に限らず、それがこの上なく好きですね。僕が学生に教えているのもその一環なのです。
――藝大は、二宮敦人さんが2016年に出版した『最後の秘境』で注目を集めました。
「卒業生の半数が行方不明」といった記述がキャッチーでしたね。東京藝大に注目してもらうことは出来ました。それをここからどう生かしていくかを考えています。
2018年に藝大のブランディングに着手することになって、最初に着手したのはタグラインの制定です。「タグライン」は自己紹介。企業やブランドの魅力や提供価値を端的に表現する言葉のことです。僕がコピーライティングするのではなく、学生、教職員、OBOGにタグラインから募集しました。一人一人それぞれが藝大をどう捉えているのかをあらためて言葉にしてみる機会を作ったのです。決定したタグラインは、「世界を変える創造の源泉」。これが全てのブランディング作業の礎となります。全ての応募作を集合知として一冊の冊子にして全学配布もしました。
芸術には、閉じる部分と開く部分、どちらも必要だと思っています。芸術のすべてと社会を接続すれば良いかというとそんなことはなく、自分だけにしか理解することのできない深い穴に入り込んでいくのも芸術にとっての重要な在り方です。僕は芸術の「閉じる」と「開く」の両方を同時に発信していくことが重要だと考えています。
「最後の秘境」といわれる神秘性に、人が芸術に心惹かれる部分も重なります。また、社会や企業において、論理だけで組み立てていった答えが通用しない場面も増えてきています。議論を戦わせる際に、AなのかBなのかという向き合い方では対立を生み、溝を深めるだけです。そういった時に、皆が全く想像しなかった答えを出せるのが芸術の役割・使命だと思います。この時代にさまざまな形で東京藝大を伝えていきたいと考えています。
――藝大の「開く部分」は、どのような取り組みをしているのでしょうか。
NHK「クローズアップ現代」のキャスターを23年間されていた国谷裕子さんが、2016年から藝大の理事をされています。僕は「クローズアップ藝大」という連載を国谷先生にお願いし、藝大のWebサイトで始めました。国谷さんが毎回、唯一無二の教授たちにインタビューし、深掘りしていく企画です。タイトルにはクローズアップ現代のご承諾もいただいています。
Webサイトでの連載を読んだ出版社から書籍化したいというオファーをいただいて、2021年に本になりました。そして今度はその本を読んだ企業の方々が藝大を訪ねていらして、新しい産学連携が始まっています。
2023年の電気代の高騰で藝大の財政が厳しい状況になった際には、客員教授のさだまさしさんとともに「電気代を稼ぐコンサート」を奏楽堂で開き、チケット収益を電気代に充てました。他にもさまざまな形で社会と経済の接点を作っていくことに取り組んでいます。
関連記事
 生成AI時代、広告クリエーターはどう受け止める? 東京藝大・箭内道彦教授に聞く
生成AI時代、広告クリエーターはどう受け止める? 東京藝大・箭内道彦教授に聞く
生成AI時代で、人が手で描くイラストはどのように変わっていくのか。広告業界への影響は? 箭内道彦・東京藝大教授に聞いた。 HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り
HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り
L'Arc-en-Cielのhydeさんが“心酔”した画家が、2015年に78歳で亡くなった金子國義画伯だ。金子画伯は、『不思義の国のアリス』などを手掛け、退廃的で妖艶な女性の絵画を多く残した。その作品を管理し、販売している金子画伯の息子である金子修さんに、アートビジネスの現場の苦労と、芸術を受け継いでいく難しさを聞く。 YOSHIKIが描く「AIと音楽ビジネス」の未来 日本主導のルール整備はなぜ必要か
YOSHIKIが描く「AIと音楽ビジネス」の未来 日本主導のルール整備はなぜ必要か
日本を代表する作曲家・音楽プロデューサーでもあるYOSHIKIに、エンタメ業界でのAI活用の可能性と課題をインタビューした。 着物の「脱恐竜化」目指す 京都の老舗「小田章」5代目が語る、120年目の事業転換
着物の「脱恐竜化」目指す 京都の老舗「小田章」5代目が語る、120年目の事業転換
明治末期に京都市で創業した呉服屋「小田章」。昨年は人気アーティストHYDEとコラボしたファッションブランド「WaRLOCK」(ワーロック)を立ち上げた。120年近く続く老舗企業は、業界の衰退を、どう見ているのか。小田毅社長に、生存戦略を聞いた。 HYDEが愛した金子國義、『不思議の国のアリス』挿絵のNFTが発売 楽天の狙いは?
HYDEが愛した金子國義、『不思議の国のアリス』挿絵のNFTが発売 楽天の狙いは?
楽天グループは、金子國義画伯が描いた『不思議の国のアリス』の挿絵を使用したNFT「金子國義『不思議の国のアリス』シリーズ」を、同社が運営するNFTマーケットプレイスと、販売プラットフォーム「Rakuten NFT」で7月23日より取り扱う。販売開始日は、金子画伯の誕生日に合わせた。 YOSHIKIに聞く日本の音楽ビジネスの課題 THE LAST ROCKSTARSで「世界の市場を切り開く」
YOSHIKIに聞く日本の音楽ビジネスの課題 THE LAST ROCKSTARSで「世界の市場を切り開く」
日本から世界を目指すロックバンド「THE LAST ROCKSTARS」。世界の市場に挑んできたYOSHIKIを中心に、日本の音楽ビジネスの課題と、同バンドによって新たな挑戦を始めた理由を聞いた。 楽天がHYDEとコラボした狙い NFTを軸にグループで水平展開
楽天がHYDEとコラボした狙い NFTを軸にグループで水平展開
楽天が全国6都市全18公演のワンマンツアー「HYDE LIVE 2023」を開催中のアーティストHYDEとコラボを進めている。コラボは複数のグループ各社に及んでいて、NFT付きライブチケットなどを販売中だ。仕掛け人に狙いを聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング