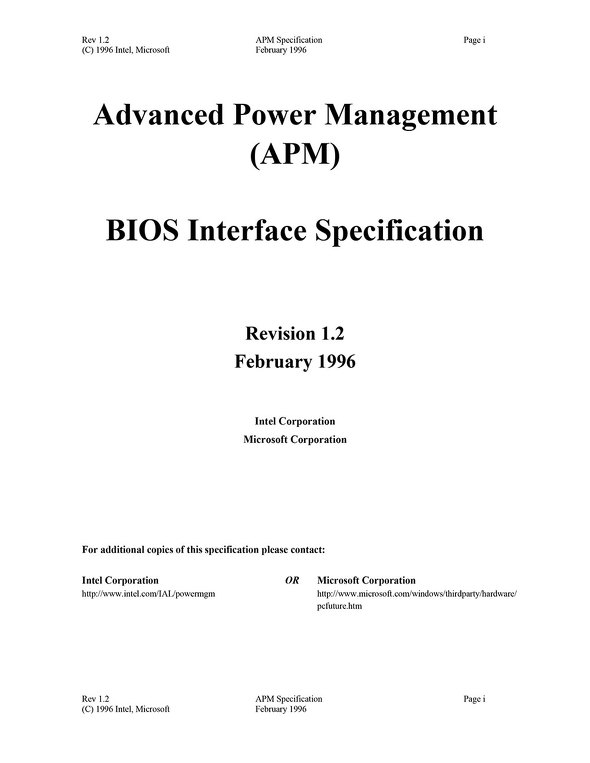ラップトップPCのための基礎技術が生まれるまでの紆余曲折 APMからACPIへ:“PC”あるいは“Personal Computer”と呼ばれるもの、その変遷を辿る(3/4 ページ)
かくして1992年、IntelとMicrosoftは共同で、APM BIOS Interface Specificationをリリースする。その後1993年にはいくつかの修正と機能追加を行ったRevision 1.1、1996年には32bit対応なども追加したRevision 1.2が出ている(写真5)。
このAPMもまた、IAL(Intel Architecture Labs)によって開発されたものだ。
時系列的な話は既に全然追えないのだが、80386のモバイル/組み込み向け向け省電力版という製品企画が持ち上がった時点で、これを扱えるようにする仕組みが必要ということになり、ちょうど立ち上がったばかりのIALのプロジェクトの1つとして、これに取り組むことになったらしい。
とにもかくにも、これでノートPCに向けて、省電力モードを実装することが可能になった。
もっとも当時の省電力はまだある意味原始的であって、要するにモジュール単位で動かすか動かさないかというレベルの話でしかないのだが。それでも、例えばStandbyに入ったらPCMCIAスロットの電源供給を止めるとか、PCを一切触らずに数分たったらシステム全体をStandbyに入れて数分たったらSuspendに入る、なんて動作はこのAPMを利用することで初めて実現可能となった。
このAPM BIOS Specificationもやはり無償で公開され、PC互換機メーカーはこれをインプリメント可能になったので、(メーカー毎のインプリメント次第で性能差というか「どこまでまともに動くか」の違いはあったものの)どこのメーカーもノートPCにAPMをインプリメントすることが可能になった。AMDも1991年にリリースしたAm386SLでSMMを実装し、Intelと同じようにAPM対応のノートを構築できるようになった。
さてではAPMが実装されて問題は解決かというと、そうもいかなかった。問題点として挙げられたことには、
- APMは扱える状態が5種類(常時On/APM有効/APM Standby/APM Suspend/電源Off)しかなく、通知される状況も限られ、APIとして提供される機能も限定的だった
- SMMがOSからTransparent(透過的)に動作するのは良いのだが、この結果SMMの状況を確認するためにはOSからAPM経由で状況を定期的にPolling(状態がどうなっているかをレジスタなどで読み取る)する必要があった
- 同様にSMMがTransparentなため、OSからSMMの動作を止めることが不可能であり、これは一部のリアルタイム処理向けには深刻な影響を及ぼした
- APMで定義される機能は限定的で、このためさまざまな周辺回路はベンダーが独自にドライバなどを使って実装する必要があり、結果非互換性とかOSとの相性問題が発生した
- APMはx86に特化した構造になっており、このため他のプラットフォームに持っていけなかった
などがある。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR