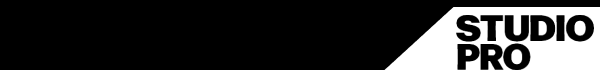「王様戦隊キングオージャー」終幕 “無謀だった”という制作の舞台裏、上堀内監督に聞いた(2/5 ページ)
全ては“勘違い”から始まった
もともと、東映作品でバーチャルプロダクションを使う試みは以前からあったという。「最初は機界戦隊ゼンカイジャーのコックピットなどでトライしながらでした」と語るのは東映テレビ・プロダクションでラインプロデューサーを務める佐々木幸司氏。
上堀内氏も「Ultimatte(豪Blackmagic Designの合成ソフト)を使ったリアルタイム撮影は一度経験していました。ただし、トラッキングなしの書き割り、1枚絵を先に出しておく状態でした」「仮面ライダーセイバーから考えると3年ぐらいやっていますけど、進み度合は階段を1段ずつ上ろうとしていたぐらいだったんですよ」と振り返る。
ところがキングオージャーでは、通常であれば必ず構築する「レギュラーセット」なし、外ロケ以外は東映のLEDスタジオと、ソニーPCLが運営する「清澄白河BASE」のバーチャルプロダクションスタジオ/ボリュメトリックキャプチャースタジオなどで撮影という、進み度合いからするとかなり無謀ともいえる構成で挑むことになった。
「ホップ、ステップ、テークオフですよ」(上堀内氏)
「普通ジャンプだろっていう(笑)」(佐々木氏)
「僕らパラシュートを付けないで飛んだんだと思います。落ちることは考えないぞっていうやり方をしてしまった」(上堀内氏)
そもそも、キングオージャーでバーチャルプロダクションをフル活用するというのは、勘違いの連鎖によるものだった。
東映で数多くの特撮作品を手掛けてきた大森敬仁プロデューサーは、キングオージャーの構想を練っていた際、東映に設立されたばかりのバーチャルプロダクション部から「(もしバーチャルプロダクションを)やるなら早く準備してください」と言われていた。
特撮から少し離れていた大森氏は、これを「バーチャルプロダクションで(撮影を)やっていいんだ」と解釈。キングオージャーの構想を上堀内氏に「バーチャルプロダクションも使えるなら使って」と伝えたところ、上堀内氏は「バーチャルプロダクションでやるんだ」というメッセージに受け取ったようだ。
もともと大森氏から、5つの王国を作るというキングオージャーの構想を聞いて「そんなロケーションあるわけないじゃんと思っていた」という上堀内氏。いわく「最悪な伝言ゲーム」になったものの、キングオージャーで「アニメ的表現を取り入れたかった」という監督の想いもあり、ロケーションの制約が少ないバーチャルプロダクションでの撮影を前提に話が進むことになる。
“見切り発車”で始めた素材集め
バーチャルプロダクションを使うということは、撮影した映像なり、Unreal Engineで作られたバーチャル空間なり、LEDウォールに表示するものが必須。つまり、下絵が必要となる。
上堀内氏は、「いっぱい下絵がないとダメだとなって、いっぱい(日本各地を)回ろうっていう子供みたいな考え方から始まった」「もう、るるぶの出番ですよ」と、九州からスタートし、合計1カ月ほど各地を撮影して回ったという。
ただし、途切れることなく毎年続くシリーズ作品のため、1〜2年は必要な準備を9カ月で行うことになった。それでもテレビシリーズとしては多めの準備期間。当然コストもかさむ。上堀内氏は「ランニングコストを抑えるために、(本編の)撮影が始まったらロケにあまり出ないようにする」と佐々木氏、大森氏に説明。それであればコストを掛ける価値があるとOKが出た。
とはいえ、見切り発車の状態で始めた撮影は、失敗の連続だったという。
「撮影した12Kの360度映像だと解像度が追い付かないので、途中から16Kのカメラに変えて持っていったら、今度は16Kがオンライン(本編集)で処理できないと分かって」(上堀内氏)
「ノウハウがあれば誰か指摘してくれるんですけど、誰も分からない状態から僕らは始めてしまった」「16Kで撮ってきたら『はぁ?』みたいに言われ、『データをダウンコンバートするので1週間もらえますか?』という感じで、恥ずかしいんですがいろいろ学んでいきました」(同氏)
これと並行して、インカメラVFXで使用する各国のバーチャル世界(ワールド)も、Unreal Engineをベースに作り上げていった。
「脚本家とプロデューサーの方でキャラクターの設定は何となく出来上がっていたんです。そのキャラクターをもとに各国の設定書を作って、イメージを出して、企画チームに共有して、コンセプトに発展させていきました」と上堀内氏。各国の最終ビジュアルは設定書をベースにコンセプトアーティストが担当したという。
「僕の設定にコンセプトアーティストが発想を載せた感じです。ビジュアル化したものをアセット製作チームに渡しました」「ただ、シュゴッダムという国だけは、全てのアセットの基盤になると思ったので、Unreal Engineのマーケットプレースでベースになりそうなものを買って、東映バーチャルプロダクション部のスタッフと僕の2人で簡易的な基盤を作り、それを製作チームに渡しています」(上堀内氏)
監督のこだわりによって作り込まれていったバーチャル世界だが、精緻すぎるゆえ、それぞれのワールドはかなり重たいデータに膨れ上がっていた。
ソニーPCLで空間映像プロダクションエキスパートを務める増田徹氏は、上堀内氏のワールドについて「カメラのアングルに入らないところまで、本当に広い世界が作り込まれていて、最初LEDウォールに出したらまともに動かなかった」と振り返る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR