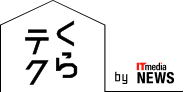ポロプリズムの復活――オリンパス「E-330」:矢野渉の「クラシック・デジカメで遊ぶ」(1/2 ページ)
ポロプリズムの復活
オリンパスファンならば「オリンパスペンF」というカメラには特別の感情を抱いているはずだ。35ミリフィルムサイズを半分にして使うハーフサイズカメラのオリンパス・ペンで大ヒットを記録したオリンパスが、その総仕上げとして世に出したのが「ハーフサイズ一眼レフカメラ」オリンパスペンFだからである。
35ミリカメラのフィルム面を、単純に半分にしてしまえば事は簡単なのだが、オリンパスはここで「オリンパスらしい」こだわりを見せる。ミラー付き一眼レフをどこまで小型化できるかを追求したのだ。
35ミリ一眼と同じ構造にすると、ハーフサイズカメラは、短辺を軸にしてミラーを上に跳ね上げることになる。これではフィルムサイズが小さいのにフランジバック(レンズの後端からフィルムまでの距離)は同じことになり、カメラの厚さは変わらない。
ここでオリンパスが採用したのがミラーを長辺を軸にして横に跳ねる方法だ。これならばフランジバックは飛躍的に短くなる。そして、レンズを通った画像が横に反射され、これをファインダーまで持ってくる方法として「ポロプリズム」(双眼鏡などに利用されている)を採用した。
一般的な一眼レフカメラが本体上部にペンタプリズムを飛び出させた形状をしているのに対して、ポロプリズムはカメラ本体を出っぱりのない直方体にすることに成功した。これはバッグなどへの収納時、場所を取らないので非常に使い勝手が良い。ポロプリズムを採用したハーフサイズ一眼レフは、もちろんオリンパスからしか発売されていないオリジナリティあふれるものだ。だから今だに愛好家が存在するのだ。
デジタルの時代になって、オリンパスはほんの短期間だけ、このポロプリズム構造のカメラを復活させている(実際はポロミラーを使ってさらなる軽量化を図っている)。それが2004年12月発売のE-300、そして今回取り上げる2006年2月発売のE-330の2機種である。
レア物デジタル一眼
2006年発売のカメラを何故「クラシック・デジカメ」として取り上げるのかという意見もあるだろう。今でも現役で使っている方もいるだろう。しかし僕はあえてこのカメラをクラシック・デジカメとしてとらえたい。
なぜなら、今後ポロプリズム(ポロミラー)採用の一眼レフはたぶん発売されないからだ。小型で取り回しが良い一眼レフは、すでにミラーレス一眼が主流になっているし、アマチュア向けの一眼レフは電子ファインダーの視認性が飛躍的に向上したため、コストのかかる光学ファインダーの存在そのものが危うくなって来ているからだ。
今後、このE-330(およびE-300)の希少性はどんどん増していくと思う。掘り起こせばPenの起源にまで逆上ることができる素性の良さ、そしてデジタルの時代にもう一度復活したという事実が最大の魅力だ。現在マイクロフォーサーズのPen「OLYMPUS PEN」がこれほど支持を受けているという事実は、Penブランドの力を証明している。E-330に「Pen」の名前はないが、
解る人にとっては紛れも無い「Pen」の直系なのである。
さらなる希少性
ポロミラーで直方体の筐体を得たE-300だが、その後継機種「E-330」では「レンズ交換式一眼では初のライブビューデジカメ」を実現すべく動いた。E-300では800万だった画素数を750万画素に落としてまで応答速度の速い「Live MOSセンサー」を採用し、撮像素子でのライブビューを可能にしたのだ。
しかし過渡期の悲しさか、この状態(Bモード)ではオートフォーカスができず、マニュアルフォーカスのみとなってしまった。普通はこれで良しとするのだが、ここであきらめないのがオリンパスという会社だ。なんとこのデジカメはポロミラーの光学ファインダー途中にライブビュー専用の小さなCCDを組み込んでしまったのである。こちらの影像(Aモード)は当然オートフォーカスで撮影できる。
背面の液晶でAモードを選ぶとピントをおまかせで快適に撮影ができるが、上がった写真が一回り広い画角なので面食らう。これは視野率92%の光学ファインダーの画像を液晶に写し出しているからだ。現在の機種では考えにくいことだが、これもクラシック・デジカメのひとつの「味」と考えると、慣れるとちょっと楽しい気分になる。自分だけが使いこなせるカメラという意識は、優越感につながるのだ。
図らずも2つの素子(Live MOSセンサー、ライブビューCCD)を内蔵することになったE-330だが、それほどの高い狙いがあるデジカメではない。あくまで必要に駆られて複雑な設計になったに過ぎない。これを技術者の完ぺき主義と感じるか、メーカーの良心とするのかは僕には判断ができない。そんなことよりも、これほど語るべき事柄の多いデジカメが世に出たことを神に感謝するばかりである。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR