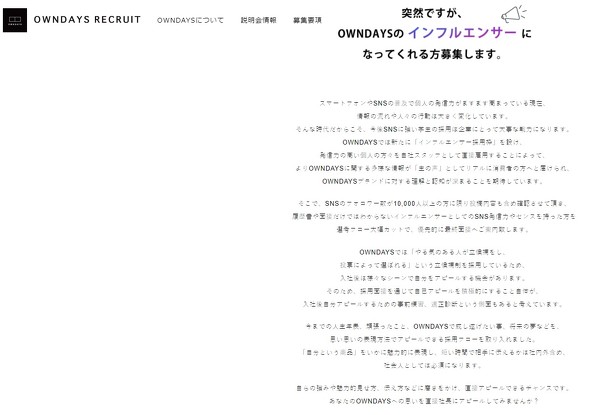フジテレビの女子アナ“ステマ”疑惑が突き付ける「※ツイートは個人の見解です。」のウソ:会社と“個人SNS”の関係
『週刊文春』4月22日号で発覚した、8人のフジテレビ女性アナウンサーの“ステマ”疑惑。6月になり該当する女性アナウンサーと、“仲介”したとされる男性アナウンサーは自身のInstagramで謝罪した。だが、それぞれ「報道された件」に関して「不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした」という、具体的に何が報道され、何が悪かったのかを明示しない、不明瞭な謝罪となった。
9人のアナウンサーはそれぞれ、自身の出演している番組も毎日のように放送されている。だが6月12日時点で、番組などを通じた謝罪はない。5月末にフジテレビは「社員就業規則に抵触する行為が認められた」と発表したものの、そもそも社内のルールに違反しているだけなら、公に謝罪する必要はないはずだ。
皆似通った文章での謝罪だが、「不快な思いをさせたからお詫びする」という文言は、政治家のよく使う定型句で、不快な思いを抱いた視聴者のほうがまずいといった責任転嫁の印象すら与える。
そもそも何が問題だったのか。そして、フジテレビ以外の企業にもそのような問題が発生する芽はないのか、考えてみたい。
なぜキー局の中でフジテレビだけ問題が起きたのか
女優やタレント、インスタグラマーと呼ばれるネット上の有名人が、美容室などのSNS投稿に顔や名前を掲載されている――それだけならよく見る光景かもしれない。ただ、今回の場合、彼女たちがキー局のアナウンサーという、有名人でありながら、1会社員――もっと言ってしまえば、総務省から公共の電波を割り当てられた放送局の局員であることが、問題に大きく作用してくる。
特に、うち一人はフジテレビの夜のニュース番組のメインキャスターでもある。
報道と広告。この2つは、距離をおくべきものだ。それゆえ、ニュース番組のキャスターは特定スポンサーのCM出演などを控えるのが基本である。報道番組内での発言が、自分に金銭を支払っている特定の組織への利益誘導になってはいけないからだ。
そんな中、このキャスターは番組内で“主観が暴走する”傾向も指摘されている。昨年、米国で起きた銃撃事件についてコメントしたことに対し、「差別を助長する発言」だと揶揄(やゆ)する声も一部であがっていた。
報道番組に携わるキャスターが、美容室とはいえ特定の企業の広告に加担し、その理由が「自分が無料でサービスを受けるため」だったというのは、放送人としての自覚をあらためて問うべき事態だ。ニュース番組ではある種の“主張”をしていたにもかかわらず、日常の個人的欲望が報道に携わる者としての自覚に勝ったと解釈されても仕方がない。
これは、このキャスター個人だけの問題ではない。2011年入社から20年入社で、現在フジテレビに在籍する計20人の女性アナウンサーのうち、4割にあたる計8人もの女性アナウンサーが該当する行為をしていた。その上、彼女たちを合コンに斡旋(あっせん)していた男性アナウンサーが美容室との“仲介人”だったというのだ。誰も止める者がいなかったから、ここまで放置されたであろうことを考えると「自分たちは得をしてもいい人間だ」という個人的な自覚と、それを止められない風土が同社にはあり、彼女たちのそういった行動を常習化させたのだろう。
同じように人気女性アナウンサーも抱える他局では問題が起きていないことを考えると、フジテレビのアナウンサーたちが、総務省から有限の電波を割り当てられた放送局から給料をもらっている“公共”の人間としての自覚と、タレントのように扱われる個人としての自覚との線引きができない集団であることが透けて見えてくる。
宣伝や採用 企業が個人の影響力を頼りにしている部分も
だが――彼女たちにも同情の余地がないわけではない。
この数年、SNSで多くのフォロワー数を抱えるいわゆる『インフルエンサー』が、企業からお金をもらい、宣伝を投稿する形の“PR案件”が多く見られるようになっている。投稿が宣伝であることを明示すればそれらはステマにあたらず、インフルエンサーは案件によっては数十万から数百万円の報酬を受け取ることができる。
それだけ、企業側は個人の影響力に力を感じ、お金を払ってでも乗っかろうとしているのだ。フォロワー数の多さで見れば、フジテレビの女性アナウンサーは、インフルエンサーよりよっぽど“インフルエンサー”である。
今回、彼女たちが受け取った報酬はゼロとされている。あくまでも既存のサービスを無料にしてもらうサービスを受けてはいるものの、純粋な利益を得ているわけではないのだ。
ステマ疑惑で名前があがった8人のうち5人は27歳以下であり、中にはミス・キャンパスコンテスト出身者もいる。世代的にも、また自分たちのいた環境をとってみても、自分たちのように多くフォロワーを抱える“インフルエンサー”の投稿が、大きな金銭的な価値を生むことは肌感覚で分かっていたはずだ。写真を掲載していた美容室の料金は、文春の報道によれば2万円~3万円程度である。彼女たちにとってみれば、自分たちの写真や名前を店の宣伝に使われることは、「得をした」どころか「損をした」と感じていても不思議ではない。
正式に契約を交わすのであれば断るであろう自らには損な話も、サービスを受けた後に「載せていい?」と言われたら無碍(むげ)にできない事情もあるだろう(ちなみにここ数年のミス・キャンパスコンテストでは、ミス候補者たちが企業のPR投稿をすると●万円といったプランが存在している。また、運営する広告研究会が、企業から受け取った報酬を“中抜き”し、候補者には一銭も支払わないことがあるなど問題もはらんでいる)。
また、他社だけではなく、所属先の企業が個人の影響力を頼りにしている部分もある。近年では番組のキャスティングをする際に、フォロワー数を基準にする場合も多いという。ネット上で影響力の大きい出演者が番組の告知をしてくれれば、それはネットとテレビの架け橋になる。大きく言えば、「テレビ離れ」といわれている若者たちが、テレビをつけるきっかけになる役割を期待されているといっていいだろう。
アナウンサーは局にとっては、いくらでも宣伝してもらえる自前のインフルエンサーでもある。宣伝してくれるのは、番組の告知だけではない。最近では、企業の採用にSNSを使用するのは当たり前だ。「●●アナウンサーがインスタライブに登場!」といった正式な採用コンテンツまであり、コロナで開きづらくなったリアルでの企業説明会の代替の役割を果たしてもいる。
宣伝や採用の現場で活用している背景にあるのは、企業が「●●さんのインスタに載っていたから」という影響力の大きさに気付き始めていることだ。そうなると、当のアナウンサーとしては普段は局の宣伝に自分のアカウントを使って“奉仕”しているのに、少しでも得をした瞬間に怒られる……と愚痴の1つでも言いたくなるだろう。
会社員個人のSNSは所属企業のものか
ここで、フジテレビに限らず、多くの企業に通じる疑問が浮かぶ。果たして、会社員個人のSNSはどこまで所属企業のものなのだろうか――?
例えば、実名で投稿している会社員のSNSアカウントにはこう書かれていることが多い。
※ツイートは個人の見解です。所属する組織とは一切関係ありません。
これが通用するのであれば――フジテレビの女性アナウンサーたちの罪は軽減されるはずだ。彼女たちも「美容室のサービスが良かったのは個人の見解です。フジテレビとは一切関係ありません」で通したいのではないだろうか。
ただ、騒動の反響を見るに、それはまかり通らなかったということだ。しかし、顔を出している女性アナウンサーたちは、個人の見解と所属先の見解を分けることができない一方で、特に有名人でない会社員たちは「※ツイートは個人の見解です。所属する組織とは一切関係ありません」の一言で乗り切ることができるとしたら、それはおかしな話に感じる。
いくら個人と企業の見解は別、と主張してみたところで、その見解にたどり着くための情報は、その会社の社員であるから得られた情報によって形成されることも少なくない。そもそも「見解」にまで至らず、「うちの会社に有名人の●●が来た」など、社員だから得られた情報を垂れ流しするだけのような投稿もときには散見される。
Twitterが定着して10年以上の時がたつ。実名を出すことで有名になっていく実例も多く存在するこの時代において、「個人で注目を浴びたい」思いが先走り、その燃料になるのであれば、会社のおかげで得られた情報や特権をフルに注入している人は多い。にもかかわらず「見解は別」と主張し、リスクは避けようとするのはいささか説明足らずで、傲慢な行為にも思える。
新聞社の社員記者が差別的発言をしたら、その新聞社に責任は一切ないのだろうか? Clubhouse上で、記録が残らないからといって、テレビ局の局員が局名を明かした上で、その立場だから得られたタレントの裏話をしているのは許されるのだろうか? 芸能事務所からしたら、テレビ局員に自社の“商品”の機密情報を漏らされていることにはならないのか。さまざまな疑問が生まれることになる。
ある旅行会社の対応
もちろん、メディア企業に限らず、最近では自社でSNS運用のルールを策定するところも多い。例えば、ある旅行会社では、海外や国内を問わず仕事で行った旅行先の写真を個人のSNSに掲載することはNGという規定を設けているという。いろいろな場所に行けるという会社が与えた特権を、個人の利益に結び付けるのはNGという線の引き方だ。
フジテレビの女性アナウンサーでいえば、局によって不特定多数の人に見てもらえる放送にのること、フジテレビというブランド力を得られること、タレントと共演できることなどが特権といえるだろう。フジテレビのアナウンサーというだけでフォロワー数が伸びるSNSアカウントは、嫌な言い方をすればフジテレビのブランド力を“着服”しているともいえる。では、その“特権の着服”の上に成り立っているアカウントである以上、自由な投稿は許されないのか。
そして、どこまでが“特権の着服”なのだろうか。今回、問題になったアナウンサーの1人は、学生時代から使用していたInstagramのアカウントを、フジテレビ社員になってもそのまま使用している。その場合「入社日前日までに彼女をフォローしていた人(=フジテレビのブランド力を使用せずに獲得したフォロワー)には自由に影響力を行使していい」という理屈もまかり通る気がするがどうなのか。
その他の、入社後にフジテレビアナウンサーとしてアカウントを作成した人の場合、そのフォロワ―の何割が「フジテレビアナウンサーである」というブランドに魅力を感じてフォローした人なのか。
このように、有名企業の会社員が個人でSNSを使用している場合、どこまでが会社のフォロワーで、どこまでが個人のフォロワ―なのか、線引きが難しい。
しかし、個人のSNSである以上、彼らの多くは全てのフォロワーを自分の力で得られたかのような錯覚をする。ここが問題の起点になる。社員個人のSNSアカウントの権利は、企業に属するものとする――などとしたら、企業をやめる社員も出てくるかもしれない。
「インフルエンサー採用」を実施する企業も
企業としても悩ましいところだろう。
企業としては社員のSNS使用に統制を強めたほうが安心だが、統制を強めれば強めるほど、それぞれのSNSに個性はなくなり、ひいては影響力の低下につながる。
メディア企業に限らず、最近は社員個人のSNSを、企業自体の認知向上や採用のきっかけにしようとするような動きもある。フォロワーが多い大学生は、それだけで面接の段階を割愛できるような採用制度を実施する企業もあるし、特にベンチャー企業などは、ネット上の有名人を重宝する。
アイウェアの製造販売を手掛けるOWNDAYS(那覇市)はSNSのフォロワー数が1万人以上の候補者に対し、選考フローを大幅にカットして優先的に最終面接を受けさせる「インフルエンサー採用」を実施した。
会社の認知度向上のために社員にSNSの利用促進をし、“目標フォロワー数”を定めたり、“バズる投稿”の指導をする企業もあるくらいだ。だが、その塩梅(あんばい)は難しい。
「500いいね!」で書類選考パスを謳(うた)うサイバー・バズ(東京都渋谷区)では、募集要項に「入社後”インフルエンサー”として活動する社員の募集ではございません」と明記するなど、SNSをうまく使える学生を歓迎する一方、社員としては、その技術を個人の知名度アップに利用されすぎても困るという思考が透けて見える。
企業側は個人にSNSをうまく利用してもらったほうがプラスも多いが、リスクも大きくなるのだ。
フジテレビ社長がいう“正しい指導”とは何なのか?
フジテレビ騒動から社員個人のSNSと会社の関係を考えるとさまざまな疑問が思い浮かぶ。少なくとも、今後、仮にきちんとお金を払っていたとしても、美容室の投稿をするアナウンサーは現れないはずだ。では、美容室投稿はNGだとして、好きなキャラクターをSNSで発信することはNGなのだろうか?
放送など、形式の定まった場所では知り得なかった個人の趣味・趣向を知ることができるのがSNSの面白い部分でもある。個性の滲(にじ)む場所がSNSだ。統制を強めた先に残るのは、番組告知のみの味気ない投稿たちではないだろうか。
フジテレビの遠藤龍之介社長は5月の会見で「指導が行き届いていなかったことなどに対して、社としての責任を痛感している」としている。では、“正しい指導”とは何で、それは誰が知っているのだろうか。線引きの難しさに直面しているのはフジテレビだけではないはずだ。(敬称略)
著者プロフィール
霜田明寛(しもだ あきひろ)
1985年東京都生まれ。東京学芸大学附属高等学校を経て、2009年早稲田大学商学部卒業。文化系WEBマガジン『チェリー』編集長。『マスコミ就活革命〜普通の僕らの負けない就活術〜』(早稲田経営出版)など、3作の就活・キャリア関連の著書がある。ジャニーズタレントの仕事術とジャニー喜多川の人材育成術をまとめた4作目の著書『ジャニーズは努力が9割』(新潮新書)は4刷を突破のヒット。J-WAVE『STEP ONE』・SBSラジオ『IPPO』などメディア出演も多く、日々の仕事や映画評、恋愛から学んだことなどを発信するネットラジオVoicy『霜田明寛 シモダフルデイズ』は累計再生回数200万回・再生時間15万時間を突破するなど話題に。Twitter。
関連記事
 Zoom面接のプロが教える「採用のオンライン化」で得られるもの、失われるもの
Zoom面接のプロが教える「採用のオンライン化」で得られるもの、失われるもの
学生に対する企業の採用選考が6月1日、解禁された。この3カ月の間に、学生の企業選びの基準が大きく変化している。加えてオンライン面接を導入する企業も増え、選考の方法そのものも様変わりした。3冊の就活本を執筆し、この10年間、学生への就活指導をしてきた筆者が、オンライン面接で判断しやすくなるもの・判断しにくくなるものについて伝えていく。 滝沢秀明ジャニーズ事務所副社長 10年前にYouTubeに目を付けていたビジネスセンスと先見性に迫る
滝沢秀明ジャニーズ事務所副社長 10年前にYouTubeに目を付けていたビジネスセンスと先見性に迫る
新型コロナウイルスでライブや演劇は軒並み中止になる中、ジャニーズ事務所は防護服を医療従事者に寄付したり、チャリティーソングを制作したりすると発表。単に利益を求める営利企業であるわけではなく、社会貢献への意識が強い組織であることをあらためて印象づけた。社会貢献活動のプロデューサーを務めるのが同事務所の滝沢秀明副社長だ。滝沢秀明は実は10年前にYouTubeに目を付けるなど“ビジネス的な先見性”を持つ。“ジャニーズを具体例としたビジネス書”を執筆した筆者が解説する。 滝沢秀明がジャニー喜多川の「後継者」となった理由
滝沢秀明がジャニー喜多川の「後継者」となった理由
日本の芸能史を変えてきた男たちに学ぶ仕事術と人材育成術を3回に分けてお届けする中編。なぜ滝沢秀明はジャニー喜多川の「後継者」となれたのか? その理由に迫る。 ジャニー喜多川は偉大な「2軍の監督」だった 部下の個性伸ばす「ジャニーズ式教育法」とは?
ジャニー喜多川は偉大な「2軍の監督」だった 部下の個性伸ばす「ジャニーズ式教育法」とは?
会社の部下をいかに成長させるか――。そんな悩みを抱えている管理職も多いだろう。どのように部下が自らの長所や課題を見つけ、伸ばすことをサポートできるか。多くの優秀な人材を生み出してきたジャニーズ事務所の創始者、ジャニー喜多川氏の教育方法からヒントを探る。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 堀江貴文が語る、ジャニーズ事務所「新時代の海外戦略」――“嵐×Netflix”はテレビ主役時代の「終わりの始まり」
堀江貴文が語る、ジャニーズ事務所「新時代の海外戦略」――“嵐×Netflix”はテレビ主役時代の「終わりの始まり」
IT起業家として、インターネット黎明期から第一線を走り続けているホリエモンこと堀江貴文。堀江の行動原理はしばしば「多動」とも呼ばれているが、その多動的な行動を支えているのは実はスマートフォンだ。堀江は自身の仕事においてPCはほとんど使わず、スマホを使って多くの関係者とコミュニケーションを取りながら複数のビジネスを回している。第2回はジャニーズ事務所の海外戦略などを例に、動画配信が変えるビジネスの変化について語る。 ジャニーズという「努力の天才たち」から学んだ仕事哲学
ジャニーズという「努力の天才たち」から学んだ仕事哲学
日本の芸能史を変えてきた男たちに学ぶ仕事術と人材育成術を前・中・後編の3回に分けてお届けする。今回は前編――。 ジャニー喜多川が育成 TOKIO国分太一、V6井ノ原快彦に学ぶ「最強のコミュニケーション術」
ジャニー喜多川が育成 TOKIO国分太一、V6井ノ原快彦に学ぶ「最強のコミュニケーション術」
日本の芸能史を変えてきた男たちに学ぶ仕事術と人材育成術を3回に分けてお届けする後編。ジャニーズの中でも特にコミュニケーション技術を学べるのがTOKIO国分太一とV6井ノ原快彦だ――。 「JKトレンド予測」ランキング 2020年は「オタク」と「病み系」がけん引
「JKトレンド予測」ランキング 2020年は「オタク」と「病み系」がけん引
「現役女子高生の2020年トレンド予測および2019年下半期トレンド」に関する調査。有名人は「オタク」、アイテムは「病み系」がそれぞれ2020年のJKトレンドをけん引するようになると分析している。「2020年に流行しそうな人・アイテム」の具体的な内容は? JC・JK流行語大賞2019が発表 「Official髭男dism」「ぴえん」「ハンドクラップダンス」「Soda」などがランクイン
JC・JK流行語大賞2019が発表 「Official髭男dism」「ぴえん」「ハンドクラップダンス」「Soda」などがランクイン
女子中高生向けのマーケティング支援などを手掛けるAMF(東京都中央区)が”JCJK調査隊”の選考結果をもとに、「2019年の流行語大賞」および「2020年のトレンド予測」を発表した。「ヒト部門」「モノ部門」「アプリ部門」「コトバ部門」の4つに分類。その結果は? ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと
ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと
平成のネット史の最重要人物「ひろゆき」への独占インタビュー。ひろゆきの仕事観・仕事哲学を3回に分けて余すことなくお届けする。中編のテーマは「働き方」――。 ひろゆきが“日本の未来”を憂う理由――「他人は変えられない」
ひろゆきが“日本の未来”を憂う理由――「他人は変えられない」
「平成ネット史」の最重要人物、ひろゆきへの独占インタビュー最終回――。ひろゆきはなぜ「日本の未来」を憂うのか? 【独占】ひろゆきが語る「“天才”と“狂気”を分けるもの」
【独占】ひろゆきが語る「“天才”と“狂気”を分けるもの」
平成のネット史の最重要人物「ひろゆき」への独占インタビュー。ひろゆきの仕事観・仕事哲学を3回に分けて余すことなくお届けする。前編のテーマは「“天才”と“狂気”を分けるもの」――。 ひろゆき流“オワコン日本”の幸福論―― 他人とズレていたほうが幸せになれる!!
ひろゆき流“オワコン日本”の幸福論―― 他人とズレていたほうが幸せになれる!!
ひろゆきこと西村博之氏が、令和時代を迎える日本が今後どんなふうにヤバくなるのか、沈みゆく日本で生き抜くためにはどうしたらいいのかを3回にわたって提言。最終回は“オワコン日本”でも「おいしく」生きていくための方法論。 ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由
ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由
ホリエモンはなぜ「子宮頸がんワクチン」を推進しているのだろうか。その裏には、政治に翻弄された「守れるはずの命」があった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング