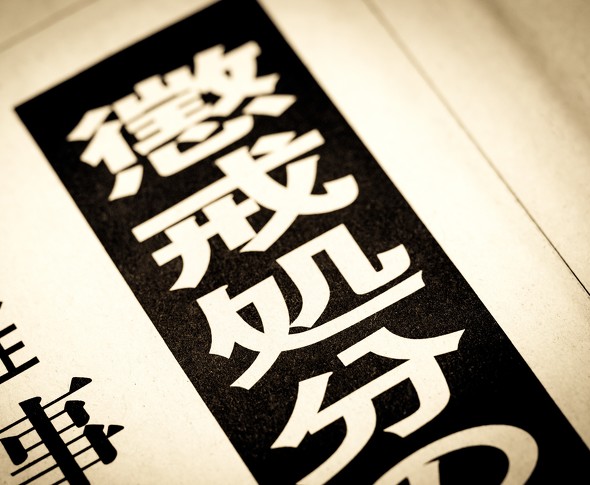「会議にふさわしくない」とバーチャル背景を禁止 リモハラ上司に懲戒解雇は妥当?:法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A(3/3 ページ)
今回のケースでは、過去に取引先からバーチャル背景に関してクレームがあったということもあり、バーチャル背景の使用禁止が直ちに「(2)業務上必要かつ相当な範囲を超え」るものであるとされる可能性は低いと考えられます。
従って、バーチャル背景の使用を禁止したことのみをもって直ちにパワハラに該当するとはいえませんが、部長が部下のプライベートな部屋の様子について話題にする、服装や体型をからかうなどの事情があれば、これらの行為を総合的に評価して、業務上必要かつ相当な範囲を超えるものと判断され、部長の行為がパワハラに該当することもあり得ます。
このように、実際にパワハラかどうかを判断するに当たっては、言動の目的、言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、行為者との関係性、社員の身体的または精神的な苦痛の程度など個別具体的な諸事情を総合考慮する必要があります。
懲戒処分は可能か?
懲戒処分は、行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法15条)。行為の内容などに対して重すぎる処分は無効になるケースも多いので、注意が必要です。
今回のケースでは、前述の通り、部長が部下に対して業務上の理由でバーチャル背景の使用を禁止したということのみでは、パワハラとなる可能性は低いと思われます。したがって、バーチャル背景の使用を禁止したという行為だけで部長を懲戒処分にすると、懲戒処分は無効になる可能性が相応にあります。
部長が部屋に言及していたら?
では仮に、部長が部下のプライベートな部屋の様子について話題にする、服装や体型をからかうなどの追加的な事情があった場合を考えてみます。
懲戒処分は、行為の内容や回数、継続性など個別具体的な事情を総合考慮して検討しますので、どのような処分が妥当であるかは一概には言えませんが、実務上、からかい行為の事案では比較的軽い処分がなされることが多く、場合によっては厳重注意にとどめることもあります。
このような事情があった場合、もちろんケースバイケースではあるものの、懲戒処分にはせず厳重注意にとどめるか、懲戒処分をするにしても比較的軽い処分(譴責処分等)を検討するのが妥当である場面が多いと思われます。懲戒処分の種類などについては、連載第1回「IT弱者の部長に『こんなのも分からないんですか?』部下の発言でもパワハラにあたる?」で解説していますので、こちらもご覧ください。
会社が取るべき対応は
バーチャル背景の使用禁止が法律的にはパワハラに該当しなくとも、プライベートな自宅の空間を見せることに抵抗のある社員もいるかと思われますので、プライバシー保護の観点から配慮は必要です。プライベートな自宅の空間を見せないようにするために、会社の会議室や会社のロゴマークの入った背景を用意して社員に配布し、Web会議で使用させるなどの対応が考えられます。
また、リモート環境下でパワハラが発生した場合も、事業場でパワハラが発生した場合と同様の対応が必要です。具体的には、(1)相談への対応、事実関係の確認・調査(ヒアリングなど)、(2)会社としての対応(懲戒処分など)の決定、(3)相談者・行為者へのフォロー、(4)再発防止措置などを実施する必要があります。
労働施策総合推進法第30条の2第1項には、会社のパワハラ防止義務が定められています。パワハラ防止義務を誠実に順守していなければ、ハラスメント問題が生じた際、会社が適切な防止措置や相談対応を行っていなかったとして、会社の安全配慮義務が問われる可能性があります(会社のパワハラ防止義務については、連載第8回「『テレワークなんだから、土日にもメールを返せ』部長の要求はパワハラ?」で解説しています)。
リモート環境であるかどうかに関わらず、会社は一般的なパワハラやセクハラについて正しく理解し、防止措置を取っておくことが重要です。その上で、リモート環境下で起こりやすいハラスメントやトラブルについて理解を深め、対応していくのがよいでしょう。
高井正巳(法律事務所ZeLo・外国法共同事業)
2013年東北大学文学部卒業。同年、裁判所入所。スタートアップ企業の人事・総務部などを経て、2019年9月法律事務所ZeLoに参画。人事・労務分野のリサーチなどを中心に業務を行っており、日常的な労務相談やIPO支援、人事・労務に関する記事執筆などのサポートに取り組んでいる。
法律事務所ZeLo・外国法共同事業
2017年3月に設立された、企業法務専門の法律事務所。「From Zero to Legal Innovation」を掲げ、スタートアップから中小・上場企業まで、企業法務の幅広い領域でリーガルサービスを提供している。AIによる契約書レビュー支援ソフトウェアなどを開発する株式会社LegalForceと共に創業されており、リーガルテックやITツールを積極的に業務に取り入れ、企業の経営と事業の成長をサポートする。2020年に設立したZeLo FAS株式会社と連携し、M&Aやファイナンスなどにも強みを有する。
関連記事
 時給制の社員が、勤務時間が長い日にばかり有給を取得 なんとかできないのか?
時給制の社員が、勤務時間が長い日にばかり有給を取得 なんとかできないのか?
一部の時給制の社員が、勤務の予定時間を長く設定した日に集中的に年次有給休暇を申請しています。勤務予定時間が長ければ長いほど賃金が高くなるため、他の社員から不公平だと声が上がってきました。どうすれば良いでしょうか。 よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……
よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……
当社の管理部門では毎年3月から5月は繁忙期で残業が多くなります。それ以外の月はそれほど残業はないのに、よりによって社会保険料が決まる4〜6月の給与だけが残業代で高くなり、「社会保険料が高額で、通常の給与に見合わない」と社員から不満が噴出しています。 “残業代切り捨て”が違法なら、未払い分を「さかのぼって支給」は義務なのか?
“残業代切り捨て”が違法なら、未払い分を「さかのぼって支給」は義務なのか?
これまで毎月の給与処理で残業代の計算をする場合、残業時間を15分単位で集計しており、15分未満の時間は切り捨てて運用していたのですが、従業員からその集計方法は違法ではないかとの指摘がありました。法的に問題があるのでしょうか。 「優秀だが、差別的な人」が面接に来たら? アマゾン・ジャパン人事が本人に伝える“一言”
「優秀だが、差別的な人」が面接に来たら? アマゾン・ジャパン人事が本人に伝える“一言”
多様性を重視するアマゾン・ジャパンの面接に「極めてだが優秀だが、差別的な人」が来た場合、どのような対応を取るのか。人事部の責任者である上田セシリアさんに聞いた。 「部下を育てられない管理職」と「プロの管理職」 両者を分ける“4つのスキル”とは?
「部下を育てられない管理職」と「プロの管理職」 両者を分ける“4つのスキル”とは?
日本企業はなぜ、「部下を育てられない管理職」を生み出してしまうのか。「部下を育てられない管理職」と「プロの管理職」を分ける“4つのスキル”とは? 転職市場で求められる優秀な管理職の特徴について解説する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング