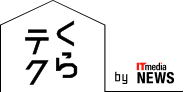コンパクトデジカメで夜桜を撮影するコツ:デジカメ「超」基礎解説 番外編
4月6日、東京都でも桜の満開宣言が出されました(気象庁)。桜の撮影については連載の「今日から始めるデジカメ撮影術」(第138回 桜の花と撮り方の関係)でも説明していますが、夜桜についてはまた注意すべき点が変わってきます。気軽に持ち運べる、コンパクトデジカメで夜桜撮影をする際に注意しておきたいポイントを確認しましょう。
暗所撮影で気をつけること
まず気をつけたいのが、暗い夜間の撮影であるということです。暗い場所で適切な露出(明るさ)を得る設定を自分で施すには、絞りとシャッタースピード、それにISO感度の関係を理解する必要があります。これについては以前説明したので割愛しますが、基本的には暗い場所に適した撮影設定――絞りを小さくし、シャッタースピードを上げ、ISO感度を上げる――を施す必要があります。
ですが、手動ですべての設定を施すのは簡単なことではありませんし、コンパクトデジカメではマニュアル設定できる範囲の限られている機種も少なくありません。そこでまずはカメラの「夜景」撮影モードを利用しましょう。夜景モードにするとフラッシュがオンになる機種も少なくありませんが、手前に人物などを入れない場合、これはオフにしておくことをお勧めします。フラッシュの光りが届く範囲だけが明るく写り、周りが暗くなるという失敗写真の元となるからです。
カメラをしっかり固定することも大事です。どうしても暗い場所の撮影となるため、設定をカメラ任せにしていてもシャッタースピードは遅くなりやすく、手ブレを起こしやすいからです。
下は夜の公園で咲く桜をコンパクトデジカメの夜景モードで撮影したものですが、ISO感度がその機種のオート撮影の上限である1600まで上がっているにもかかわらず、シャッタースピードが1/10秒までにしかならず、結果として手ブレを招いています(一般的には、シャッタースピードが1/30秒以上ないと手ブレすると言われます)。荷物になってしまいますが、このような事態を防ぐため、可能ならば三脚を使いたいところです。近くにカメラをおける場所があるならばセルフタイマーを使うのも手です。
ホワイトバランスに注意
最近のコンパクトデジカメは、カメラが撮影状況を認識して自動的に最適な撮影モードを設定してくれる機能を備えていますが、その機能も万能ではありません。特に問題となるのが桜を照らす光源の種類です。
最近の機種は、自動シーン認識による夜景モードのほかにも、高速連写と重ね合わせ処理を用いて、手持ちでの夜景撮影を可能とした「手持ち夜景モード」など、暗い場所での撮影に適した撮影モードを複数持っているものも珍しくありません。これらはいずれも優秀ですが、複数の光の種類までも考慮して、見た目そのままに撮影するのは非常に困難です。
理想的なのは、その場所でノートなど白い紙などを使い、その場所に最適なホワイトバランスを設定してやることですが、「白熱灯」「蛍光灯」などプリセットされているホワイトバランスを設定することで、見た目に近い色合いで撮影することが可能となります。オート撮影モードではホワイトバランスを変えられない機種もありますので、その際には撮影モードを「P」(プログラムオート)などに変更し、ホワイトバランスを調整しましょう。その際には暗い場所での撮影となるので、ISO感度も高めに設定することもお忘れなく。

 フルオートで撮影したところ桜の花びらが緑がかってしまったので(写真=左)、撮影モードをプログラムオートに切り替え、プリセットのホワイトバランス「蛍光灯」を選択したところ、肉眼に近い感じになりました(写真=右)
フルオートで撮影したところ桜の花びらが緑がかってしまったので(写真=左)、撮影モードをプログラムオートに切り替え、プリセットのホワイトバランス「蛍光灯」を選択したところ、肉眼に近い感じになりました(写真=右)夜桜は暗所での撮影であること、光源の種類や位置もさまざまと、被写体としては難易度の高い部類に入ります。加えて、手前に人物を入れて撮るとなると、さらに考慮すべき点と活用したいテクニックがありますが、それについてはこちら(今日から始めるデジカメ撮影術:第134回 イルミネーションと人物の関係)を参考にしてください。
ですが、「最適な撮影モードを選ぶ」「カメラを固定する」「フラッシュは使わない」「ホワイトバランスに注意する」この4つに注意すれば、手軽に持ち歩けるコンパクトデジカメでも、きれいな夜桜の写真を撮ることができます。桜が楽しめるのは1年1回、ぜひ夜桜の撮影を楽しんでください。
関連記事
 今日から始めるデジカメ撮影術:第138回 桜の花と撮り方の関係
今日から始めるデジカメ撮影術:第138回 桜の花と撮り方の関係
春といえば桜。その日の天候、背景の選び方、レンズの選び方、光の向き、などなどで桜はいろいろな表情を見せてくれる。いろいろな撮り方できるのが面白さでもある。 デジカメ「超」基礎解説:番外編 イルミネーションを「キラキラ」撮る方法
デジカメ「超」基礎解説:番外編 イルミネーションを「キラキラ」撮る方法
ふと街中で足を止めると、さまざまなイルミネーションが街を彩っていますが、ぱっとカメラを向けてもその“キラキラ”感は意外に残しにくいもの。風景としてのイルミネーションを「キラキラ」撮る、ちょっとした方法をご紹介します。 デジカメ「超」基礎解説:「コントラスト」「位相差」2つのAFを理解する
デジカメ「超」基礎解説:「コントラスト」「位相差」2つのAFを理解する
快適な撮影に欠かせないオートフォーカス。デジタルカメラでは主に「コントラストAF」「位相差AF」の2つの方式が用いられています。その仕組みと違いについて理解しましょう。 デジカメ「超」基礎解説:ISO感度と写りの関係を理解する
デジカメ「超」基礎解説:ISO感度と写りの関係を理解する
写真の明るさである露出は絞りとシャッタースピードによって決定されますが、実はもうひとつ、露出に大きな影響を与える要素がデジタルカメラにはあります。それが「ISO感度」です。今回はISO感度について理解を深めましょう。 デジカメ「超」基礎解説:絞りとシャッタースピードの関係を理解する
デジカメ「超」基礎解説:絞りとシャッタースピードの関係を理解する
最近のデジカメは優秀で、フルオートでもきれいな写真が撮れますが、基礎的な事柄を理解するだけでより操作の幅が広がり、さまざまな撮影を楽しめるようになります。そんな基礎を解説していきます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR